{ 海印三昧という仏教の深い思想をフアンタジ−にして、
分かりやすく出来ないかと試みた音風祐介の作品 }
哲学ファンタジー 海
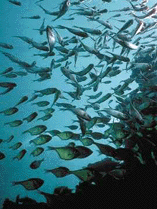
私は地下鉄に乗っている。その時、私は海の中にいるような気持ちになった。座っている人もいる。吊革につかまりながら立っている人もいる。その人達はみな色々な魚が衣服をつけているようだった。奇妙な錯覚だ。その時の私にとって地下鉄は深い海だった。その深さのためか、魚も眠る時があるせいか、ひどく静かである。背広を着た魚というのは妙なものだ。隣の魚とビジネスについて喋っているらしい。ゴトコドと変な音がする。私には遠い海の外で嵐が吹きまくっている激しい波の音のようにも聞こえる。
突然、電車が駅にとまった。人々は駅に吐き出される魚の群れの様だった。そして、衣服を着た魚の群れが入ってきた。この駅の構内は深い海の洞窟の中の宮殿の様だった。 私の前に座った魚は眼鏡をかけた中年だ。彼は新聞を広げると熱心に読み出した。隣に座った魚は若い女だ。人魚の様につるつるとした足をだしている。 そこに年取ったお祖母さんが入ってきた。私は故郷にいる祖母を思い出した。席をかわってあげたいが、ちょっと気恥ずかしいので躊躇している。二十才前後の若い男が数人 座っているのだから、直ぐにかわってあげればいいのにと勝手なことを考える。
一向に誰も席を譲らない。私は勇気を出して、おばあちゃんに声をかけて、逃げるように海の中を泳いで隣の車両に移って行った。私は深海を泳ぐ魚のようなものだ。泳ぎにかけては誰にも負けないつもりだ。私はいつかスキ−に行ったことを思い出した。あの銀世界は
全てが真っ白な色をした、実に不思議な海だった。銀色に輝く雪の海だった。宇宙人の様な魚はみんな長い下駄を履いていた。まるで熱帯魚の様に実に様々な色とデザインのウエアを着て、その泳ぐ動きの早さは格別だった。 それにあの細長い下駄はよく出来ていた。なにしろ、転ぶと直ぐに外れるから怪我はしない。そして、直ぐにワンタッチで履ける。リフトで山を上る時の景色は素晴らしい。雪で真っ白になった樹木が無数にはえている。斜面は雪の結晶で宝石の様に輝いている。まるで天国の坂道の様な感じがした。あそこが銀色の海だったらという私の空想は楽しかった。
しばらくして、私は 次の駅でおりようと足早に出口に向かった。そしてうっかり、座っている若い男の足を踏んでしまった。彼は鮫の様な顔をしていた。口が大きかった。そして、大きな白い歯は鋭く切れそうだった。おまけに細い目が左右に長かつた。黒い瞳はどんよりよどんだビ−ダマの様で、私をにらみつけた。私ははっとして、謝ろうとしたが、その男が鮫そっくりの顔をしていたので、あっけにとられていた。私はしばらく彼の顔をまじまじと見つめていた。
「痛いですね」とその若者はにこりと微笑した。私は鮫の様な男がいかにも上品な紳士の様な
雰囲気で言ったので二度びっくりした。そして、すみませんと私は頭をさげた。そして、私は冷や汗をかきながら、駅のプラットホ−ムに出た。
駅名に漢字で『海』と書いてあった。私は確か、大手町に来た筈だと思って、立ち止まった。しばらくぼんやりその海という文字を眺めていた。私はのどがかわいていることを思いだし、新聞を売っている叔母さんの所に行き、缶入りのアイスコ−ヒ−を買った。
「ここは大手町ですよね」と私は質問した。まぐろの様な女はけげんな顔をして、「ここは海ですよ」と答えた。
私は不信の目で彼女を見詰め、コ−ヒ−を飲んだ。ああ、そのおいしかったこと。 昔話に出てくる竜宮城の素晴らしい飲み物もこれ程おいしくはあるまいと私は思った。私は缶をゴミ箱に捨てると、しばらく竜宮城のことを考えた。それから、天国とか極楽とか四次元の世界とかについても私は考えてみた。そのように、私は何かとてつもない異次元の素晴らしい世界を夢見た。しかし、ここは
深い海の通路の様な所だった。大理石の様にすべすべした肌色の壁や天井が見える。私には深い海の広い洞窟に思えた。私はエレベ−タ−に乗った。海の外の青空を早く見たい気持ちで一杯だった。私はゆっくりゆっくり泳いで上昇していくのだ。上に出ると、改札口がある。今度は長い長いトンネルの様な所に出た。トイレからは恐ろしくも大きな蛸が出てくる様な気がした。私は青空を見たいと切に願いながら、ひっそりと泳いだ。
途中で腰にピストルをさげている二人の男が喋りながら私を見ている。彼らはイルカの様な魚だった。彼らは黒い帽子をかぶって、私の方を見ていた。
突然、イルカの背の高い方が、「もしもし」と声をかけてきた。「宝くじを落とされたようですけど」とイルカの警察官は微笑しながら言った。
私は数日前 買って、ポケットに入れたまますっかり忘れていたのだ。先ほど歩きながらハンカチを取り出した時に、落としたのかもしれない。私は軽く礼を言って、宝くじ五枚程 手にしたまま歩き出した。背後から、イルカの警察官が言った。
「もしかしたら、その宝くじ当たっているかもしれませんよ。僕の記憶によれば、確かその数字だったと思います。早い内に調べた方がいいと思いますよ」
私はどきりとした。宝くじが当たっていたら、大金持ちになれると私は思った。向こうからぞろぞろ鮭の様な顔をした紳士が歩いてくる。この暑いのにネクタイをしめている。
東京駅の外は青空だった。私はついに海から顔を出した魚の様に飛び跳ねた。目の前の蛸の様なおっさんが目を丸くして私を見た。私はうきうき、わくわくしながら外に広がる夏の光を見た。光の海だ。暑い。生命の喜びと苦悩がここにはある。凄い勢いで走る車は鮫か? それともシャチか。それとも鯨か。変な臭いのする排気ガスを出す所はきっとたちの悪い奴に違いない。第一、ぶつかると死にそうだ。恐ろしい。私のめざす所は本屋なのだ。
広い道路。海と空が溶け合う所だ。溶け合う。何て素晴らしい言葉だろう。車のシャチや鮫。行き交う背広を着た魚。美しい肌をさらした女の魚。塔の様にそびえるビルはどこかの島の様に見える。
そして、広場に歌を歌う、若者の集団があった。
歌はこう言っている。
太陽と海の重なる水平線に向かって、私はうっとりと泳いでいこう。
赤を中心としてあらゆる色に変化する西の空に向かって、私はまるで温泉にでも入っている様な気分で泳いでいこう。 白いかもめが飛びかい、海の波のささやきの聞こえる所、その天国の様な無垢の色の広がる所、めがけて泳いでいこう。そして、時に不安が横切る時に、私は泳ぎながら歌うのだ。
わたしの肉体は海の放つ香りと美しき流れにのろう。魂からほとばしりでる喜びと悲しみの二重奏がすべての人の魂を生命の海の永遠の流れに運び去る。 わたしの芸術は霊と水によって復活する。汚れた魂を心地よいシャワ−で浴びるようにして、洗い清め、美しい生命の流れを見る。
清らかな天使の歌声のごとく、海の風、海の波、夕日の沈む色の変化、鳥の鳴き声、魚の泳ぎ、それらはみな音楽となり、いのちの交響曲となって泳ぐ者の頭上に響く。
憂いある者よ、憂いを去れ。悲しむ者よ、海の神秘を見よ。幸福を感じる者よ、全てが海のいのちのたまものであることに感謝せよ。こうして、海には霊の風が吹く。 詩人よ。ありとあらゆる美の誘惑の手口を使って すべての人の魂に、ここに泳ぐこのいのちの海こそ天国であり、極楽であることを知らせよ。
あちこちには熱帯魚の様な美しい色をした魚が泳ぎ、海水は太陽の差し込む位置により、千変万化の色となり、花火の様に大空に咲く巨大な花となる。そして、どこからともなく、軽やかで楽しく、それでいて深遠な音楽が聞こえてくる。
ここがどこであろうと、ここは生命の海なのだと。地下鉄の中であろうと、太陽の照る広場であろうと、雪の原っぱであろうと、秋葉原の電気街であろうと、アパートの部屋の中であろうと、どこであろうと、ここは生命の海なのだと。
私は胸が震えた。感動に震えながら、泳ぐように本屋にむかった。
あそこには未知の宝庫がある。そして、そこの喫茶室で、飲み物を飲める。私の耳にはその美しい歌が響いている。ここは生命の海だ。ここは不滅のいのちの海だと、歌は唄っている。
その時の私はもはや宝くじのことなんかどうでも良かった。このいのちの海の発見こそ宝の山の発見以上のことに思えたのだから。
音風祐介
E−Mailアドレス
karonv@hi-ho.ne.jp