|
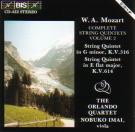
|
モーツァルト:弦楽五重奏曲第4番
K.516
演奏:オルランド弦楽四重奏団、今井 信子(ヴィオラ)(BIS BIS-CD-432♪♪♪)
6曲あるモーツァルトの弦楽五重奏曲のなかでは、アンリ・ゲオンが「駆けめぐる悲しみ」と表現した第4番が特に知られています。
オルランド弦楽四重奏団と今井信子(ヴィオラ)の演奏では、ゆっくりめのテンポもあって、この曲が持っているもう一つの顔、優雅でしなやかな面を聴くことができます。
|
|
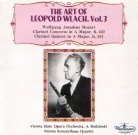
※写真は、ワーナー時代のジャケットです。
|
モーツァルト:クラリネット五重奏曲
K.581
演奏:ウラッハ(クラリネット)、ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団(MCAビクター MVCW-19020 \1,845)
ウィーンの宮廷オーケストラのクラリネット奏者、シュタードラー兄弟と親しくなったモーツァルトが、シュタードラーの依頼により作曲したのがクラリネット五重奏曲K.581とクラリネット協奏曲K.622の2曲で、いずれも名曲として広く知られています。
ウィーン・フィルの首席奏者として活躍したウラッハの演奏は50年近く前の古い録音(1952年)ですが、ウィーンの情緒豊かな香りを伝える演奏は、21世紀にも聴き継がれる価値があると思います。
|
|
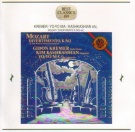
|
モーツァルト:ディヴェルティメント
K.563
演奏:クレーメル(ヴァイオリン)、カシュカシアン(ヴィオラ)、マ(チェロ)(SONY SRCR-2673 \1,800)
弦楽三重奏のためのディヴェルティメントは透き通るような美しさにあふれたモーツァルト晩年の傑作です。ギドン・クレーメル、キム・カシュカシアン、ヨーヨー・マ、3人の名手は、親しい友人どうしの語らいのような自然体のアンサンブルを聴かせてくれます。
|
|
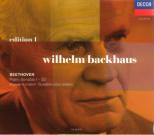
|
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第1番〜第32番(全集)
演奏:バックハウス(ピアノ)(ロンドン POCL-9911〜9919 分売・各
\952、LONDON 433-882-2 ♪♪
9CD)
バッハの「平均率クラヴィーア曲集」が“ピアノの旧約聖書”にたとえられるのに対して、ベートーヴェンの32曲のピアノ・ソナタは“ピアノの新約聖書”とされています。タイトル付きの有名曲から聴きはじめるのなら、第14番《月光》、第8番《悲愴》、第23番《熱情》の入ったCD(POCL-9911)から入って、次に第21番《ワルトシュタイン》、第17番《テンペスト》、第26番《告別》(POCL-9912)に進むのがオーソドックスでしょう。その後は、お好きな順番でどうぞ。
タイトル付きの曲が好きなのは日本人の特徴のようですが、もちろんタイトルの無い曲も魅力いっぱいです。私が好きなのは、第7番、第27番と第30番〜第32番です。
なお、ここではバックハウスを推薦しましたが、グルダ(amadeo 415 193-2 ♪
9CD)、ギレリス(第9、10、22、24、32番を除く27曲と2曲の「選帝侯ソナタ」を収録。Grammophon
453 221-2 9CD♪)の演奏も、定評のある名盤です。
|
|
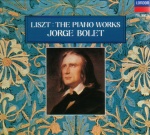
|
リスト:ピアノ作品集
超絶技巧練習曲集、巡礼の年第1年《スイス》、巡礼の年第2年《イタリア》、ピアノ・ソナタ、3つの夜想曲(愛の夢)、コンソレーション、メフィスト・ワルツ第1番 等
演奏:ボレット(ピアノ)(ロンドン
POCL-9092〜9099 \15,534
8CD、467-801-2♪♪
9CD)
リストのピアノ作品に対しては「やたらと超絶技巧を要求する装飾過剰な音楽」という先入観があるかもしれません。たしかにそのような側面もありますが、例えば、3組の《巡礼の年》や、10曲からなる《詩的で宗教的な調べ》など、一定レベル以上の技巧を要求しながらも 流れ出る音楽は信じられないほど詩情豊かという作品も数多くあります。
巡礼の年第2年《イタリア》の中の《ペトラルカのソネット》にはピアノ譜に歌詞(この曲の元となった歌曲の)が書かれているのですが、ボレットのこの曲の演奏は、バリトン歌手が歌っているかのように思えるほど歌心に満ちています。
《愛の夢》や《コンソレーション》のような珠玉の佳品も同様なので、このボレット盤でリストの意外な横顔を味わってみてはいかがでしょうか?
|
|
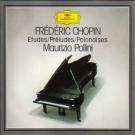
|
ショパン:24の前奏曲、12の練習曲作品10/12の練習曲作品25、ポロネーズ第1番〜第7番
演奏:ポリーニ(ピアノ)(Grammophon 431-221-2 ♪♪ 3CD)
ショパンの代表作のうち、《雨だれ》を含む24の前奏曲、《革命》《別れの曲》を含む練習曲集、《軍隊ポロネーズ》《英雄ポロネーズ》を含むポロネーズ7曲をまとめて聴くことができるセットです。ポリーニは切れ味鋭いテクニックを存分に用いて、ショパンの詩情豊かなメロディを表現しています。
穏やかな音色が好きな方には、アシュケナージの演奏をおすすめします(24の前奏曲:ロンドン POCL-5064
\1,942、練習曲:ロンドン
POCL-5046 \1,942、ポロネーズ集:ロンドン POCL-5116 \1,942)。
|
|
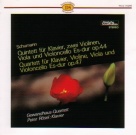
|
シューマン:ピアノ四重奏曲
演奏:レーゼル(ピアノ)、ゲヴァントハウス弦楽四重奏団(ドイツシャルプラッテンン TKCC-70268 \971
限定盤)
シューマンの室内楽曲ではピアノ五重奏曲が有名ですが、同時期に作曲されたピアノ四重奏曲も屈指の名曲です。特に第3楽章の冒頭でチェロが歌う、どことなく翳りを帯びたメロディは、シューマンならではの叙情を漂わせています。
|
|
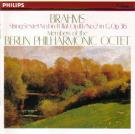
|
ブラームス:弦楽六重奏曲第1番
演奏:ベルリン・フィルハーモニー八重奏団員(PHILIPS 420-259-2 ♪♪♪)
ブラームスらしい美しいメロディがいっぱいの曲。個人的には特に、「幸せに満ち足りた」という感じの第1楽章が大好きです。また、「恋人たち」というフランス映画のなかで使われた、憂いに満ちた主題が次々に変容していく変奏曲形式の第2楽章も魅力的です。
|
|
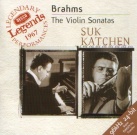
|
ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第1番
演奏:スーク(ヴァイオリン)、カッチェン(ピアノ)(Decca 466393-2 ♪♪)
ブラームス自身の作による歌曲「雨の歌」にインスピレーションを受けて作曲されたのがヴァイオリン・ソナタ第1番で、ブラームス独特の
どこか陰のある叙情が魅力の曲です。
スーク/カッチェン盤は一聴すると無駄のない、すっきりとした演奏スタイルに思えますが、聴き込むうちに旨みがにじみ出てくる。そんな味わい深い演奏です。
|
|
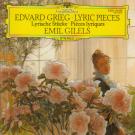
|
グリーグ:抒情小品集(抜粋)
グリーグ:抒情小品集第1集〜第8集より
アリエッタ、子守歌、、蝶々、メロディ、夜想曲、小川、ゆりかごの歌、余韻
ほか
演奏:ギレリス(ピアノ)(グラモフォン
POCG-3626 \1,942)
《ペール・ギュント》やピアノ協奏曲でよく知られているグリーグが、長年にわたって作り続けたピアノのための小品集。《ペール・ギュント》のような大作で聴かれるグリーグ独特の響きの余韻が、あちこちに感じられます。ギレリスのCDでは全66曲のうち20曲を聴くことができます。「鋼鉄のタッチをもつピアニスト」などといわれたギレリスの、心優しい一面が示された演奏です。
ギレリスのCDに収録されていない曲にも《春に寄す》《トロルドハルゲンの婚礼の日》など魅力的な曲があります。全66曲を聴きたい方は、ノックレベルグのCD(NAXOS 8.553394〜8.553396 ♪
3CD分売)でどうぞ。ノックレベルグはグリーグのピアノ・ソロ作品をほぼ全曲録音していて、日本語解説付きのボックス・セット(NAXOS 8.514001J \11,650 14CD)として発売されています。
|
|

|
フォーレ:ピアノ作品集
フォーレ:即興曲第2・3番、夜想曲第1〜5番、無言歌、舟歌第1・2・4番、ヴァルス・カプリス第1番
演奏:ロジェ(ピアノ)(ロンドン
POCL-1009 \2,913)
フォーレのピアノ曲を耳にする機会は少ないと思いますが、彼は、夜想曲(13曲)、前奏曲(9曲)、舟歌(13曲)、即興曲(5曲)など多くのピアノ曲を遺しています。
ロジェ盤は、叙情的な香りに満ちた初期の作品を集めたCDで、フォーレ入門にぴったり。隅々まで神経が行き届いたロジェの演奏は、刺繍糸で縫い上げたような優美で繊細なフォーレのピアノ曲から、洗練の極みともいえる響きを引き出していると思います。
もっとフォーレのピアノ曲を聴いてみたいという方は、コラールによる全集(EMI 769149-2 2CD,762687-2
2CD)をどうぞ。
|
|
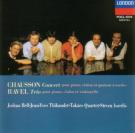
|
ショーソン:ピアノ・ヴァイオリンと弦楽四重奏のための協奏曲
演奏:ティボーテ(ピアノ)、ベル(ヴァイオリン)、タカーチ弦楽四重奏団(ロンドン POCL-1034 \2,913)
ある日ぼんやりとNHK−FMを聴いていたら、この曲が流れてきました。あまりの美しさに衝撃を受けたのを思い出します。
全曲を通してショーソンが紡ぎ出す繊細な響きを楽しむことができますが、特に、第2楽章の悲しくも美しいメロディを一度聴いてみてください!
|
|
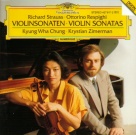
|
R.シュトラウス:ヴァイオリン・ソナタ
演奏:チョン・キョン・ファ(ヴァイオリン)、ツィマーマン(ピアノ)(Deutsche Grammophon 427 617-2♪♪♪)
オペラや交響詩などの大規模な管弦楽曲の大家として知られるR.シュトラウスがのこした室内楽の佳品。
チョン・キョンファの情熱的なヴァイオリンと、ツィマーマンの理知的なピアノ伴奏がほどよく調和した名演でお楽しみください。
|
|
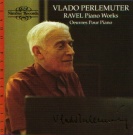
|
ラヴェル:ピアノ作品集
鏡、水の戯れ、亡き王女のためのパヴァーヌ、夜のガスパール、ソナチネ、優雅で感傷的なワルツ、クープランの墓、前奏曲、ボロディン風に、シャブリエ風に、古風な舞曲、ハイドンの名によるメヌエット
演奏:ペルルミュテル(ピアノ)(Nimbus
NI7713〜7714♪♪)
ペルルミュテルは、晩年を迎えたラヴェルから直接、演奏技術と演奏法の指導を2年間(1925〜27年)にわたり受けたそうです。ラヴェル直伝の「楽譜には記し得ない微妙な表現」や「オーケストラ的な色彩感」が具現化されたペルルミュテルのラヴェル演奏は、「今後も数多くのラヴェルのピアノ曲の演奏が出るだろうが、これからは常にこのペルルミュテルの演奏と比較して判断されるべきだ、といっても言い過ぎではない」と評される(イギリス『グラモフォン』誌)など、ラヴェル解釈のスタンダードとなっています。
|
|
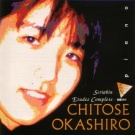
|
スクリャービン:練習曲全集
3つの小品作品2〜第1曲《練習曲》、12の練習曲作品8、8つの練習曲作品42、3つの小品作品49〜第1曲《練習曲》、、4つの小品作品56〜第4曲《練習曲》、3つの練習曲作品65
演奏:岡城千歳(ピアノ)(Pro Piano
PPR224510 ♪♪♪)
スクリャービンが作曲した「練習曲」と名の付く曲(全26曲)をすべて録音したCD。
スクリャービンの練習曲は、まるでショパンのようなロマン味あふれるメロディと、斬新な和声のブレンドが何ともいえない味わいなのですが、岡城さんの演奏は、超速のパッセージを難なく弾きこなしつつ、その中に潜む叙情的な「歌」も見逃さず心をこめて歌い上げています。
|