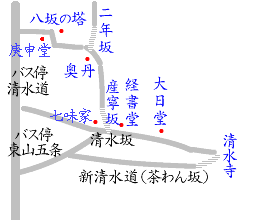/// 八坂の塔から清水寺へ /// (00/02/25)
清水寺へは東山五条のバス停から五条坂を、清水道のバス停から清水坂を 登って行くのが普通ですが、清水道のバス停から北へ直ぐの八坂通を登る コースを紹介しましょう。ここは庚申信仰を基にするお寺ですが、庚申信仰は一般には庚申待ちとも 云われ、江戸中期には、本州各地に普及していたそうです。 干支で60日ごとに回ってくる庚申(かのえ さる)の日に、庚申講という 集まりを当番の家で行い、そこで「庚申さん」と呼ばれる掛軸を掲げて 唱えごとをして、食事、長話などで夜が明けるのを待つと云うものです。 そうすることで、災いから逃れられると云う民間信仰です。 その庚申ですが、「申」はサルとも読めることから、猿が災い除けの対象に なったのかなと思います。