/// 京都の台所、錦小路 /// (99/11/20)
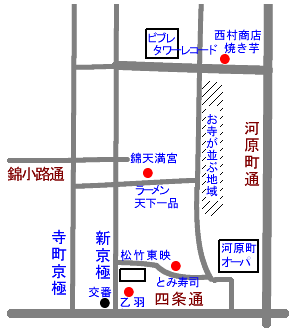 |
京都の台所と云われる錦小路を 歩いてみます。 錦小路は東は新京極から西へ 壬生川通まで約2kmの通りです。 そして東端の寺町京極から高倉通 までが錦市場で、道幅2mそこ そこの通り400mに約150軒 もの店が並び、京都の台所と形容 されます。 平安京の当時は道幅も10mを越 える大路だったようです。 武具甲冑の職人が住む地域だった ので当初は「具足(ぐそく)小路」 と呼ばれていたようです。 |
それがいつしか訛って「糞小路」と呼ばれるようになり、この話を聞いた 天皇が余りにも品がないと云うことで、綾小路(あやこうじ)にならい 錦小路とせよとの直言で、今に伝わる錦小路となったと云います。 京都の台所と云われるだけあって、その商う品は多種多様です。 日用品などの店もありますが、食材の店が多いです、その表情は 朝と昼過ぎとでは異なります。 特に鮮魚店などでは品揃えががらりと変わります。 朝方は旅館や料理屋の主人や仕入れ担当者が多いので、魚なども丸ごと 売り、野菜なども箱ごと売りだったりしますが、午後になり、庶民の 時間帯となると刺身だったり、焼き魚だったり、京野菜も綺麗に飾り 細工されたものだったりと手を入れたもの、加工されたものが多く なります。 京都は盆地であるにも関わらず、魚は昔から新鮮なもの、活きのいい 魚が入ってきます。その昔、鯖を京都へ運ぶ道だった鯖街道に その名残を留めるように日本海方面との交通は盛んでした。 このような背景もあって、京都では魚料理もよく食べます。睨みタイに はじまり、琵琶湖のアユ、若狭カレイ、夏のハモ料理、これからの 季節ならグジの荒煮などが美味しいです。昔から鮮魚店が多かった こともあり、この錦市場一帯の正式な町名は東魚屋町、中魚屋町と なっています。 錦市場では特定の品に特化した店が多いです。メリケン粉、カタクリ 粉など粉ものだけを商う店、各地のチリメンジャコだけを商う店、 鰹節だけを商う店と云うように、幅は狭いが奥は深い店です。 まるで京都の町屋のようです。 京野菜、京漬け物なども売っていますので、パック詰めのお土産用 漬け物を買うのも良いですが、店ごとに味も異なる庶民の漬け物も 賞味して下さい。


