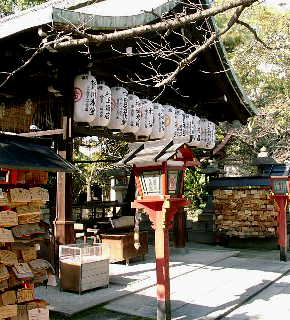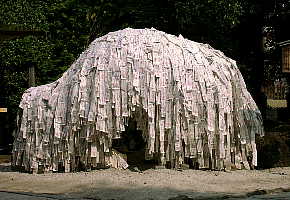|
その後、後白河天皇の詔によって光明院
観勝寺と改められますが、応仁の乱によって
荒廃してしまいます。江戸の世となり
元禄8年に太秦安井と云うから、現在の
右京区にあった蓮華光院が移建された時に、
その鎮守として崇徳天皇に加えて、讃岐の
金刀比羅宮より勧請した大物主神と、
源頼政を祀ったことから安井の金比羅さん
として知られるようになります。
明治維新の後、廃仏毀釈によって寺は大覚寺に
没収されて安井神社と改称、そして戦後、
安井金比羅宮の名を受け現在に至っています。
ここ安井金比羅宮は京都では縁切り・物断
(ものたち)と縁結びの御利益の神社として
知られています。
これには祭神である崇徳天皇に大きな
関わりがあります。
|
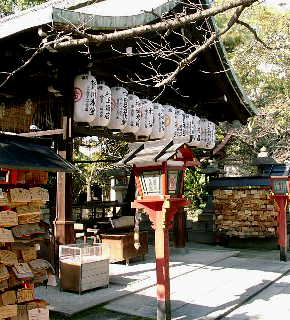 |
早良親王が怨霊となって都を騒がせたのと
同じく、崇徳上皇も保元の乱で敗れ、讃岐へと
流されますが、その地で全ての物を断った
崇徳上皇は五部大乗経を血書すると共に
「われ日本国の大魔王となり、皇を取って
民となし、民を皇となさん」としたため、
恨みを残し没します。
この後、天変地異に見舞われた都では
崇徳上皇の祟りと恐れ、上皇に崇徳天皇の
追号をなし、祟りを鎮めようとします。
この当たりも早良親王の話と類似する
ところですね。
この崇徳天皇の物断に由来して、安井金比羅宮は
縁切り・物断の御利益神社として知られます。
|
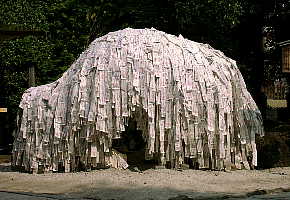 |
本殿脇に縁切り縁結び碑(いし)、高さ1.5m、
幅3mの巨石があり、中央の亀裂を通じて
神の力が下の円形の穴に注がれているとか。
まず、身代わりとなる形代(かたしろ)に願い
事を書いて、碑の表から裏へ穴を通って悪縁を
切り、裏から表へ通って良縁を結びます。
そして最後に形代を碑に貼って祈願します。
今では数多くの形代が貼られており、縁結び碑
自体も見えなくなるほどです。
|