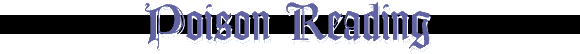| 1999/11/29 |
| 冬の保安官 |
大沢在昌 |
晶文社 |
1999年11月25日発行 |
毒毒度:2
|
“「私には何もない」
「いいえ、あなたは気づいていないだけよ。自分の凍てついた上辺の内側にあるものを」
「私は…」
ローズはうつろな声でいった。
「自分の中に死しか持っていない男だ」
「それはちがう。やがてあなたも気づくときが来るわ」
「それまでに私の命が尽きなければ」”
ブラッドベリの未来版を読む予定だったのだが、泊まり仕事となったため、急遽昼休みに書店で見つくろった。私にとっては初めての作者。短編集のタイトルの響きにつられて購入。温泉町でも、冬の別荘地でも、ハードボイルドはできるという証明となっている。ハードボイルドは会話、所作の描写に神経の細やかさがないと成り立たない。その点で合格。引用は、任務中にアケロ-ンローズという植物の花粉を浴びたため「ローズショット」という麻薬を摂取せざるをえない元シークレットサービスを主人公とした連作。摂取間隔が徐々に短くなる、つまり徐々に死に近づいているかれは現在歓楽の惑星「カナン」最大のホテルの探偵。そこで起きる事件を鮮やかに解決していく…。さて、新宿鮫シリーズの外伝ともいうべき書き下ろし「再会の街角」を読んでしまったからには本伝も読まなくてはならないか。 |
| 1999/11/24 |
ブラッドベリがやってくる
--小説の愉快-- |
レイ・ブラッドベリ、小川高義訳 |
晶文社 |
1996年6月10日発行 |
毒毒度:-5
|
“書いていて何がわかるのか。まず第一に、われわれは生きているということがわかる。そして、生きているのは特別にあたえられた状態なのであって、もとからの権利なのではないともわかる。ひとたび生命なるものを授与されたなら、今度は生命を保つべく働かなければならない。生きて動けるようにしてもらえた者は、生命から見返りを要求される”
“第二に、書くことはサバイバルである。いかなる芸術も、良質の芸術であるならば、すべてそうである。かなりの人間にとって、書かないということは死につながる”
二冊同時に刊行され話題になった、ブラッドベリの過去と未来にかかわるエッセイの「過去版」。もう3年たつわけだ、購入してから。単行本なので待機が長かった、すみません。でもこれを上回る「薔薇の名前」(約10年)もあることだし。何で日の目をみたかというと、読書に勢いづいた結果です。で、読んでみたら何と素晴しい! 一冊まるごと暗記しよう。何で今まで放っておいたのか後悔しきり。でも今からでも遅くはない。毎日欠かさず詩を読む。好きなものを追いかける。何にせよ、猛烈にうれしくてたまらない精神状態で、ものを書く。ああ、早く「未来版」が読みたい。
|
| 1999/11/24 |
| テキーラの朝やけ |
オキ・シロー |
幻冬舎文庫 |
1998年2月25日初版発行 |
毒毒度:2
|
| “残酷なほどに美しいギブソンの出来上がりだ。透明な酒の中で、パール・オニオンが白く、冷たく輝いている。その串刺しにされた二粒のオニオンを見る度に、大介はきれいだなあと思い、そして決まって男と女の「道行き」という古風な言葉を思い出すのだった。”
無国籍風だった「ギムレットの海」に比べ、この「テキーラの朝やけ」は渋谷は道玄坂のバー・ボロンゴを舞台にした連作集。マスター大介、バーテンダー二郎、見習いバーテンダー敏也がレギュラーである。登場人物に名前があるし、犯罪の匂いどころか血も流れるので、今までよりも少々生々しい。前作とまったく同じ題名の違う話あり。 |
| 1999/11/23 |
| ギムレットの海 |
オキ・シロー |
幻冬舎文庫 |
1998年2月25日初版発行 |
毒毒度:2
|
| “すっきりと脚の長いカクテルドレス。その透明な酒の中に、オリーブの若緑が淡くにじんで見える。遠目にもよく冷えた、いかにもうまそうなドライ・マティーニだった。わたしもマティーニにすればよかった。女は、自分のシェリーを持ちながら、見知らぬ男の前に置かれたマティーニの端正な姿に、思わず見とれた。”
17篇すべてバーのカウンター、あるいはテーブルでのお話。ほとんどの登場人物が男と女、バーテンダーだけというシンプルにしてハードボイルド、口あたりのよいカクテルに潜む火の酒か。いや、武骨な男たちがストレートで飲む酒も、組み合わせ次第で上品にまろやかになることも証明されている。「雪の日のホワイト・レディ」にホラーのフレーバーを感じるのは私だけ?
私が以前から好きだったカクテル、フローズン・ダイキリ。単にヘミングウェイの酒というただそれだけの理由で。この本を読んで、飲みたくなったカクテル、ジャマイカ・マティーニ。ジンとベルモットのかわりに、ラムとシェリー。もう大人なんだから、いきつけのバーが存在してしかるべきと思うが、ちゃんとしたバーのカウンターにて自分の意志でカクテル飲むのは年に一回ぐらいとは、冴えない人生。 |
| 1999/11/22 |
グイン・サーガ第68巻
豹頭将軍の帰還 |
栗本薫 |
ハヤカワ文庫JA |
1999年11月15日発行 |
毒毒度:2
|
“真実はいつかあらわれる。--ならば、本当は真実は最初から、隠したりしないほうがいい”
“……そして話している間に俺は気がついたのだが、俺は何よりも--この世の何よりも真実が大切だと信じている。俺がシルヴィア姫をいとしいと思っているのはおそらく、彼女が誰よりも真実だからだろう--誰にでもなんらかいつわりはあるものだ。そしてそれによって自分を救っている。だがあの少女にはそれがない。あのかよわさ、あの無力、あのよるべなさで、あの少女は何ひとつ嘘などなくおのれ自身をまわりじゅうにまきちらしている。--それが俺にはたまらないのだ。”
本の中では2年振り、現実だと実に5年振りに、グインがケイロニアの首都サイロンへ帰還する。「マルーク、グイン」の歓声とともに。アキレウス皇帝は約束通りグインにシルヴィアを娶らせ、ケイロニア王の称号を与えようとするがはたしてグインはうけるのか…。
キタイでシルヴィアとともに救出された吟遊詩人マリウス、そしてトーラスから共に旅したマリウスの妻子オクタヴィアとマリニア。オクタヴィアはいよいよ、シルヴィアとは腹違いの姫としてケイロニア国民に公表されることになっている。しかも実はマリウスはパロの第三王位継承者アル・ディーン、皇室ギライで出奔したのにはたしてサイロンでの皇室生活がつとまるのか? 一方トーラスでは、強引にゴーラ王となったイシュトヴァーンの過去の所業が明るみに出ようとしていて! 片脚切断以後、悪魔ぶりをあんまり発揮しなくなったアルド・ナリスにかわり、イシュトの悪魔度急上昇。カメロンもたじたじ。 |
| 1999/11/21 |
| 詩的私的ジャック |
森博嗣 |
講談社文庫 |
1999年11月15日第1刷発行 |
毒毒度:-1
|
“研究ってね。何かに興味があるからできるというものじゃないんだよ。研究そのものが面白いんだ。目的を見失うことが研究の心髄なんだ。君が、今、殺人事件に夢中なのと同じ。君だって、殺人が好きなわけじゃないだろう?”
“花が枯れても人は泣かない。花はまた咲くからか。いや、人間だってまた、生まれる。失われるのは、躰ではない。死んだ者の記憶だ。だが、記憶でさえ電子的に保存することができる。再生できないのは、人間の思考だ。”
時代小説から一転、森博嗣の文庫版新刊。相変わらず、殺人事件に関心がないにもかかわらずどんどん関わらざるをえない、推理さざるをえない犀川。おっと私の好きなハンドラーの名前が見えますね。ハンドラーの主人公ホーギーは、彼のいくところで殺人が起きて巻き込まれて…というパターンだが、似ているといえば似ている。そこらへんはインスパイアされた本100冊として森博嗣自身がハンドラーを3冊も挙げている「ミステリィ工作室」を読まなくてはいけない。今まで気がつかなかったが、殺人事件の話をしながらご飯食べる人たちといえば、スケルトン探偵シリーズ。事件発生が研究者や学者の世界という点でも類似性があるのでは。
データは上書きできる。FDは初期化が可能だ。ウィルスにやられたハードディスクだって物理フォーマットすれば再生する。でもね、人間にはそうじゃないだろう? 関係者がロックスターという設定自体はなかなか魅力的だが、もう少し書き込んでほしかった。ちなみに、ロックスターがどんなに暑くても人前ではしない格好というのが、私には謎解きの鍵となった。理系の人たちがMacintoshを使っていることにはいつもながら納得いかない。理系ではない私は確かに使っているけれど、なんであんなに機械とはほど遠いものなのに。序盤、そして終盤怒涛の「綺麗」攻撃には屈せずに読み切りましたよ。ちなみに全部で27回、見開きに最高3回。やっぱり多すぎやしませんか? |
| 1999/11/20 |
木枯し紋次郎(13)
人斬りに紋日は暮れた |
笹沢左保 |
光文社時代小説文庫 |
1998年1月20日初版1刷発行 |
毒毒度:3
|
| “「あっしには、言い訳なんぞござんせんよ」そう言って紋次郎は、楊枝を口の中心に寄せた。その一点から息を吐き出すと、木枯しに似た音とともに楊枝が吹き矢のように飛んだ。”
「あっしにはかかわりのねえことで」に続き、新しく紋次郎のキメ科白ができたようである。収録の4作品のうち3作にヤナ女が登場する点で、毒読度はいつもより高め。解説は笹沢左保本人。女性には苦労しているようで。え、言い訳はござんせん? はいはい。 |
| 1999/11/19 |
木枯し紋次郎(11)
お百度に心で詫びた紋次郎 |
笹沢左保 |
光文社時代小説文庫 |
1997年11月20日初版1刷発行 |
毒毒度:2
|
| “雪が降る。白い闇だった。間もなく、日が暮れる。街道を、人影が突っ切る。路上に、足跡が残る。その足跡をすぐまた、降りしきる雪が消してしまう。人声がする。呼び合っている男たちの声である。雪が舞う。美しさも、風流もなかった。”
雪中の殺し合いから、ことづてを頼まれて房州は那古へ。目的を持った紋次郎の足どりは軽い。行徳、舟橋、検見川、寒川、浜野、五井、姉崎、木更津…千葉県内の地名は馴染みがあって嬉しい。そして迎えてくれた家は暖かかった。元渡世人であるあるじは、この土地に落ち着いてはとすすめてくれる。あるじの孫娘もなついて、紋次郎がその気になった矢先、事件が起こる。いつも新鮮なミステリ仕立て、読みとばしてはならない。文章に無駄というものは一切存在しないのだから。
|
| 1999/11/18 |
木枯し紋次郎(10)
虎空に賭けた賽二つ |
笹沢左保 |
光文社時代小説文庫 |
1997年10月20日初版1刷発行 |
毒毒度:2
|
| “闇である。目で見ての、闇だけではない。心の中にも、何かがないのである。あらゆるものから、刺激も影響も作用も受けずにいる。考えることも、思い浮かべることも、感じ取ることもない。自分の存在すら、確かめられないのであった。心境としては、『無』である。だが、達観したり、悟りを開いたりした上での『無』ではない。何もないことを、押しつけられての『無』であった。”
素晴しい、この出だしが。この状況こそ紋次郎の生そのものである。話の締めに当時の公式記録を配する趣向。“『21人の遠来の巨魁、花咲屋において3日間にわたり豪遊す』と、天保11年3月の境町問屋場の日誌に記されている。”という結びの収録作品「桜が隠す嘘二つ」では、大前田英五郎、安東文吉、国定忠治、笹川の繁蔵、飯岡の助五郎らそうそうたる親分衆の眼前で、紋次郎が自らの濡れ衣を晴らして、一堂を感嘆せしめる。さらには「二度と拝めぬ三日月」ではあの国定忠治を泣かせたり…。解説はTVで紋次郎を演じた中村敦夫氏、ファンには堪りません。 |
| 1999/11/17 |
| 俺、南進して。 |
荒木経惟・町田康 |
新潮社 |
1999年9月30日第1刷発行 |
毒毒度:5
|
| “ツーツーいう電話を架台に戻して俺、快適なベッドに転がり、ようよう手を伸ばしてグラスに残っていた酒を飲んだ。腕と胸、ひときわ痛く、途轍もない陰(いん)、心でひときわ激しく暴れ回って。”
JAL最終便で生まれて初めて空から大阪を見たときは結構綺麗じゃんと思った。ネオンが一斉においでおいでをしていた。しかしそうはいっても、大阪は苦手なまちだ。電車に乗ってあたりの会話が耳に入ってくるだけで疲れてしまう。たぶん波長が合わないのだろう。帰ってくるとまるで日付変更線が存在したかのように、ぐったりする。大阪以西、たとえば広島に日帰りしてもこれほど疲れないのに。
大阪を舞台にした話題のコラボレーション。荒木経惟の写真、町田康の小説という、アナーキーな二人による刺激的な一冊。ここしばらく写真集、写文集にこだわっているのでなかなかの選択。いきがかり上朝の通勤電車で読みはじめたが、ちょっと写真のページは開くのがはばかれるものも当然あるわけで…。元パンクロッカー町田康の文章はananの読書日記でしか読んだことがない、新鮮。私小説か、否か。書評によると町田康夫人も出演しているらしいのだが、はてどの女性? ノンブルがないのが変わっている。 |
| 1999/11/16 |
| 肉体泥棒の罠(下) |
アン・ライス、柿沼瑛子訳 |
扶桑社ミステリー文庫 |
1996年9月30日第1刷 |
毒毒度:4
|
“救われる。なんと素敵で、途方もなく、不可能な考えだろう……よりにもよってこんなことを真剣に考えてくれる、一人の人間の女性を見いだすというのはなんと素敵なことだろう。
そしてクローディアはもはや笑っていなかった。なぜならクローディアは死んでいるのだから。”
読みやすいというのが第一印象。シリーズ前作ではヴァンパイアオールスターズが登場し、舞台も古代エジプトから現代までめくるめく大絵巻だったため、はかどらなかったが、今回は登場人物が少ない上ほとんどが二人しか同時に登場しないので会話もわかりやすい。誰が誰の肉体にいるのかを除けば…。ネタばらしはしません。ただ、ディヴィッドの今後が気になる気になる…。 |
| 1999/11/15 |
| 肉体泥棒の罠(上) |
アン・ライス、柿沼瑛子訳 |
扶桑社ミステリー文庫 |
1996年9月30日第1刷 |
毒毒度:4
|
| “わたしたちは答えを知る運命にはないのです。魂が輪廻を通してひとつの肉体から別の肉体へ移動するかどうか知る定めにはないのです。はたして神が本当に世界を作ったのかどうか知る運命にはないのです。アラーだろうとヤハヴェだろうと、シバだろうとキリストだろうと知る定めにはないのです。神は啓示を植えつけると共に疑いも植えていった。わたしたちは皆、神に踊らされている愚か者なのです”
これがアン・ライスの宗教観か。神は存在する、しかし神は忙しいので私たち全員の面倒は見られないと言ったのは誰だったか。私にとっても神は存在する。しかし、人間はなまけものなので神に頼って手を患わせてはいけない運命にある。それにしても、極悪人と肉体を交換するとはなんという愚かものレスタトよ。 |
| 1999/11/11 |
ドラキュラ・ドラキュラ
〜吸血鬼小説集〜 |
種村季弘編 |
河出書房新社 |
1986年1月10日初版発行 |
再 毒毒度:2
|
| HP開設に伴い、昔読んだものを再読している。当時、ジュール・ヴェルヌの「カルパチアの城」に何かを感じたのか。HPの吸血鬼部屋は「カルパチアの城」という題名がついているが、でも偶然です。編者は日本での吸血鬼研究者の草分け。 |
| 1999/11/10 |
江戸の人生論
〜木枯し紋次郎のことわざ散歩 |
笹沢左保 |
光文社文庫 |
1999年10月20日初版1刷発行 |
毒毒度:1
|
| “初めから適当に急いでいれば、日暮れが近づいても悠然と構えていられる。ところが人間というものは、まだまだ大丈夫だと初めのうちのんびりしている。そのくせ残り時間が少ないと気づくと、にわかにあわてふためいて青くなる。”
「日暮れて道を急ぐ」の説明は、しょっぱなから耳が痛い。意外な出所もあり、なじみのことわざの意味が再確認できる。面白いのは逆の意味のことわざの存在だ。たとえば、「夫婦は一心同体」と「夫婦は他人の集まり」、「芸は身を助く」と「芸は身の仇」などなど。 |
| 1999/11/09 |
iichiko design
「いいちこ」のポスターとデザインワークの世界 |
三和酒類編 |
ビジネス社 |
1996年7月15日1刷発行 |
毒毒度:-3
|
| “無伴奏でうたう。”
1984年4月、小さなテーブルの上にいいちこのボトルとお洒落な小物たちが載った光景を世に送りだしてから12年間の、『いいちこ』のボトルが続けた旅の数々。私の好きな広告のシリーズに『キューピーマヨネーズ』とこの『いいちこ』がある。『いいちこ』のシリーズは、河北秀也のディレクション、浅井愼平の風景写真と野口武のコピーワークが中心となり、つねに心地よい雰囲気を創り出している。基本的に、『いいちこ』のボトルは風景の中に実際に置かれている。引用のコピーは1991年9月のポスター。アンドリュー・ワイエス風の草原に石がひとつ、その上にいいちこのボトル。
どんなにデジタルが流行ろうとも、『いいちこ』はアナログの酒であり、見ようとする人には風の色が見え、聴こうとする人には音が聞こえ、冷えていたりあたたかかったりするその触覚も味わいたいと思う人にはいつでも味わうことができるのだ。
|
| 1999/11/09 |
| 本屋でぼくの本を見た |
渡辺淳一ほか |
角川文庫 |
1999年10月25日初版発行 |
毒毒度:-5
|
“編集者の情熱というものは一体どこから来るのだろう。他の社会には存在しない、何か特別なものに動かされている人達だ。それに触れたとき、心が騒ぎ立ち、やみくもに走ってみたくなる。”(高樹のぶ子)
“誰もはっきりとは言わないが、新人が世に出るとき、有能な編集者に当たるか否かは作家としての生命予後を左右する大問題なのである。”(南木佳士)
61名の人気作家のデビュー作にまつわるエッセイ・アンソロジー。赤江瀑と尾辻克彦(赤瀬川原平)が載っていたので迷わず買い。小説を書くきっかけはさまざま。賞金が欲しくて、というのも結構あるのがおもしろい。作家が成り立つには優秀な編集者の力に負うところが多い、これは事実だ。 |
| 1999/11/08 |
| レキシントンの幽霊 |
村上春樹 |
文春文庫 |
1999年10月10日第1刷発行 |
毒毒度:1
|
“ケイシーはそれからしばらく、黙って何かを考えていた。季節は秋の終わりで、椎の実がアスファルトの路面を打つコーンという乾いた音が時折耳に届いた。”
“僕が今ここで死んでも、世界中の誰も、僕のためにそんなに深く眠ってはくれない”
1990、1991年と、間に長編をはさんで1995、1996年に発表された作品。奇妙で、哀しくて、怖い、7つの短編集。最近さがしものの途中で見つけたSports Graphic Number 第12号、村上春樹のコラムOnly Yesterday(記憶の中の瞬間)に涙した。『息子と紙袋を抱えて、サインに応じたヒルトンの優しい目』というタイトルからしてリリカルな一文である(最も、重大な勘違いが隠れているのだがそれについてはまたいつか)。こうして見ると、淡々と描写しているようで人を突然叙情の波にさらってしまう文体、欧米的なセンスを持ったお洒落な大人のイメージがなんだか山際淳司とダブってきた。たしか、かれらはおない年くらいだったと記憶している。 |
| 1999/11/06 |
| 28年目のハーフタイム |
金子達仁 |
文春文庫 |
1999年10月10日第1刷発行 |
毒毒度:1
|
“日本がブラジルに勝った--。間違いなく、日本サッカー史上空前の快挙だった。気の早いマスコミのなかには、決勝トーナメント進出はおろか、はやメダルが見えたとブチあげるところもあった。”
“だが、歴史的偉業の陰には、もう一つの真実が隠されていた。この日は、日本オリンピック代表がチームとして機能した最後の日でもあったのである”
馳星州をして「稀代のインタビュアー」といわしめる金子達仁の出世作。金子にインタビューを受けるということは、かれと闘うことだという。実は私にもインタビュアーとしての経験はあるが、無難な線でしかこなしていない。相手の仮面をはがせない、つまりは自分の本心を出していないということ、これはものすごく失礼ではなかったかと、今にして思う。
メキシコ・オリンピックでの銅メダルのときの映像は脳裏にはない。新聞記事に添えられた写真の記憶があるだけである。TVで見る日本リーグは私にとってはなかなかにして面白く、釜本、杉山はもちろん、ネルソン吉村、カルロスといった選手の活躍は記憶している。その後、アトランタまで一度もオリンピック出場がなく、ワールドカップ出場も果たせないほど、なぜ日本のサッカーは強くなれなかったのか。ヨーロッパとは何が違ったのか。経験から来るイマジネーションの重要性には、大きくうなずいてしまった。
「健全な肉体に美しい精神が宿る」ということはない。「健全な肉体にそれに見合う健全な精神が宿るといいのだが」くらいのニュアンス、つまり「あらまほし」の世界。「宿るといいなあ、でも残念ながら宿らないことが多いんだよね」
そして今日、シドニー行きが、決まった。 |
| 1999/11/05 |
| 写真集をよむ ベスト338完全ガイド |
リテレール編集部 |
メタローグ |
1997年12月25日発行 |
毒毒度:3
|
とりあげた写真集を並べた表紙カバーを除くと全部モノクロ。念のため数えたら確かに338冊の表紙が並んでいた。
買ってみたい写真集ベスト10
Witkin, Joel-Peter: Witkin/Scalo/1995
動物の死体、新聞で募ったフリークス、切断された身体の一部などを材料に、
ベラスケス、レンブラント、ゴヤなどの名画の構図を引用しながら
イメージを作り上げるジョエル・ピーター=ウィトキン。
1970年代初期から1990年代の作品100点収録。
ベラスケスの光と影が写真でどう表現されているのだろう。
Bavcar, Evgen: La voyeur absolu/Seuil/1992
ユジェン・バフチャルは盲目の写真家。一体どうやって撮影するのか。
時間に触ること、それが彼の写真行為である。
Alpern, Merry: Dirty Windows/Scalo/1995
ウォール街のとあるトイレの窓を5メートル離れた一階上のダクト越しに見た、
あらゆる意味でダーティな87枚の写真集。
Cartie-Bresson, Henri: And the Artless Art/Bulfinch/1996
写真家集団マグナムの創設者アンリ・カルティエ=ブレッソンの代表作抜粋版。
写真を見る喜びを感じたい。
Salgado, Sebasti黍: Terra/Phaidon/1997
セバスチャン・サルガドが出身地ブラジルでドキュメントした、土地を持たぬ農民の労働と闘い。
サルガドの撮る労働者の肉体・表情・皺のひとつまで堪能したい。
Leibovitz, Annie: Olympic Portraits/Bulfinch/1996
アトランタ・オリンピックを記念して企画された写真集。
ポートレイト写真家アニー・リーボヴィッツ撮影による、スポーツシーン。
アスリートたちの個々のパーソナリティが見えるという点にひかれる。
木村伊兵衛『パリ』/のら社/1974
1954、1955、1960年撮影のパリ。
細江英公『薔薇刑・新版』/集英社/1984
三島由紀夫を被写体とした写真集。粟津潔装丁・レイアウト!
森山大道『サン・ルゥへの手紙』/河出書房新社/1990
「写真は光と時間の化石」
渡辺兼人/文・金井美恵子『既視の街』/新潮社/1980
写真なるものと言葉なるものの対立。 |
 |
| 1999/11/05 |
| 超芸術トマソン |
赤瀬川原平 |
ちくま文庫 |
1987年12月1日第1刷発行 |
毒毒度:3
|
| “堂々と空振りしようとしていたトマソン選手のバットが、ちょっと間違ってボールに当たってしまった。だけど一つだけその路上に残されたという、それは何だろうか。そこのところでこの物件は超芸術に引っ掛かってはいる。空振り用のバットにボールが当ってはしまったんだけど、やはり当ったボールはファールになって、それを八重樫に捕られたと、そういう事情が含まれているのだろうか。そうだとすれば、この物件はきわどいところでトマソンなの、かもしれないのです。”
ここしばらく凝っているトマソンの原点。コメントに八重樫までも登場するところはさすが。ちなみに八重樫は当時のヤクルトスワローズのキャッチャー(現コーチ)です。四谷階段の発見からトマソン観測センター設立、路上観察学会発足にいたる充実のトマソン物件。圧巻は表紙の写真、エントツの上に立って一脚を持ち、魚眼レンズで自らをもおさめたという飯村昭彦氏の神をもおそれぬ所業。この行為に呆れて、他のトマソン本より毒毒度は高い。
ところで、今、若い女性を中心に写真ブームらしいのだが、テーマ探しは結構大事だと思う。要はどれほど愛があるかということだ。私としてはあたたかい写真が撮りたいのだが。 |
| 1999/11/04 |
| 氷の眠り |
アーロン・エルキンズ
瑳峨静江訳 |
ミステリアス・プレス文庫 |
1993年2月28日初版発行 |
毒毒度:1
|
| “それであんたの考えは、先生? 科学者たちというのは、だれがどのアイデアを先に考えたかで、ほんとうにおたがいに殺し合うんですかね?”
スケルトン探偵、ギデオン・オリヴァーもの第6作目(ただし1作目は未訳)。舞台はアラスカの氷河。
遭難救助研修に参加する妻ジュリーについてきたオリヴァーが、メンバーの配偶者として初日から退屈しはじめていた矢先、氷河から、30年前に起きた雪崩で遭難死したと思われる調査隊員の骨が発見される。ロッジに居合わせたのはこれまた偶然か、30年前の事故から奇跡の生還を遂げたトリメイン教授と著作執筆のために教授が集めた遺族や研究者のグループであった。オリヴァーの鑑定で、遭難死した隊員は実は殺されていたという事実が判明、そして30年後の現代で殺人が…。2つの殺人の関連は?不明の隊員は男2名、女1名。発見された人骨はそもそも誰の骨なのか?誰が誰を殺したのか?
はじめて訪れた町でも必ず気のおけない、くつろいだ雰囲気の店を見つける主人公たちの能力は素晴しい。ユーモラスな会話が食事つきで楽しめるというわけだ。会話の内容がたとえ、殺人と骨に関することであろうとも。
どの科学者がどのアイデアを先に考えたかという問題でダーウィンとウォレスが例にあげられている。ウォレスはダーウィンと同時に進化論を発表しながらも「ダーウィンに消された男」として知られる。ウォレスの研究は「熱帯の自然」(ちくま学芸文庫)で知ることができる。ダーウィンについては最近高価な伝記が出版された。 |
| 1999/11/02 |
| 異常快楽殺人 |
平山夢明 |
角川ホラー文庫 |
1999年8月10日初版発行 |
毒毒度:4
|
| “もしも、ごく短期間に、この物語のなかに突入し無事に帰還、現在に至るも何の変調もきたさないとするなら、あなたの精神は自覚しているいないにかかわらず、相当のものであるといえる。”
ごく最近、南米で子供ばかり数百人の大量殺人者が逮捕されたというニュースがあったばかり。
エドワード・ゲイン、アルバート・フィッシュ、ヘンリー・リー・ルーカス、アーサー・シャウクロス、アンドレイ・チチカルロ、ジョン・ウェイン・ゲーシー、ジェフリー・ダーマー…このうちほとんどは異常快楽殺人者としてかなりスタンダードな(異常に標準があるのか?)負のサンプルである。コリン・ウィルソンの一連の著作、ロバート・K・レスラーの「FBI心理分析官」シリーズ、またチチカルロについては「子供たちは森に消えた」は既読。ルーカスとシャウクロスについてのみ体系だったものを読むのが初。殺人者たちの手口がこれでもかと語られるので、おそらく人生を害する人がいるだろう。ためしに私は昼飯前にダーマーの項を読んでみたりした。昔、こそこそ買ってこそこそ読んでいた一般的には忌むべきジャンルが、こうして文庫で手軽に買えて、しかも売れる時代。あたり前だが、生身の人間が一番怖い。 |
(c) atelier millet 1999-2002
contact: millet@hi-ho.ne.jp