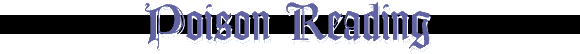 ●あと10000冊の読書(毒読日記) ※再は再読の意 毒毒度(10が最高)
画家のグリフィンに送られてきた見知らぬ恋人サビーヌの絵はがきを発端にした不思議な文通のお話。ブロック体のグリフィンと筆記体のサビーヌの手紙が、美しいけれど風変わりな絵はがきや、本物のレターセットで綴られる。想像上の恋人が訪ねてくるということに恐怖を感じたグリフィンの旅は、サビーヌから逃れるようにギリシア、エジプト、はたまた日本へ。偶然なのだが、表紙が私のこのHPのトップページと同じ青。書店で目にしたときは、ドキドキしたものだ。そんないきさつで、自分へのクリスマス本として選んだ。続・不思議な文通ということは当然正編があるのだが、残念ながら書店には続編と完結編の2册のみ。正編を読まずして続編にすすむのは私の主義には反するのだが…。それぞれテーマカラーが異なるようで、3冊揃ったときがとても楽しみではある。装丁には力がこもっている、2500円を高いとは思わない。 1990年柴田錬三郎賞受賞の作品集。私にとって『水底の祭り』(文春文庫)以来2冊目の皆川博子作品。7作品すべてタイトルからして美しい。薔薇の葩(はなびら)に埋もれての窒息死という幻想物語『薔薇忌』はほとんど劇のように進行する。苳子(とうこ)という主人公の名前はまさに、芝居をやっている女性の名前にふさわしくはないか。たぶん舞台栄えする美女であろうと思われるのだが、あえて男言葉でポンポンものをいうこのリアルさが堪らない。美しくて怖いホラ話を聞きたいのだからお願い早く騙してくれ!という気持ちになる。7作品すべてがなんらかの形で芝居、舞踊、舞台芸術にかかわり、その世界に棲む「魔」を描いている。どうしてもまた、作家が女性と男性という性の違いこそあれ、赤江瀑作品を思い起こしてしまう。バレエ界の魔『ニジンスキーの手』、能の世界の魔『禽獣の門』などなど…。考えてみれば、赤江瀑の描く「魔」が、数十年の時を経て特殊な題材でもなんでもなくなったということか。そしてまた、書き手として女性がようやく解放され、書きたいものを書きたいように書ける時代にはなったのだと、気づかされる。 1990年に作家デビュー、いまをときめく篠田節子、1991年から1994年までの作品集。私にとっては『美神解体』(角川ホラー文庫)以来、2册目の篠田節子ワールドだ。集英社文庫のテーマ別フェアで<ミステリー&ホラーの一冊>とされていた。しかし、そんなカテゴリーには収まり切れない作者のパワーが感じられる。<読んで毒の一冊>とでもいおうか。伝統文化を前に女性が囚われる一瞬の狂気を描いた『秋草』は、舞台が京都ということもあり、初期の赤江瀑作品を思い起こさせ、私には特に新鮮な題材ではなかった。幕切れも予想通りのイメージ。朝の通勤電車でページをめくる私の耳には、まだ乗降の物音が聞こえる。かつての恋人と再会した死者の国において、甘美な想い出をなぞるうち、不愉快さの刺(とげ)が少しずつあらわになる『38階の黄泉の国』には、パトリシア・ハイスミスやルース・レンデルに通じる、女性ならではの意地悪さ(誉め言葉だ)を感じる。ただ、この作品集の解説者小池真理子の世界でもある。海底で鱶を撮影中の事故で半身不随になったフォトグラファーの、その後の恐怖を描いたのが『柔らかな手』。海に潜む魔というと、またまた『ポセイドン変幻』や『カツオノエボシ獄』という赤江瀑作品なのだが、なるほど、鱶よりも妻の方が恐ろしかったのですね。でも次の『ピジョン・ブラッド』にしても、小池真理子が書きそううな展開。むしろ凄いと思ったのは、作品集の最後を占める『内助』である。誰も死なないのだが、フツーの人間の日常の持つ怖さに痺れた。食の持つエロティシズムもコワイ。気づいたら降車駅だった。篠田氏は、読み手が本を閉じて現実世界に戻るための、長調のヴィヴィアーチェとしてこの作品を用意してくれたようだが、果たしてその現実に立ち返れるのかどうか、私には自信がない。 読む以前に本選びの時間は愉しい。迷い行く森を前に、どんなに悪い花を見つけられるのかわくわくしている自分がいる。今はもう古本屋をわざわざ訪ねるという時間を作ってはいないが、10年ほど前は自分のなじみのないジャンル、なじみのない作家のものをよく半額くらいで見つくろっていた。今は駅のコンコースなどに古書の出店があると覗いてみる程度だ。最近では昼休みに銀座まで歩き、1週間分新刊まとめ買いというのが習慣。今年もあと4日、9900で新年を迎えられたら上出来だが、少々無理なようだ。ただし年内に読む本は購入済、そのなかの一冊である。 金木犀の香る窓の下で、読書する幼子。昭和10年生まれの久世光彦、幼年時代から少年までの夕暮れにまつわる記憶を綴った物語風のエッセイ集。漢字にすべてルビがふってあったとはいえ、3、4歳の子が、暗い森の湿った木々の根元に開く妖しい花に魅せられたごとく横溝正史の「真珠郎」や江戸川乱歩を読み耽る、早熟さに驚く。漱石を小学一年で読むというのは、その時代ですら普通ではなかっただろう。しかし、向田邦子も久世と同様な読書体験をして育ったらしい。私も今まで読書に関しては早熟と思っていたが、かなりの割合で子供向けの本を読んでいたことになる。わが家にはルビだらけの「銀色ラッコのなみだ」がある。小学校高学年向きのものを一年生で読んだのだ。ルビをふってくれのは父である。夕方、風呂が沸くまで、父と私はよく風呂の蓋の上に座って本を読んだ。父はハーバート・リードあたりを原書で読んでいたのであろうか。父の書棚の本は美学・哲学が中心で、盗み読みの醍醐味はなかったかもしれない。サルトルがいた、ブルトンもいたが、乱歩や横溝は自分で買って読んだ。その後、幻想文学の迷宮へは、自ら好んで迷い込んだと思っている。私はツケで本が買える環境で育ったことに感謝する。同時に、未だ何者にもなりえていない現実をどうしたものか途方に暮れてもいる。 傭兵時代にモンゴールを裏切ったいう告発をされ、突然トーラスでの審問を受けることになったイシュトヴァーン。もはやアムネリスもイシュトヴァーンに甘美な思いを抱いてはいない。カメロン必死の弁護で、黒幕サイデン宰相を追い詰めたかに見えたが、休廷をはさんで事態は一転、知られているはずのないイシュトヴァーンの過去が次々と明るみに出る。サイデンにのり移っている者それはあの…。金蠍宮は文字どおり修羅場と化して。 心あたたまるクリスマス・ウィークのはずだったが、仕事がらみでついうっかり手に取り、そのまま再読してしまった。もちろん読後の私は、平忠彦(すみません、敬称略させていただくことお許しください)の一ファンでいられる至福に、心あたたまるクリスマス・ウィークを過ごしている。このHPの隣の部屋ALPHABET STADIUMのC、J、P項に登場する平忠彦の、生い立ちから1988年春までを、中島祥和が取材したノンフィクション。人力飛行機の取材でヤマハ発動機の人たちと知り合う以前から、私は平忠彦を、ファンの立場から知っていたし、端正な外見とは裏腹に派手さのない努力の人という印象はいまも変わらない。バイク乗りはじめはよくコケたということにも親しみを感じた。自転車乗りにはおなじみの日本サイクルセンターにてオフのトレーニングをしていたこと、シーズン開幕直前に自転車で転倒、骨折したことで、ますます親しみを感じた。あの、サイテーの映画『汚れた英雄』で、草刈正雄の代わりにすべてのライディング・シーンをこなしたとき、平の寡黙さが格好良かったので、主人公のキャラが饒舌から落ち着いた男へと変化したというエピソードは他の書物で読んだ。平がライディング・テクニックを語らないのは有名なので、この本が一体どのような読者に購入されたのか、ふと考える。おそらく、私のような、ファンのためなのだろう。最近、ヤマハの友人がバイク・ツーリングの折に、平忠彦のサインを貰ってくれた。バイクだったので色紙が持てなかったという言い訳つきで。罫線付きの手帳の1ページなのが苦笑を誘う平忠彦のサインには、To MIREI SANと記されている。眺めるたびに、至福の瞬間がそこにある。 忘却事象閲覧塔、雲母印書房、残像保管庫、人工降雨機、蝙蝠的手品師、幻の蒸溜酒「ゴールデン・スランバー」、遊星オペラ劇場……目次を辿るだけでも、わくわくさせられる言葉たちの集まりだ。 発行された1996年は、賢治生誕100年の年。宮沢賢治の作品のなかから綺羅星のごとき言葉を再編集、イーハトーブの四季が、美しい写真とともにある。全4巻のうち、好きな言葉、好きな写真の収められた第3巻を購入した。引用の1は、壮絶な夕焼け、引用の2は藍い夜に糸杉を照らす蒼い月。生命の不思議、有難さというものをかみしめる。プレゼント本にどうぞ。あーすっかり毒が抜けてしまいました。 早朝、夫の眠る寝台から年上の愛人宅へ向かってハーレーダヴィッドソンにまたがりアウトバーンを疾走する若妻レベッカ。アグノーからハイデルベルグまでの数時間のライディング、過ぎ去る風景、レベッカの脳裏にうかぶイメージの数々を綴った長編小説。今月3冊目のマンディアルグ。オートバイを走らせているときはライダーズ・ハイだし、カフェでひと休みの最中とかには年上の愛人ダニエルとの逢引、情事を思い出すという状態は、危険としかいいようがない。さてこの作品は映画化されている。レベッカ=マリアンヌ・フェイスフル、ダニエル=アラン・ドロン、邦題は「あの胸にもういちど」。観てはいないのだが、マリアンヌ・フェイスフルの、全身黒の革ツナギ姿には記憶がある。マンディアルグ作だったのか。考古学系で(実際考古学を修めたとのこと、美術品収集家ポール・ベルナールの孫というのは後から聞いて納得)、暗い博物館系で、粘っこく狂った詩のような作品ばかりだったのだが、この作品でポピュラー作家の仲間入りをしたらしい。シュルレアリスムのブルトンには当初から高い評価を得ていたとのことだ。さーて、年末は「シュルレアリスム宣言」(アンドレ・ブルトン)再読に行ってみるとするか。 もう、元祖検屍官ケイ・スカーペッタには期待通りの形では会えないのではという危惧は一掃された。読後、ありがたいことに第11作への渇望が生まれたからである。いままで以上にケイの心中が語られるので、感情移入がしやすい。読み進みも早く、600ページを超えているにもかかわらず、計4時間で読了。注意!第9作「業火」を読んでいない方で読む予定のある方も、ここからは先は読まないでください。前作でのショッキングなベントン・ウェズリーの死。ケイは仕事に没頭しているように見える。マリーノとルーシーは、ベントンに捨てられたような気持ちでいる。ケイを含めた3人は互いに気づかい合っているために、結果的にもっともっと傷ついている。ベントンの死から1年後の1997年12月、死の前に遺したベントンの手紙が、ケイの元へ届けられる。折しも港で発見されたコンテナ中の腐乱死体、死体に付着した金色の毛…捜査の舞台はパリ、そしてリヨンのインターポールへ。異常な犯人像は、奇病に頼ったせいか、単純すぎてコワクはない。犯人よりもむしろ、ケイを陥れようとする人々の方がコワイ。検屍局内部での盗難、ケイ局長と名乗る人物によるCHATの存在、ケイの秘書には偽のケイからメールが送られていた…等。美貌と悪知恵でのしあがってきた新任女性副署長とそのとりまきども。おかげで、制服組に格下げされたマリーノのいらだちといったら、もう。犯人との死闘というお約束のクライマックスにほとんどページが割かれていないのは意外(たったの6ページ)だが、リヨンのATF捜査官ジェイ(おそらく20歳以上年下、頭脳明晰、容姿端麗、家柄良)との突然の恋の行く末も気になるし、ジェイの登場をきっかけに錯乱状態、保護者にしてききわけのない子供のような存在マリーノ、囮捜査に失敗、大切な人生のパートナーを傷つけ、それ以上に自らが傷ついているルーシーとの関係にもまだまだ波乱がありそうな今後に注目。 伊那の高速バスステーション内の売店で購入。なぜかイエーツの詩集『薔薇』も置いてあった。キャッチは「痛快ハードボイルド」ということで、ユーモア系ハードボイルド連作集。大沢在昌という作家の硬派な部分(新宿鮫シリーズ)にはこれからおつきあい願おうと思っているので、まずはお手柔らかにというところ。で、実際柔らかでした、はい。語り手はヤマダ・イチロー、渋谷にあるタウン誌編集長、非力なインテリゲンチャを自称。銀座6丁目にある高級ホテルの御曹司にしてフリーのやくざムウこと武藤峻が2年間のアメリカ遊学から帰国、私立探偵を開業したところで、ヤマダ君の苦難がはじまる。東京の地理・風俗に詳しいというアイデアの部分をヤマダが担当、ムウはといえばビジュアル・体力・行動力(女性に関しては特に)担当。アメリカの新興宗教やら、マフィアやら、FBIやら、銀座の老舗極道の女親分やら、恐怖の新人女性編集者やらが登場する「囮にされた探偵たち」にはじまる全5話。ハデな銃撃戦があっても、なぜか死人が出ないのは健全ですね。なわけで、毒毒度は低いです。本筋よりも、「趣味で深夜開業している某大会社の会長蕎麦」や「まさかのときには従業員が身代わりで交通刑務所にも入ってくれる超高級車専門レンタカー屋」や「身よりのない年寄りに養女としてあっせんされ、死ぬまで介護するドーターたち」というありそうななさそうな話に興味しんしん。
マンディアルグの同名の短編集に2編を追加したもの。確かに「サビーヌ」と「満潮」は毛色が違う、きわめて仏蘭西映画的なエピソードだ。ちなみに5編のうち流血しないのは「満潮」だけなので、血の苦手な方にはおすすめしない。ドイツが超自然的寓話の安住の地であるのと対照的に、そもそもフランス人は幻想的な頭脳を持っていないと言ったのはルイ・ヴァックスであったか(「幻想の美学」、窪田般弥訳、白水社文庫クセジュ)。そんななかでマンディアルグの短編は、腐った菓子あるいは深い森から滲み出てくるような、病的でねばっこい詩に近いと評されていた。「サビーヌ」にエゴン・シーレの描くところの女性、「仔羊の血」に「羊たちの沈黙」、引用した「ポムレー路地」に、緑魔子の出てくる芝居、「ビアズレーの墓」に「ロッキーホラーショー」を連想した。これって貧困だろうか。好き嫌いだけで言うと、「ポムレー路地」が好み。「ビアズレーの墓」では、オセロ役者が登場する冒頭にはひかれたのだが、屋敷でのドンチャン騒ぎの頃には興味も薄れてしまった。美術館めぐりの最後を、自分の好きな絵でしめくくれるとは限らない。 スポーツ選手は、スタジアムで、グラウンドで何事かを表現する人間である。かれは言葉にはしないが、かれの行動に心情が表現されているのだ。しかし、マスコミに読み取る能力を求めても仕方ないと、かれは気づいている。あまりにも憶測で勝手に書かれた嘘が多すぎる、これは自分を理解してくれようとしている人たちに、すごく申し訳ない…スポーツをする者としての中田英寿と、中田を見つめ、行動を読み取る小松成実の共同作業で完成した本書。私は中田英寿には特別な思いはないが、中田が信頼する小松成美という存在に興味を持ったので購入。読んでみると、類い稀なるエゴイストがなぜサッカーをやっているのかが、少なくとも尻尾の先くらいは、かすった気がする。決して思い通りにならないからだ。一筋縄ではいかないからなのだ。 と序文にある通りの物語だ。発表当時は、作者の本名も明かされなかった20世紀の奇書。26年後にマンディアルグ作とあきらかにされ、序文も加えられた。私が読んだのは、たしか最初のディナーが終わったところまで、約三分の一。いつかは全編とは思っていたが、なるほど、白水社から出版されていたのかと納得。さて、マンディアルグと澁澤龍彦の組み合わせである。当然ながら、朝の通勤電車で読むのにふさわしくはなかった。知人の所有する断崖の城ガムユーシュへ招待された「私」の体験を綴ったものだが、淫蕩、ゲテモノ喰い、スカトロ、SM、鶏姦、獣姦、赤児殺し、人妻の凌辱、拷問殺人…なんでもアリ。それでいて、美しい文章で語られてしまう。本を読んで気分が悪くなった体験は過去に一回だけ、揺れるバスの車中、すきっ腹にクライヴ・バーカー一気読みだったのだが、今回は特に体調の変化はなし。後日談により、後味はよくなったのか悪くなったのか。訳者あとがきによると、「ボマルツォの怪物」というマンディアルグのエッセイ集が存在するらしい。ボマルツォといえば、わが憧れの地ではないか。何とか入手したいものだが。 「ザ・ホテル」を舞台としたノンフィクション。英国はロンドンの世界最高級ホテル「クラリッジ」がモデルとなり、宿泊者名とルーム・ナンバーを変えてある以外はすべて実際に起きた出来事という。ジェフリー・ロビンソンは「クラリッジ」に数ヵ月滞在して書き上げたそうだ。フランス生まれの総支配人トゥザーンの出勤風景からはじまるホテルの一日。採算を度外視して顧客へのサーヴィスにつとめてきた老舗のホテルが近代的経営をするべく徐々に変貌を遂げていく過程で、まずホテル内部での葛藤がある。歴代の総支配人とは異なり、モーニングではなくダークスーツを着用し、従業員食堂で食事するトゥザーンに馴染めない古参の従業員たち。トリュフや超高価なビネガーをめぐって総料理長と料飲支配人の攻防もある。夜間支配人の苦労がある。韓国大統領の滞在にはじまり、エリザベス女王の晩餐会で「ザ・ホテル」はクライマックスを迎える。ちょっと厚めなので多少心配したのだが、飽きさせない語り口。扉の向こうに隠された数々のエピソードの中でも、夜間支配人アラン・ソルターの、嵐のようなひと晩が印象深い。 各章の冒頭にある言葉は、すべてなかなか気に入った。しかし、翻訳は下巻に入ってもしっくりこない、平凡すぎるのかも知れない。「背筋がぞくぞくする」とか「くたくただった」とか…。殺人犯の名は上巻の2ページ目で、殺人の方法も、死体の処理方法も読者に知らされている。サスペンスフルなのは、主人公たち捜査側と犯人との邂逅のみというのは淋しすぎるぞ…シリーズ処女作と第2作をそれなりに楽しんだ記憶があるのに。この不満が聞こえたのか、ラストには突然のおみやげ付き。第1作でジェシカがアキレス腱を切断され、徐々に血を飲まれるという悪夢の体験の末に収監したマティサックが脱獄、殺しのメッセージを送りつけてくるのだ。検屍官シリーズの宿敵ゴールドとキャリー・グレセンを足したような展開の次回作なのか。 元祖検屍官ケイ・スカーペッタは失礼ながらアクションの似合わない年齢に達し、コーンウェルも新シリーズに力を入れているようだ…というわけかどうか、若くて美人で仕事のできるニューヒロインとして登場したFBI所属の検死官ジェシカ・コランシリーズ第3作。舞台はジェシカの休暇先ハワイ。先住民族から白人が奪い、さらに日本人が襲撃した土地。 今は日本人が最も好む観光地として存在する。ハワイの地理、歴史、先住民・白人・混血・日系人らそれぞれの社会、宗教的問題、経済的差異などの記述は細かいのだが、登場人物の言動を表現するのにどうも馴染めないというか、ところどころしっくりこない文章が気になる。訳者が悪いのではなく、そもそも作者のせいなのか、読み手との相性が悪いだけなのか。翻訳本の難しいところだ。ついでなので余談に走ろう。扶桑社ミステリー文庫というのは、昔から取り揃えている書店が少なかったのだが、現状もさほど変化はないようだ。ないものは本当にない。思い出したように書店に並ぶ。しかも、シリーズ第2作だけ翻訳権を持っているなどどいう面倒くさいこともしばしば。 「ブラッドベリがやってくる」と同時に出版されたエッセイ集。原題はYESTERMORROWという、まさにファンタジー。19篇のうち、1953年のエッセイが1篇の他は1970年代から1990年までの、比較的最近のものだ。ブラッドベリの創作に対する姿勢は、終始一貫している。つまり、自分が楽しくなくて、何が創造か。つねに、真面目に遊ぶ。全編がきらめきに充ちた文章である。ここまで自然にブラッドベリを表現できる翻訳の仕事は尊敬に値する。さぞかし、翻訳作業が楽しかったに違いない。 (c) atelier millet 1999-2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||