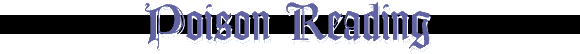| 2000/05/30-9796 |
| ロマネ・コンティ・一九三五年 |
開高 健 |
文春文庫 |
1981年7月25日第1刷 |
再 毒毒度:2
|
“ことごとくを聞いている。しかし、それは意識に掻き傷も爪跡ものこさないのである。昂揚もなく、下降もない。沸騰もなく、沈澱もない。暑熱もないが、凍結もない。希望もなく、後悔もない。期待もないが、逡巡もない。善もなければ、悪もない。言語もなく、思惟もなく、他者もない。ただのびのびとよこたわって澄みきった北方の湖のようなもののさなかにありつつ前方にそれを眺め、下方にそれを眺める。おだやかで澄明な光が射し、閃きも翳りもなく揺蕩している。それほど淡麗な無化はかつて味わったことがなかった”(飽満の種子)
“二階へもどって『スターリンも味を変えられなかったウォッカ』とか『一滴一滴が宝石です』とか、『ここから発し、ここへ回帰する』などと、右から左へ書きちらす。ふと気がつくと、胃のむかつきはおさまり、血は中和されて、夕方が運河から窓へにじりよっている。潮を体のまわりに感じつつ瓶をさがしにかかる。愚行の輪がのしかかり、そそのかしにかかる。死人のような指で。蛙の膚のような手で…”(黄昏の力)
食。阿片。酒。釣り。漂泊。そして再び酒。六つの物語はどれもどこかしらみだらで、官能的。すんなり読みとおさせない語彙の数々。どことなく、釣れた魚をつかんだときの、ぬめっとした感覚。語尾はきっぱりとしながらも、執拗な描写。開高健の文章の、この、きっぱり感が好きである。よく真似たりもするのだが。 |
| 2000/05/29-9797 |
| ガストン・ルルーの恐怖夜話 |
ガストン・ルルー
飯島 宏 訳 |
創元推理文庫 |
1983年10月21日初版 |
再 毒毒度:2
|
| “悪魔との出会いを本気で望む者は真心をこめて呼び出しさえすればよい”
ミステリィ『黄色い部屋の謎』、今やミュージカルが有名な『オペラ座の怪人』の作者ガストン・ルルーによる綺譚集。ツーロンのヴィエイユ・ダンスのカフェに集う老船乗りたちが語る世にも奇妙な物語である。復讐譚、毒婦、極限状態での人肉喰い、蝋人形の館、悪魔との取引、泊まり客を襲う旅篭の主人…ヒットしたホラー映画のパターンが、ほとんど網羅されている。書かれた時期は1920年代、かなりセンセーショナルであったことは確かだ。
5月29日というのは山際淳司氏の命日であり、このHPがうまれるきっかけになった日なのだが、特に、ちなんだ毒書はしなかった。 |
| 2000/05/28-9798 |
惨敗
二〇〇二年への序曲 -- |
金子 達仁 |
幻冬舎文庫 |
2000年4月25日初版発行 |
毒毒度:2
|
“たぶん日本は、二〇〇二年もダメだろう。日本人が日本人であるがゆえに、ダメだろう。きっと我々は、また同じことを四年後に繰り返す。そして、史上初めてグループ・リーグを突破できなかった開催国として、ワールドカップの歴史に汚名を残すことになるのだろう”
“なぜ、『28年目のハーフタイム』を書くことができたのか。僕自身が、アトランタでの戦いに胸を打たれたからであり、大会が終わって半年近く経って聞いた選手たちの肉声が、あまりにも衝撃的なものだったから”
“なぜ『決戦前夜』を書くことができたのか。マスコミに心を開くことの少ない、それでいながら「わかってもらいたい」との気持ちを捨てきれない二人の選手の肉声を、少しでも真実に近い形で伝えたかったから”
ではなぜ、今回は完全なる書き下ろしができなかったのか。ひとつ、物理的に不可能だったこと(現地で選手達を取材することができない)。ひとつ、原稿を書くにあたって前二作と異なるスタイルが見つからなかったこと。最後にして最大の理由は、ワールドカップで勝ちたいという気持ちが日本(日本代表、ファン、日本の社会)から感じられなかったこと。最終予選に満ちていた激しい祈りは、キリンカップの会場にはなかった。著者が目撃したのは遠足に出かける幼児たちと、それを見送る父兄のような、のどかな雰囲気だった。「やらなければつぶされる」という危機感を持たぬままフランスへ代表を送った結果は見ての通りである。日本のサッカーに夜明けは訪れなかった。さらに悪いことには、2002年にも夜明けはないかも知れないということだ。フランス大会が終わってからの日本サッカー界の動きを見ればわかる。
先日の記者会見で、トルシエは言った、「かんじんなのは、任期は6月ではなく、10月31日までだということだ」。2002年まで岡田監督で行くといいながらトルシエに任せ、さらに今さらベンゲルだというウワサがある。岡田監督時代にもアドバイザーとして名前が挙げられた人物である。ワールドカップ開催国でありながら決勝トーナメントにすすめないという前代未聞の事態に陥ってしまったとき、監督がベンゲルだったら納得してもらえるだろうという思惑があるらしい。アホか。惨敗するつもりなのだ。
西野朗は困惑した。彼の率いるレイソルは優勝にからんでいる最中だった。今はチームに集中したい、勝手なことを言わないでくれ。案の定、チームは動揺した。レイソル側は怒り、どんなことがあっても西野は出さないといった。
こんな現実があり、「不吉な予言者」と呼ばれる金子達仁の本がある。購入してからずいぶんたつが、間にさまざまな本が毒破され、だらだら読みつづける結果となった。雨男というより「嵐を呼ぶ男」らしいことがわかって、親しみを感じている。「いいストライカーは人でなし」説は面白かった。が、2000年の現実は…。シドニー・オリンピックの夏も間近、2002年もあっという間である。日本のサッカーというオーケストラが奏でようとする曲は、序曲のまま何の展開もなく終わりそうな気がしている。『惨敗』というタイトルがそのまま2002年にも使えるのではという恐怖すら感じている。栄光という夜明けを望む者は存在するはずなのに、未だその数が足らない。そしてまた、望んだからといって夜明けは訪れてくるものではない、そう、幾ばくかの幸運に恵まれなければ。われわれはまた2002年を、ただ都合のよい幸運によってのみ待たねばならないのか。 |
 |
| 2000/05/26-9799 |
| 吸血鬼幻想 ドラキュラ王国へ |
菊池 秀行 |
中公文庫 |
2000年5月25日発行 |
毒毒度:1
|
“見たいものは見られない。旅とはこんなものなのだ”
“人はなぜ、魔の近くに棲むのか。魔性のものがいると知って、なぜ、村を捨てて逃げようとしないのか。これは人の世に魔界が存在するのか、或いは魔界の中に人間の世界が許されているのか。人間はその場合、魔物に仕えるのか、一生怯えて暮らすのか”
“この世界は本当は魔性の国であって、人間は単なる間借り人にすぎないのではないだろうか”
千葉県は銚子の生まれ。隣は銚盛館という映画館であった。映画、特にドラキュラ映画にはうるさい。出不精を自認する作家、菊池秀行がNHK取材班と旅にでた。番組は1994年11月6日にNHK衛星第2で放映された『世界・わが心の旅 トランシルヴァニア・吸血鬼幻想』である。残念ながら、観ていない。2年後に書き下ろしで出版され、さらに4年後、こうして文庫化された。放映されなかったウラ話として、キチンと王道を歩んでいる。大好きなランパブの話題もさりげない以上に登場するし、程よく横道にそれる。お約束のようにパウチ盗難事件まで起こる。時間があけば、どこででもどんな紙にでも原稿を書ける特技があるようだ。他に時間のつぶし方を知らないらしい。映画館で、映画に飽きてしまって暗闇で書いたこともあるとか。そこまでやるか…。 |
| 2000/05/23-9800 |
| 森博嗣のミステリィ工作室 |
森 博嗣
|
メディアファクトリー ダ・ヴィンチ編集室 |
1999年3月18日第1刷発行 |
毒毒度:1
|
“萩尾望都という作家の才能に触れることは、それだけで一つの人生です”
“萩尾望都という今世紀最大の天才漫画家の作品に触れなければ、森は創作を始めなかったと思う。そして今回、そのヒーローに直接会ってしまったのだ。これは過ちだっただろうか…。しかし…、
過ちを犯すことほど、心踊ることはない。”
おあと9800。ちなみに1999年7月23日に、死ぬまでに10000冊という試みがはじめられていて、最初の一冊が森博嗣『すべてがFになる』だった(毒読19990723-19990831参照)。あと2ヵ月で50冊くらいいけるのだろうか、微妙なところ。さてこの本はふだんあとがきを書かない森博嗣が、読者のためのアフターサービスとして書いたもの。萩尾望都との対談とルーツ・ミステリ100が気になって購入した。私は、森ミステリィをまだ5冊しか読んでいない駆け出し者。特にファンではないが文庫が出れば必ず買う。興味があるのは、小説を書くように至ったその経歴かもしれない。1957年生まれ、子供の頃は特に本屋に本を買うために行くことはなかった。高校時代より、萩尾望都を神とあがめるようになる。萩尾望都というよりも大島弓子にかなり似た絵を描いていた(脇役や小物はひさうちみきお風)。模型飛行機、HOゲージ、スポーツ・カーの話…。何らか影響を受けた100冊の中にハンドラーが3冊入っている。現在一番のお気に入りとか。犀川&西之園のシリーズは、ハンドラーのシリーズを目ざしたらしい。近いとは思えないけれども。『羊たちの沈黙』のレクター博士にヒントを得て『すべてがFになる』の冒頭場面を書いたとのことだが、これも?ではある。 |
| 2000/05/21-9801 |
| 色の名前 |
近江 源太郎 監修
ネイチャープロ編集室 構成・文 |
角川書店 |
2000年4月25日初版発行 |
毒毒度:-2
|
| 宵藍。時雨の色。暮色。セラドン・グリーン。猩々緋。菫色。オールド・ローズ。紺青。インディゴ。
光琳社出版が存在しなくなり、人にあげてしまった『色々な色』を確保できずにいたのだが、こうして角川から『色の名前』と名を変えて刊行された。光琳社版3200円→角川版2500円と、廉価になっている。装丁はほとんど変わっていないような気がするが、表4のISBNコードの部分を、製版上でいうところの白マド・文字スミノセ処理にせざるをえない悲しさ。写真のムードは当然、壊れている…。
色の名前の由来、特に動物や植物の写真も多数。図鑑として楽しめる。雀色・雀頭色の説明に添えられた雀たちの写真には笑わしてもらった。もしその動物が絶滅してしまった場合、その色の名前はどうなるのだろう?
自分の色は何色? おそらくこのホームページのTOPの色に近い。青色は自然の物としては存在しにくく、存在しても毒が多い。コバルトしかり、青黴しかり。宙に近い青。夜に近い青。淵に近い青。このHPを読書の快楽の深い海と表現してくださった方には、大いに感謝。 |
| 2000/05/20-9802 |
勝者に報酬はない・キリマンジャロの雪
--ヘミングウェイ全短編2 -- |
アーネスト・ヘミングウェイ
高見 浩 訳 |
新潮文庫 |
1996年7月1日発行 |
毒毒度:3
|
“自分は何を恐れているのだろう? いや、不安とか恐怖が自分をむしばんでいるのではない。無<ナダ>というやつなのだ、おれにとりついているのは。この世はすべて、無<ナダ>、であって、人間もまた、無<ナダ>、なんだ。要するにそれだけのことだから、光、がありさえすればいい。それに、ある種の清潔さと秩序が。無<ナダ>、のなかで生きながらそれと気づかない者もいるが、おれは気づいている。(清潔で、とても明るいところ)
“ほとんどの人間は動物のように死ぬ。人間らしくは死なない”(死者の博物誌)
“宗教は人民の阿片である。…そして音楽も人民の阿片だ。…酒は人民の最高の阿片、そう、すこぶる上質の阿片だ。…ギャンブルがある。これもまた人民の阿片、そういう言い方が許されれば、人民の最古の阿片だ”(ギャンブラーと尼僧とラジオ)
“彼は、スペインの諺にあるように、<幻想に埋もれて>死んだのである。彼には、それらの幻想の一つとして払い捨てる暇もなければ、最後の瞬間に懺悔をすませる暇もなかった。”(世界の首都)
“おれは自分で自分の才能をぶち壊したのだ。そう、それを使わないことによって、自分と自分の信念を裏切ることによって。自分の感性の触手を鈍らせるほど酒を飲むことによって。怠惰によって。安逸によって。それから、俗物根性によって。誇りと偏見によって。ありとあらゆることによって。”(キリマンジャロの雪)
GWに計画して結局第1集しか読めなかったヘミングウェイの第2集。『勝者に報酬はない WINNER TAKE NOTHING』という短編集にはスポーツを題材にしたものが収録されているわけではない。なぜこの題名になったのだろうか。アメリカは大恐慌のさなかにあった。ヘミングウェイは、キー・ウエストの太陽を浴びながら大がかりな海釣りを愉しみ、サファリにでかけライオンやバッファローを撃ち、まるで好き勝手に暮らしているように見えても、その実、ひっそりと死を想っていた。
気がつくと、無<ナダ>という言葉にとりつかれている。すべての人間が来たりて、帰するところ、無<ナダ>。幻想に生き、怠惰と安逸とで才能をぶち壊している、これは私だ。ホラーを読むよりも、怖い。なにげないようでいて、いちいち突き刺さってくる文章が痛い。 |
 |
| 2000/05/18-9803 |
| 無間人形 新宿鮫IV |
大沢在昌 |
光文社文庫 |
2000年5月20日初版1刷発行 |
毒毒度:1
|
“やくざは、人間のそういう心理のあやをついてくる。一度はまれば、すべてそれがテクニックであったことに気づくが、そのときはもう、相手に望むものをさしだすことでしか、抜けでる方法はない。もちろん、警察という、もうひとつの逃げ道もあるが。”
“あなたは生まれついての女王だ。金持ちで家柄がよくて、洗練されていて美人なのだ。なのに一度の失敗で、人生を投げ出してしまった。そんなあなたには、叩かれて泥まみれになって、唇を噛み切って戦っている若い奴のことなんかわかりっこないんだ”
文庫化されてから毎年8月に出ているシリーズだが、今年は5月に出た。ということは年内に5作目が出るのだろうか。今のところ、和もので必ず買う文庫はグイン・サーガ、森博嗣、そしてこの新宿鮫シリーズだ。直木賞を受賞した第4 作、ひとことでいえば読みやすい。前3作に比べて登場人物が整理されたせいか。覚醒剤の密売ルートを追う新宿署の警部鮫島と、恋人であるロック歌手、晶。この絆は揺らぎそうにない。ただ『毒猿』に登場する刑事と暗殺者ほどにはインパクトのある人物が出てこないというのは、悲しむべきことかも。 |
| 2000/05/17-9804 |
| 死霊たちの宴(下) |
ロバート・R・マキャモン他
スキップ&スペクター編
夏来健次 訳 |
創元推理文庫 |
1998年8月14日初版 |
毒毒度:4
|
“頭に浮かぶことはいつも、生きることは死ぬことで死ぬことは生きることで、人は結局、生きていようが死んでいようが、やっぱり怖がっているということだ”(「レス・ザン・ゾンビ」ダグラス・E・ウィンター)
“彼はいつも愛をさがしていた。愛を分かちあえるだれかを。だが、この灰色の街がネズミと安らぎのない死者とで満たされる前は、これほど愛を強く意識したことはなかった”(「わたしを食べて」ロバート・R・マキャモン)
死せる生者か、生ける死者か。もはや区別する必要はない。ついに生ける者がゾンビを喰うところまで行っているのだ。あるいは生ける死を免れた者が、ゾンビを使って宗教組織を作る「キャデラック砂漠の奥地にて、死者たちと戯るの記」(ジョー・R・ランズデール)。あるいはまた、その二つのことが同時に起こる「聖ジェリー教団 VS ウォームボーイ」(デイヴ・J・ショウ)まで。そしてゾンビ同士の至上の愛を描いたマキャモンの作品で締めくくられる。 |
| 2000/05/16-9805 |
| 死霊たちの宴(上) |
スティーヴン・キング他
スキップ&スペクター編
夏来健次 訳 |
創元推理文庫 |
1998年8月14日初版 |
毒毒度:3
|
“長い道のりの果てにあるものは、死だけとは限らない。選択肢の大半は、死よりもはるかに好ましくないものにつながっているのだ--しかも、苦痛に満ちた長い旅の果てに。”
“人類世界のすべてがとんでもない危機にみまわれ、余儀なく巻きこまれてしまったとき--その危機のすごさにもう耐えられないと思ったとき……かまうことはない、勇気を持って逃げ出すんだ。おまえには逃げる権利があり、ほかの選択肢をだれかに強いられるいわれはない。”(「選択」グレン・ウェイジー)
私はいわゆるスプラッタ・パンクはそれほど好まないが、一応押さえておく。東京創元社ゆえ、それほど簡単に品切れにはならないとは思っても用心にこしたことはない。ジョージ・A・ロメロと「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」に捧げられた、生きている死者のアンソロジー。上巻にはキングが、下巻にはマキャモンが収録されている。ゾンビの正体はわかっている。ゾンビに噛まれたらその人間もゾンビになる。しかし編者の言う通り「最奥まで」行ってしまった場合、今度は生きた人間がゾンビを喰う物語となるのだ。 |
| 2000/05/15-9806 |
パロの苦悶
グイン・サーガ第72巻 |
栗本 薫 |
ハヤカワ文庫JA |
2000年5月15日発行 |
毒毒度:2
|
| “…所詮このかたは、軍神として生きることしか知らぬかたなのかもしれぬ。…どれほどたおやかに、貴婦人のように見えようとも、片足をうしない、病の床に伏そうとも--このかたはルアーの申し子だ、ルアーの子なのだ”
パロの危機。自らの手足ともいうべきヴァレリウスと、パロの心ともいうべき妻リンダを、従弟レムス国王に囚われたアルド・ナリスはついにパロ聖王を宣言する。レムスに憑依した竜王ヤンダル・ゾックの狙いはまさにアルド・ナリスその人。古代機械を動かせる、真のアルド・ナリスを必要としているのだ。ナリスにイエスと言わせるためには、ヴァレリウスを傷つけ、リンダを辱めることをもするだろう。ナリスはパロを守るために再びルアーの申し子となれるか。空から魔道士の骸が降ってくる、それは囚われたヴァレリウスなのか? クルスタルの民を虐殺しはじめた国王側の騎士団は、もはや人間の姿をしていなかった…。ついに著者自身、100冊では終わらないかも宣言をしたシリーズ第72巻。 |
| 2000/05/14-9807 |
| 名門校 殺人のルール |
エリザベス・ジョージ
小菅正夫 訳 |
新潮文庫 |
1996年1月1日発行 |
毒毒度:3
|
“いまケヴィン・ウェートリーの顔に刻み込まれたような苦悩に直面して、自分の動機の身勝手なあさましさにひたすら身の縮む思いをした。ここに真の空虚がある。自分の感じていた孤独や喪失感が何であれ、これと較べればそんなものはお笑い草もいいところだ。”
“選択は簡単だった。死ぬか、何も言わないかだ。彼はたったの十三歳だった。選択の余地はまったくなかった”
“若さとはそうしたものなのだ。つねに自分たちが不滅であることを確信している”
おじさんの街S駅地下コンコース、移動古本屋での掘り出し物。デビュー作『そしてボビーは死んだ』が『大いなる救い』と名を変えて再版されているものの、この第3作だけは品切れで入手できなかった。これでトマス・リンリー&バーバラ・ハヴァーズのシリーズすべて手にしたことになる。これを機会に隣の部屋に新たな展開ができればよいのだが。エリザベス・ジョージは純粋なアメリカ女性でありながらイギリスを舞台にしたミステリィを書く。主人公は貴族刑事トマス・リンリーと、仕事のパートナーである巡査部長バーバラ・ハヴァーズ。彼女は労働者階級の出身で、病気の両親という現実から逃れるべく仕事に打ち込むような女性。容貌から家柄まですべてが整ったリンリーとは正反対だ。リンリーの親友サイモン・オールコート=セント・ジェイムズとその妻デボラ、リンリーの女友達レディ・ヘレン・クライドもかなり重要な位置を占め、作品によっては主役になり得るキャラクター。
リンリーのイートン校時代の同級生から、持ち込まれた、13歳の少年の行方不明事件。ほどなく、それは拷問を受けた死体の遺棄事件となる。張り出し窓、礼拝堂、聖歌隊、薔薇窓。髪をぴっちりなでつけ、いささかの服装の乱れもないシニア監督生。学校内部で何が起こっていたか生徒の誰もが知っていたことは明らかだが、誰も語ろうとはしない。子供たちの一瞬の表情、視線、行動のはしばしで、ほころびが見えはじめる。リンリーとハヴァーズの捜査は伝統あるブレッドガー=チェンバーズの真の姿を暴くこととなる。マタイによる福音書が引用され、学校は「白く塗ってある墓」にたとえられる。外見は美しいが、内側は死人(しびと)の骨とさまざまな穢れとに満ちていると…。
親子の絆、学校でのいじめ、同性愛、性的虐待、復讐、愛の証し…テーマは相変わらず重い。想像の世界に生きていれば安全だ。魂が刺し貫かれるような危険はないからだ。真実と立ち向かうことを勇気と呼ぶならば、彼らはずっと逃げ続けていたのであり、ついに逃げる場所はなくなった。そして、今さら真実に生きようとするには遅すぎた。 |
 |
| 2000/05/11-9808 |
| スケッチ・ブック |
ワシントン・アーヴィング
吉田甲子太郎 訳 |
新潮文庫 |
1957年5月20日発行
2000年2月20日33刷改版 |
毒毒度:1
|
| “それは動かなかった。暗闇のなかで、からだを引きしめて、巨大な怪物が旅人に飛びかかろうとしているかのようだった”
映画《スリーピーホロウ》が話題になったところで、原作の改版が出た。ちなみに「リップ・ヴァン・ウィンクル」も収録。リップ・ヴァン・ウィンクルと同じくらいこの「スリーピー・ホローの伝説」の主人公イカバット・クレーンは有名であるらしい。映画は原作に忠実ではないようだ。というのも、原作では主人公である教師の行状と結局は実りのなかった恋愛が語られるばかりで、首のない騎士の登場がかなり後半、しかもそれこそ風のように去っていくからだ。ホラーとして読むなら、肩すかしと言えるだろう。伝統的なクリスマスの思い出を綴ったエッセイ風の連作が印象に残る。 |
| 2000/05/10-9809 |
| 酔いどれ家鴨亭のかくも長き煩悶 |
マーサ・グライムズ
吉野美恵子 訳 |
文春文庫 |
1994年12月10日第1刷 |
毒毒度:2
|
“「…ただ、こまったことに、ハムレットはクローディアスに復讐したいと思いながら、最後にようやく目当ての人物にたどり着くまでに、殺さなくてもいい人間を次々に殺してまわるんだよ」
爽快なまでに単純明快な『ハムレット』の解釈であると、メルローズも認めざるをえなかった”
“その紙きれにぞっとさせられた、なぜならそれは一種の署名だから--切り裂きジャックのような異常者が警察に送りつけて楽しむ、ちょっとしたラヴレターだ。やっかいなことに、そのての殺人者が一度だけ自分の名を記してやめることはまずない。”
迷ったときは、ミステリィを読め。一昨日が泊り仕事となったため、読み始めが中途半端ではあるが。訳されたのは11番目だが、実はシリーズ第4作。舞台はストラトフォード。シェイクスピアを観に行ったはずの警視リチャード・ジュリー&爵位返上伯爵メルローズ・プラントのコンビが難事件に巻き込まれる。被害者は、豪華イギリス・ツアーに参加したアメリカ人たち。ツアー参加者は裕福だがうさんくさい人物ばかり。子供がいる者同士再婚したため成立したにすぎない家族…あばずれの母娘、父親側の連れ子はもともと養子。下品で意地の悪いおば(しかも爵位あり)と、芝居がかった殉教者精神を持つ姪。誰も言いよらないオールド・ミス。誰にでも言いよられる男前。マーロー狂のコンピュータ・エンジニア。死体のそばにはエリザベス朝の詩の一部が書き置かれる。ほんの端役に至るまで、奇妙なほどリアリティを持つ人物描写…子供、老婦人、小さな動物はことのほか。引用された詩の出典を知っていればとは思うが、あいにくシェイクスピアもきちんと読んだことがない。それでも謎解きは愉しめる。殺人犯人は自らのクローディアスに結局会ったのだ。書き置きさえ残さなければ逃げおおせたかもしれないものを。 |
| 2000/05/07-9810 |
われらの時代・男だけの世界
--ヘミングウェイ全短編1 -- |
アーネスト・ヘミングウェイ
高見 浩 訳 |
新潮文庫 |
1995年10月1日第1刷発行 |
毒毒度:2
|
“「じゃあ、ジャイアンツの優勝は決まったようなもんじゃないか」”
「あれは楽勝だよ」 ビルは言った。「マグロウのやつがいい選手を手当たりしだい金で引き抜けるう ちは、優勝したって何の価値もないさ」
「でも、いい選手を残らず引き抜くことはできないだろう」ニックは言った。
「ほしい選手はみんな引き抜いてるからな、あいつは」ビルは言った。「それが無理な場合は、これと狙いをつけた選手に不満を抱かせて、自分のところにトレードさせるしかないようにもっていくのさ」
(われらの時代第3章「三日吹く風」)
“でも、ぼくにはわからない。この世の中って、せっかく本気で何かをはじめても、結局、何もあとには残らないみたいだ” (われらの時代第13章「ぼくの父」)
マグロウを誰かに言い換えることができるので思わず引用してみた。さて、今さらヘミングウェイでもないかもしれない。手にとったのは、山際淳司氏に教えられた「スポーツはすべてのことを、つまり人生ってやつを教えてくれる」というヘミングウェイの言葉を確認したかったからだ。ラムもライムもクラッシャーもないのでフローズンダイキリが作れない。代わりにエクアドルのリキュールをソーダで割って飲りながら、読みはじめている。「われらの時代 IN OUR TIME」では、各章の間にはさまれたごく短いスケッチが印象的だ。戦士達が血を流し、雄牛が、ピカドールの馬が、そしてマタドールが血を流し続ける。「われらの時代」第14章と15章にあたる「二つの心臓の大きな川」で描かれるのは、釣りという行為の官能。短編集「男だけの世界 MEN WITHOUT WOMEN」の冒頭を飾るのは、闘牛の官能だ。「敗れざる者」というタイトルからして魅力的だが、牛が倒れるまでの詳細な描写に、引き込まれる。 |
| 2000/05/06-9811 |
ひねもす
--a day of the sky-- |
高橋健司、林完次
|
光琳社出版 |
1999年3月4日発行 |
毒毒度:-3
|
| “朝未き。夜の明けきらない早朝の頃…星は消えかかりつつもまだ残っています”
光琳社出版はもはや存在しない。人にあげてしまった『色々な色』が入手できずに残念に思っていたのだが、最近になって角川書店から『色の名前』と名をかえて出版された。購入しようとして、近くの棚にこの掘り出し物を発見。光琳社出版としては、かなり終焉に近い時期に出版されたと思われる。『空の名前』の高橋健司と『宙の名前』の林完次が一緒に本を作った、昼の空と夜の宙の本。朝起き出して身のまわりの風景や空を撮る高橋健司。そこでしか撮れない風景のときのみ遠出する、自らは立ち止まって、巡りゆく季節を撮る。一方、昼間はロケハン、暮れなずむときから朝までが、林完次の時間だ。星も見えて地面も見えてくる朝が、一番好きだという。仕事が上手くいった満足感、そして安堵の朝。巻末の対談によって、異なるアプローチによる、それぞれの「そら」が語られる。日本ならではの風景と言葉が美しい。欲をいえば、一部の写真を割っている白線は余計なものでは? さて、5月に入り、毒毒度、かなりのマイナスモードへ突入。ばん回なるか。
|
| 2000/05/05-9812 |
葉っぱのフレディ
--いのちの旅-- |
レオ・バスカーリア作
みらいなな 訳、島田光雄 画 |
童話屋 |
1998年10月22日初版 |
毒毒度:-4
|
| 売れているらしい。もともとは子どものための本。童話と写真に絵が加わったコラボレーション。春生まれた葉っぱのフレディが、夏、人々に涼し気な木陰をもたらし、美しく紅葉する。しかし、やがて厳しい寒さを連れて冬がやってくる。葉っぱたちは一枚一枚、別世界へと旅だつ。親友のダニエルがひと足先に散っていった。別世界へ行くとは死ぬこと? フレディは独りだけ枝に残っていたが初雪の降った明け方、迎えに来た風にのって舞い落ちる。地面に落ちてはじめて、自分が今まで存在していた木の姿全体を見る機会を得た。ああ、この木なら、こんなにたくましい木なら、永遠にでも生き続けるだろう。やがて次の春へ向けて、“いのち”は受け継がれていく。 |
| 2000/05/05-9813 |
| 海の上のピアニスト |
アレッサンドロ・バリッコ
草皆伸子 訳 |
白水社 |
1999年11月15日第1刷発行 |
毒毒度:-5
|
“人の目の中を覗けば、その人が見たものではなく、これから見るものが見えるんだ、って言ってました。これから見るものが見えるんだ、って”
“よく言っていましたよ。「何かいい話を心の片隅にもっているかぎり、そして、それを語る相手がいるかぎり、人生まだまだ捨てたもんじゃない」かれはもっていた…いい話を。かれの存在そのものが、いい話だっだ。今思うと、突拍子もない、でもほんとうに素晴らしい話…そして、あの日、ダイナマイトの上に座ったかれは、それをわたしに残してくれた。”
陸地を果てなく旅して最後に現れる海を発見するのと、洋上からアメリカ大陸をはじめて見るのと、どちらが幸せな人生か。こんなにも大きな世界に直面してもなお、われわれのちっぽけな人生は生きるに値するか。本は読んでいても、まだまだ人間を読むことに熟達していない、まっすぐ海をめざし夜を走り抜けてから1週間が経つ。舞台は海の上。映画の原作は、戯曲として書かれたものである。ダニー・ブードマン・T・D・レモン・ノヴェチェント。新世紀の最初の年、ヴァージニアン号の一等船客用のダンス室にあるグランドピアノの上に置き去りにされていた赤ん坊。ダニー・ブードマンが、T・D・レモンの箱に入っているかれをみつけ、1900年の900(ノヴェチェント)が加えられて完璧な名前になった。ノヴェチェントは8歳になったある日突然ピアノを弾きはじめる。抑えが利いているときはジャズを弾くが、抑えがきかなくなるとこの世のものではない音楽を弾く。青年となり、一度も船を下りず、街を歩いたわけでもないのに、人々の体に書いてある場所、匂い、人生を読むことで、世界中を旅している。全米一というジャズピアニストから売られた喧嘩(ピアノ対決)にけりをつけ、32歳の時にはじめてタラップを下りようと試みるが、待ち受ける世界のあまりの大きさに動転し、逆戻りしてしまう。戦争中、病院船に使用されたヴァージニアン号は老化し、いまやダイナマイトで爆破される運命。ノヴェチェントは独りダイナマイトの箱に腰掛け、船とともに生涯を終えようとする。 |
| 2000/05/03-9814 |
メール・グリーティング
封筒で贈る小物集 |
中島祥子 |
文化出版局 |
1993年1月31日第1刷発行 |
再 毒毒度:-3
|
| “抑制のきいたエスプリで、ほんのひととき、微笑をとり交わせるような、つまりメール・グリーティングを贈り合えるような素敵な関係を多くの人ともちたいもの”
今、この時代にメールといえば、ほとんどの人がEメールのことと思っている。私はEメールをもらうのも出すのも好きだが、実はアナログのメールも好きだ。確かに文面とか苦労するにしても、封筒や便せんを選ぶ楽しさがあるからだ。この本は、単なる手紙ではなく、贈られる側に負担のかからないプレゼントの仕方を教えてくれる。例えば旅の贈り物コインや写真、可愛い切手などをカードに仕立て、封筒に入れて贈る。季節を感じさせる--言葉のない花びらだけのメール・グリーティング。乾燥させた木の葉に油性ペンで手紙を書く。言葉で遊ぶ--逆さ文字で書く等々。書かれていることはアナログの世界であるが、例えばホームページ作りのヒントになることも得られる。センスアップのコツともいうべきもの--色を控えめにするとか、レイアウト、文字のバランスなどの部分である。センスがないから…とよく言いわけする人がいるが、センスは生まれながらのものではない。その気になればセンスアップは必ずできる。 |
| 2000/05/02-9815 |
| 黒い薔薇 |
フィリップ・マーゴリン
田口俊樹 訳 |
ハヤカワ文庫NV |
1998年5月15日発行 |
毒毒度:3
|
“自分がこれからすることがどのような結果をもたらそうと、それには耐えられる。が、今ここでレイクをみすみす見逃すような真似をしてしまったら、それにはいつか耐えられなくなるだろう”
“誰にも--人殺しにも麻薬の密売人にも誰にも公正な裁判を受ける権利がある。それはあなたの台詞じゃなかった? わたしには受け入れにくいことよ、相手が女性であろうと誰であろうと、あんなひどいことをした人間にもそんな権利があるなんてことは。そんな人間には唾を吐きかけてやりたい。でも、あなたはその人間を守るんじゃないんでしょ? いつもあなたはそう言っているじゃないの。被告ではなく、すばらしい制度を守ってるんだって”
“ほんとうのけだものは、いつもけだものの顔をしているとはかぎらない。一度檻を出てしまえば、もう誰にもわからない。”
Gone, But Not Forgotten(去れど、忘れられず)…失踪した女性たちの枕元には、この紙片が残されていた、さらに、黒く塗られた薔薇も。オレゴン州ポートランドで起きている連続女性失踪事件。いずれも社会で成功している人物の妻たち。現場に争った跡がない。まったく同じ事件が10年前のニューヨーク州ハンターズポイントで起きていたことがわかる。当時の捜査チームに所属していた女性刑事ナンシーからの情報だった。彼女の話によると、犯人の名はピーター・レイク。レイクはローズ・キラーに妻子を殺された被害者だったが、有力者のコネを使い捜査陣に加わったあげく、自分に容疑がかかるや、別の人物に罪をきせることまでやってのけた。そのレイクがポートランドで再び殺人を犯しているのだろうか。レイクは名を変え新しい人生を歩んでいる、有力実業家ダイアラスとして…。辣腕弁護士ベッツィ・タンネンバウムは、事件発覚直前に、ダイアラスから破格の報酬で弁護を依頼された。家庭内暴力に悩む妻たちを幾度も助けてきたベッツィは、真実を知るために調査を開始する。結果は実に忌まわしくショッキングなものであった。
1990年代、翻訳サイコものが大量出版されると同時に、流行の終焉を迎えたころの一冊。ハードカヴァーで出版され、最近になるまで、文庫版が出たとは知らなかった。連続殺人、異常心理、リーガル物という、売れる要素満載。「感じのよい人物が、実は異常人格者である」パターンではあるが、異常の度合いといい、展開といい、読者のイマジネーションの一歩先を行く、そしてどんでん返し。「『羊たちの沈黙』をディズニーランドにしてしまう」という賛辞が贈られたらしく、うーん、そこまではどうかなと思うが、乗り換えのホームででも続きを読みたいと思わせる魅力は否定できない。犯人がハンターズポイントの女性達にした行為は、コリン・ウィルソンによる実録もので言うと1987年に発覚したハイドニクの「セックス奴隷」事件がモデルか。強引・怒とうのストーリー展開は初期型クーンツか。
|
 |
(c) atelier millet 2000-2002
contact: millet@hi-ho.ne.jp