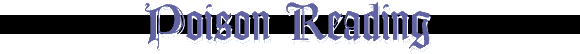 ●あと10000冊の読書(毒読日記) ※再は再読の意 毒毒度(10が最高)
民主政体を十分に機能させるのに、民主主義者である必要はない。きっぱり言われて目を覚ます。そう、はっきり言ってしまえば一番の理想は、抜群のバランス感覚に恵まれた品格ある独裁者の統治か(ただし、このような人物は稀である)。昼は久しぶりに独りで「樹の花」へ出かけ、古人に思いを馳せたのだった。かくして美しく悲しい5月が終わる。 そして、ローマ人は、法律へと向かった。人間の行動原則の正し手を法律に求めたのである。ちなみにユダヤ人は宗教に求め、ギリシア人は哲学に求めた。待望の文庫化開始! 昼休みに収穫したのだが、K造社のレジにいた年配のご婦人は、「文庫になって良かったですねぇ」と言いながらカバーをかけてくれた。ええ、ほんとに! ニューヨーク。ボーンと呼ばれるホームレス。なぜか大腿骨を携えている。目下のところ連続殺人の容疑者だが、記憶喪失のかれには、その容疑を晴らせる見込がない…。EQMM90年代ベストミステリー『夜汽車はバビロンへ』収録のチェスブロ作「名もなき墓」に惚れたのが2000年10月。この長編は読みやすい。連続殺人犯が早々にわかってしまうが、凡庸なヒロインを除いて、記憶喪失の主人公、脇キャラはなかなか魅力的。サイコ流行りの90年代初頭に翻訳が発行された当時、社会派というレッテルに邪魔され、作品の質は高いのに売れてはいないようだ。 父親は上院議員、自身も優秀な警部が、惨殺死体で発見された、手足を縛られ、肛門には未だ動いているバイブレータが突っ込まれていた。市長の特命を受けたポール・デヴリン警視の捜査線上に、国連の秘密クラブの存在が浮かび上がる…。アメリカ探偵作家クラブ賞受賞作なのだが、真犯人はすぐわかるし、目新しさがあるわけではない。実はサイコもの全盛期に第1作『殺しの儀式』を読んでいるのだが、あの時の連続殺人を解決したのがポール・デヴリンという名だったとは、解説を読むまで気がつかなかった。そういえば、容疑者と捜査側が事件の渦中でデキてしまうパターンが第1作にもあったが。 このあたりで誰かに考えてもらおう…というわけでひと昔(今は5年か)前の評論を選ぶ。エルロイ言及部分に興味があったのはもちろんだが、ダン・シモンズ『殺戮のチェス・ゲーム』にかなりのページが割かれていて思わぬ収穫。D・リンジー作品に正当な評価を下している点も、信用できそう。 この2週間ほど、C市内にある古本屋にしばしば出入りができ、収穫を重ねている。BOOK-OFFのように削ってピカピカではないが、2階の隅で発掘したウィリアム・モリスの例もあり、私にとって掘り出し物がある処という認識。エドナ・ブキャナンの『マイアミ犯罪白書』と野崎六助『アメリカン・ミステリの時代』で迷って後者を選んでレジを済ませ外に出たところで、山際淳司の名前を発見。出版は1991年だが、懐かしい80年代後半の香りがするクリスマス・イブ・オムニバス。山際淳司・安西水丸・秋元康らがアメリカあるいはニューヨークのクリスマスを書き、安珠が鷲尾いさ子を撮り、電通のCD杉山恒太郎がいかにもな世界を展開し、松本伊代が少女の夢を書き、高見恭子が彷徨う都会の女を書く。あのころの雑誌は12月になるとこんなカンジの特集を組んだものだった。 吸血鬼とゾンビが出演するマカロニ・ウエスタン「エルーリアの修道女」(キング『暗黒の塔』)や、発掘中の神殿での殺人事件を教皇ヴァレンタインがポアロよろしく名推理する「第七の神殿」(シルヴァーバーグ『マジプール』)、最後に悪がとっちめられる水戸黄門的な「笑う男」(カード『アルヴィン・メイカー』)、大量殺人の真相は?という真冬の夜の小話「薪運びの少年」(フィースト『リフトウォー・サーガ』)を収録。 恋人の名はシルヴァー。銀色の肌に赤褐色の髪。悲劇は、かれがあまりに人間に近しい存在だったことだ。驚くべきことに、かれは魂を持っていたのだから…。アンドロイドが出てくるのでSFとされているタニス・リーの傑作ラブ・ロマンス。 伝承ものの常として、凄いことがあまりに淡々と書かれていたり、巡り巡るしつこさがあったり、結構悪魔がマヌケだったりして笑えるんである。 女性記者ブリット・モンテーロ・シリーズ第2作。過去に罪を逃れた容疑者が次々と事故死する事件を追いつつ、マイアミのキャリアウーマンを恐怖に陥れるレイプ犯との邂逅…マイアミの夏は相変わらず波乱にとんでいる。慌てて礼服を買った日、閉店直前の古本屋にて、巡り合った本。とりあえず今日から仕事に戻った、とりあえず規則正しい生活をしてみることとする。で、本なんだな、おまえは。 とするとイギリス流「直截」だったのか、あの性格は。そして豊かな人生だったと思う。 不謹慎。母の通夜に、ひとり、棺の側で読むとは。よりにもよって、こんな本とは。ムルソーのごとく私は非難されるに違いない。なにかを見るにつけなにかを思い出す。頭の中は思い出の渦である。母は5月13日朝、急性循環不全で亡くなった。たしかにパーキンソンという病ではあったけれども、いまは予期せぬ死。私たちは長期療養を覚悟こそすれ、見舞客の風邪が院内にまん延したのを発端に母が死に至るとは想像していなかった。私がこの2ヵ月ほど風邪をひき面会を遠慮していたのが今となっては悔やまれる。会話をほとんどしていない。本人はこの半年ほど覚悟をしていて、棺に入れる着物にも注文があったようだが、まともにとりあわずにいた。あの着物で良かったのかどうか、果して…。 12年ぶりに再会する妹リサをむかえに行ったジェニー。ジェニーの住むスノーフィールドで、二人の生活がはじまるのだ。が、戻ってみると町は死んでいた。惨殺された死体が次々発見される。500人もの住民が一度に殺されたのだろうか? 太古からの敵の来襲なのだろうか? 文人は、色に奔るか食に奔るか。550ページ余。参考文献700余冊、完成まで実に5年。ものの見事に濃い。翻訳物の3倍時間をかけて毒了。久々大ヒットの毒である。最近でいえば『エンディミオン』に匹敵するポイントの高さである。ピーナツ食べて亡くなった漱石、饅頭の茶漬け!を好んだ鴎外、病魔に侵されてもなお過食症の子規、粗食淫乱の藤村、食魔岡本かの子、イメージをくつがえすほどとんでもない乱暴もの中也…食にこだわる文人たち、その生と死はどんなホラーにもまさるインパクトである。当時のゴシップも豊富で、それだけ読んでも十分面白い。 世界一非力なヒロイン、エリーズ。前回の事件を綴った小説のおかげで、今や人気者。介護人のイヴェットと共にリゾートへ出かけ、雪に閉ざされた山荘で、再び事件に巻き込まれる。偏執狂的なファンが、血のしたたるステーキ肉を贈ってきたのだ。イヴェットと夕餉にしたエリーズだったが、実はそれは人肉だった?! テロに巻き込まれ、恋人を失い、自身も全身麻痺となったエリーズ。話すことも見ることもできない彼女はある日ヴィルジニーという少女と知り合う。ヴィルジニーはエリーズに幼い男の子を殺す「森の死神」の話をはじめた。驚くべきことにその話は事実であり、やがてエリーズは事件へと巻き込まれていく。しかしエリーズにはなすすべがないのだった…。 シリーズ第2作。実は第1作は未毒。だが時代的には遡っての話であるという。滅亡へと至った大導寺一族。その呪われた歴史にも名の残らない人物がいた。その名は大導寺笙子。青渓女学院に通っていた彼女は、大輪の薔薇のような同級生、向後摩由璃に秘かな恋心を抱いていた…。恋は成就されたかに見えたが、笙子の心も身体も越えてはならない処へと導かれていく。やがて惨劇が。 ファム・ファタル。夫の命を盗むヴァンパイア女、肖像画に恋した男を手玉にとるビッチ…。読まずにはいられないタイトルで迫るジョイス・キャロル・オーツ、変幻自在のエリック・ヴァン・ラストベーダー(毎度ながら名前がコワイ)をはじめとして読ませる作家がずらり。買いである。解説で気になるのはエド・マクベインの別名でリチャード・マシスンと書かれているのだけれど、ホントか?? 確かに生年は同じなんだけれど。 4月の毒書数は、北海道巡業のある9月を除くと、今までで最低だったのではあるまいか。マキャモン『マイン』とストラウブ『ココ』をやっつけたので濃度的にはまあまあとは思うのだが。 大評判らしい。クラフト・エヴィング商會といえば「もの」とお話づくり専門と思っていたが、なんと今回の主人公は人間である。そして一風変わった職業の人たち…月光密売人からチョッキ食堂、シチュ−当番まで18人。聞いたこともない職業なのに、インタビューのような文章とリアルな写真によってわれわれはだまされる。あ、海辺の〈チョッキ食堂〉でチョッキを選んでごはんを食べたい。夏の間一生懸命働いて冬眠して好きな本を読みながら、〈冬眠図書館〉の司書の作るシチューが食べられたらなあ。もちろんチョッキのメニューやシチュー回数券などお得意のモノづくりも絶好調で、この素敵なファンタジーを盛り上げるのだった。ううむ、正体がわかってもホントにないかな〈冬眠図書館〉。それとも作っちゃうかな〈冬眠図書館〉。 データダウンロードの合間に、ページを繰る。突然ひらける非日常。実はGWの狭間に2泊3日会社の旅進行中。私は朝一回着替えに帰ったからまだまし、視界の隅には3泊4日検版の旅になりそうな人数名。GW初日の来客もてなしに、久々テラスでブランチなぞしたせいか、ちょっとハウススタイリング寄りの本選び。ふだんはわき役のトレーたちの写真&エッセイ。わき役・外伝好きの私にはぴったり? 毎日の食事だからこそのひと工夫。出会いたいと思う、自分で手がかりをつかんでアンテナを張る、足を使って自分の目でしっかり見る…気に入ったモノさがしのヒケツも大変参考になりましたとさ。というのも今、隠れ家に似合う電話器捜索中。キンキンピカピカは合わないのでね、どっちかというと昔の黒電話なんかいいかも。さて著者はJ大仏語出身の料理スタイリスト。写真も撮るし、イラストも描く。ちなみに、貝谷郁子というイタリア料理スタイリストもJ大だった。 (c) atelier millet 2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||