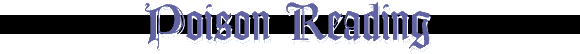| 2003/05/26-9057 |
| 天涯2 水は囁き 月は眠る |
沢木耕太郎 |
集英社文庫 |
2001年5月25日第1刷 |
再 毒毒度:3
|
“旅は素晴らしく、同時に無惨なものである”
“猫は旅行を好まない、ただ自由を好む。 ジャン・グルニエ『孤島』(井上究一郎訳)”
旅に出た。金曜の夜に発ち、土曜の朝、大阪に着く。日曜は京都は美山町にてロードレース観戦。土曜をどう過ごすか。ここ数年どうしても行きたかったのは鳴門。故・神吉敬三先生の「エル・グレコ祭壇画衝立復元」を見たい。これはもしかしてチャンスなのではないか。大阪→鳴門は高速バスで約2時間、朝10時現地到着を目指せば4〜5時間、大塚国際美術館で過ごすことができる。周辺観光一切ナシも潔くてよいだろう。というわけで梅田発8時ちょうどの高速バス乗車。予約ナシの飛び込みゆえ、席は最前列。他愛無く居眠りに突入、目が覚めたら大鳴門橋にさしかかるところ。なんと明石海峡大橋も淡路島も見過ごすことに! 驚いたことに、停留所「鳴門公園口」はうず潮の真上であった。下車したのは私と親子連れの2組のみ。もちろん美術館目指して歩いたのは私ひとり。インフォメーションでは約10分で美術館1Fのエントランスに着けるはずだったが、結構なハイキングコースで、睡眠不足の身体にはツライ。無表情な自動券売機に迎えられたが、中には生身のおねーさんがいて館内全体の説明をしてくれた。エレベーターで地下3階へおりると、いきなり17メートルもの吹き抜けでシスティーナ・ホールが出現する。順序では2番目が「エル・グレコ祭壇画衝立復元」があった。しばし佇み、この復元の完成を見ることなく亡くなった神吉先生の講議に思いをはせる。戦火で散逸した幻の祭壇画は、先生の6点説(別に7点説もあるという)に従って約200年ぶりによみがえった。黄金色に輝く衝立部分はイタリアへ発注、たしか衝立だけで1億円かかっているはず。この美術館の凄いところは、1074点中本物の絵画は一切なく、すべて陶板で「原寸大」に再現されていること、「環境展示」という手法で遺跡や教会の壁画を空間ごと再現していることなのだ。もちろん大きな作品には陶板の継ぎ目があるのだが、巧みなライティングが成せるわざか、それほど気にならない。絵の選び方もマニアックではなく程よくポピュラーで、一般客を飽きさせない。タイプのマドンナ探し(やっぱりラファエッロだな)もできるし、ウルビーノのストゥディオーロ(書斎)を埋める肖像画でイイ男ウォッチングもよいだろう。だが1074点はべらぼうな量である。順序通りロスなく進んでも地下3階のワンフロアだけで1時間、とてもそのまま地下2階を攻める力はなく、ラウンジ(カフェ・ド・ジベルニー)へ待避、チャージののち見学を再開したほど。ルネサンス〜バロック〜ゴヤの家までは真面目に見たが、近代〜現代は惰性。トータル4時間半。これで世界各国の25ほどの美術館を巡ったことになるらしい。これ全部本物だったら、作品の持つエネルギーに圧倒されとても生きては外に出られなかったのではあるまいか。おそるべし、大塚国際美術館。 |
 |
| 2003/05/22-9058 |
天涯
第一 鳥は舞い 光は流れ |
沢木耕太郎 |
スイッチ・パブリッシング |
1997年10月20日第1刷発行 |
毒毒度:4
|
“さて、どこに行こう。
しかし、どこと決めた瞬間に無限の自由は失われてしまう。それが惜しいために、行く先を決めず、机の前で無為な時を過ごす。無為な時にして至福の時。だが、私は知っている。やがて、その至福の時にも倦むようになるだろうということを。”
今現在私は、自由である。4月7日に突然、所属していた組織が消滅してからというもの、自由なのである。1ヵ月以上経った今では、潮時だったかと思う。直属の上司とは先にやめるのも先にやめられるのもツライ現場だった。あのまま突き進んでいれば死者が出たと言っても過言ではない。今は晴耕雨読というわけでもないが、平日に筍を掘ったり躑躅の剪定をしたりもできる。時折ハローワークに行き、時々人材銀行のプログラムに参加する。組織に属していないということは自由なのだが、世間的には不自由とも言えるかも知れない。通勤電車というものに乗らなくなったので、ご覧の通り毒書量は激減した。かつスローリーディングである。
“私は旅をする”という書き出しではじまるこの単行本の方を、今回さるBOOK-OFFにて600円で購入した。もとは3200円と、お高め。やはり大きいと写真の雰囲気が違う、というわけで並べて読んでみる。マカオの、ピンクのパラソルや空の色は文庫の方が鮮やかなのだが、はてどちらが本物に近いのか。 |
| 2003/05/22-9059 |
| 天涯1 鳥は舞い 光は流れ |
沢木耕太郎 |
集英社文庫 |
2001年1月25日第1刷 |
再 毒毒度:3
|
| “だが、私はまだ出発していない。汽車にも乗らず、飛行機にも乗らず、船にも乗らず、ただ机の前に座っている。出発していない私には無限の自由がある”
旅に出ようと思う。 |
| 2003/05/21-9060 |
| 東京珍景録 |
林 望 |
新潮文庫 |
1999年6月1日発行
1999年6月20日2刷 |
毒毒度:1
|
| “ここはむろん水道局の敷地で、一般の人は入ることが出来ない。にもかかわらず、ここにこうして謎のように、珍しくも妖しい美景が隠匿されている。思うにこれらは、それがそこにあることに、あまりにも慣れ切ってしまっているために、却って見落としている「時代のダンディズム」である。「珍景」とはまさにこの消息をいうのである。”(水道塔のダンディズム)
珍景といえば路上観察学会の面々の東京風景を思い起こすが、これはリンボウ先生による東京珍景集。むろん文章は美しい、ちょっと美しすぎるくらいだ。時折、「見よ!」と叫ばれるのが少々うざったい気がするが。写真は残念ながら先生ではなく他の人が撮ったものの方が美しい。 |
| 2003/05/19-9061 |
| 初球はストレート--荒木大輔物語 |
木村幸治 |
潮出版社 |
1993年7月7日発行 |
毒毒度:-2
|
“賑やかで統一のとれていないそのどよめきには、球場全体を一瞬のうちに包みこんだ、ある種のぬくもりがあった。ヤクルトを応援する客ばかりか、敵対する広島のファンの群れからも、歓迎の叫びや拍手が送られた。
荒木大輔が、小走りにマウンドへ走ってゆく。”
1992年9月24日、神宮球場のマウンドに一人の投手が上がる。実に4年と80日ぶりのマウンド。たった6球だけの投球だったが、9連敗という試練を越えて栄冠を勝ち取るチームの救世主となった。
次に見た時は日本シリーズ第2戦。清原にホームランを浴び、結局その一発で敗戦投手となる。その姿はあまりにも凛々しかった。
弱小球団スワローズが一気に花開いた1992年。日本一にこそならなかったが、実は私はこのシーズンが一番好きである。上を目指す者の、挑戦者の輝きがあった。その1992年ペナントレース終盤、奇跡のように復活した荒木大輔。以前、一軍で投げないのにコマーシャル・フィルムで笑顔を見せていた彼に魅力は感じなかった。ヤクルト・スワローズという球団にドラフト1位で入った選手はろくなことにならないというジンクス。荒木大輔もあのままいけばそのラインに乗ってしまっただろう。なぜ復活できたのか。きれいなマウンドに立つという信念、家族愛か。荒木への愛情先行でややキレイすぎる気もするし、例の白い蝶の話はラストを占めるエピソードとしては疑問ではあるが。 |
| 2003/05/15-9062 |
| サイゴンの昼下がり |
写真・文 横木安良夫 |
新潮社 |
1999年1月25日発行
2001年4月25日2刷 |
毒毒度:3
|
| “理屈でなく、五感のセンサーをフル動員して、回りを見回す。陽の昇る時間、沈む時間、光の方角、順光、逆光、サイド光、トップ光、フット光、水面の輝き、木々の蔭。雲の流れ。”
表紙が魅力的。アオザイと、それを着るヴェトナム女性の美しさ。風に舞う布、歩みにつられて粋にめくり上がり、露になるショーツのライン。ちらっと見える脇腹の生の肌。
いいかげん、望遠でポートレエトを撮るのはやめろよ、ともう一人の自分が言う。そう、安全な世界から、他人事のように覗いて、近寄ることなく、写真を撮っていいのかと責めるのだ。 |
| 2003/05/11-9063 |
| エレクトリック・ミスト |
ジェイムズ・リー・バーク
大久保 寛 訳 |
角川文庫 |
1997年9月25日初版発行 |
毒毒度:1
|
| 最近発見した古本屋にて収穫。ロビショーものはこれでおあと一作を残すのみ。でも実はどーでもよくなってしまった。やばいぞ管理人、今年の5月病はちといつもと違う。そうこうするうちに法事ツアーが迫るし。 |
| 2003/05/10-9064 |
| 秘密のクッキング |
マドモアゼルいくこ |
21世紀ブックス |
1979年12月10日初版発行 |
再 毒毒度:-2
|
| その昔母親が買ったこの一風変わった料理本は、何度見ているかわからないほどボロボロになりかけている。久々、「じゃがいもきんぴら」と「カレースパゲティサラダ風」「ごく日本的なサラダ」のレシピをのぞいてみた。特徴はヘルシーな野菜メニューが多いこと、早くできること、簡単なこと。あたりまえといえばあたりまえだが、出来上がりの立派な写真がなくとも、料理というのは出来るもんである。 |
| 2003/05/04-9065 |
| エスニック料理 |
財団法人ベターホーム協会 編集 |
ベターホーム出版局 |
1993年4月1日初版発行 |
再再 毒毒度:2
|
| 人見知りのたぁちゃんとちゃきちゃき美人妻ちゃこちゃん到来、恒例たけのこ狩&くいしん坊バンザイをこなして帰って行った。「きっとおかずが何かあると思って、おにぎり持ってきたんです」という判断は、うん、正しい。深夜だったが筍姿焼き&ポテチー焼き(ゆでて粗くつぶしたじゃがいもにいためベーコン&たまねぎを混ぜ、耐熱皿に入れ、卵&ミルクを回しかけ、チーズとバジルをのせて180℃〜200℃のオーブンにて30分、むろん筍姿焼きと同時進行)など出し、あまりの好評ぶりに翌朝もたまねぎパイという焼き物料理オンパレード。結局4食食べたが、特に喜ばれたのは、●ゆでたけのこをいためてめんつゆをじゅっとかけ卵回しかけ、●二十日大根の葉をごま油でいため酒とめんつゆで煮たつくだ煮風と、●ピーマンピリ辛味噌いため、●ベーコンしょうゆなど、ごはんがすすむおかずだった。 |
| 2003/05/03-9066 |
マイ・ラスト・ソング
あなたは最後に何を聴きたいか |
久世 光彦 |
文春文庫 |
1998年4月10日第1刷 |
再 毒毒度:4
|
“いまでも、あのうねるようなイントロを聴くと、沢田の酷薄な美貌が薄闇の中から浮かび上がってくる。恐ろしく投げやりなくせに少女の肌みたいに傷つきやすく、女に何も期待していないのに顔だけは花がほころぶように微笑っていて、だけど目だけは決して微笑っていない--そんな甘い毒薬のような男になれるのは沢田だけだった。「時の過ぎゆくままに」は、どこまでも堕ちていく人間の、気が遠くあるようあ悦楽の歌なのである。”(時の過ぎゆくままに)
“この人の「影を慕いて」は絶品だった。凄絶というか、妖異というか、あるいは静かな狂乱というか、とにかく聴いているうちに死にたくなるのである” (影を慕いて)
忘れられない歌を突然きく。と書いたのは中島みゆきだったか。続を読んだら還りたくなった。感傷である。BGMに古井戸を選んで読んだ。ここに書かれている人たちの人生と死に思いをはせて。歌。唄。詩。詠。 |
| 2003/05/02-9067 |
| みんな夢の中 続マイ・ラスト・ソング |
久世光彦 |
文春文庫 |
2003年4月10日第1刷 |
毒毒度:3
|
“あなたがたった一つ書いた歌を、いったいどれくらいの人たちが忘れられないでいるだろう。いまでも恋しているだろう。あなたがいなくても、70年安保はあっただろうが、もしあなたが書いた歌がなかったら、あの奇妙な安保前夜はなかっただろう”(唐獅子牡丹)
“忘れられない歌というものは、いつも自分の中の恥と、どこかで関わっている”(喫茶店の片隅で)
“輪の中心の森繁さんは、ほぼ百人のスタッフ、キャスト一人一人の手を取り、一人一人の目を見つめて、「月の砂漠」を歌った。私は、あんな異様な光景を後にも先にも見たことがない。全員、それこそ一人残らず、滂沱と涙流したのである”(月の砂漠)
“ラスト・ソングを選ぶということは、自分の人生をどんな気持ちで終わるかということである”(あとがき)
人を泣かすのが大好きな森繁久彌。そして自分が泣くのはもっと好きな森繁久彌。森繁の歌には人の世の空しさがあるという。それを色気といいかえてみる。泣かされた『マイ・ラスト・ソング』の続編。前回は美空ひばりが口ずさむ「さくらの唄」に泣き、今回は森繁の「月の砂漠」に泣く。
久世自身も毎回泣いている。泣くことを隠さない。この人は今最も色気のある文章を書く一人だと思う。簡潔な中に漂う色気を好ましく思う。感傷的であること。センチメンタル。私のラスト・ソングもかなり感傷的であることはたしかだ。 |
(c) atelier millet 2003
contact: millet@hi-ho.ne.jp