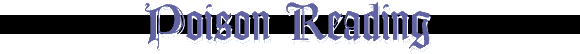| 2004/03/30-8892 |
| 三十過ぎたら楽しくなった! |
岸本葉子 |
講談社文庫 |
2000年10月15日第1刷発行 |
毒毒度:1
|
| “私にとっての三十代は、「好奇心事始め」なのだった”
海外通販、足もみエステ、食べ放題、アカスリ、快眠の追求。。。などなど今まで見向きもしなかったブームにも目を向けましょってことで岸本さんの体験手記だす。
本日は納品後、丸ビルのコンラン・ショップで、実家のリビングテーブルの品定めなど。目の保養にはなるが、お高いですな。 |
| 2004/03/26-8893 |
| アジア発、東へ西へ |
岸本葉子 |
講談社文庫 |
1998年5月15日第1刷発行 |
毒毒度:2
|
| “岩塩を砕き、バケツいっぱい詰めたのを、ざあっとばかりに引っくり返したような。ざくざくと、いくらでもスコップですくえそうなほど。夜空の黒より、星の白の方がおびただしい。とにかく、どの方角に向かってでもいい、立って、肩の高さに右手を上げ、左手を上げたら、その間全部、星なのだ”(「草原の包で一泊…内モンゴルのごちそう」)
いかん、読む順番が狂っている。だがどうも毎日は電車に乗らないせいか、出かけるときに鞄を変えて読みかけの本を忘れたりしてしまうのである。 |
| 2004/03/22-8894 |
| 旅はお肌の曲り角 |
岸本葉子 |
講談社文庫 |
1999年6月15日第1刷発行 |
毒毒度:2
|
“赤いペンキで書かれた「女」という字も、書くそばから風に吹きちぎられたように、赤い点々が飛び散り、そこはかとないさい果て感が漂って、なかなかいい雰囲気であった。ドアなし仕切りなし。積もり積もった便が、寒さのせいか乾燥のせいか、かちんかちんに固まって、ほとんど石化し、穴から覗いている。さながら鍾乳洞のようである。”(「雄大! モンゴルの草原トイレ」)
“哀しいかな、運はばらつきがある。ある人がだいじょうぶだったからといって、自分もだいじょうぶという保証は、まったくない。するとやはり、ひとつひとつ「自分で選びとっていくほかはない」”(「バンコクの危険な誘惑」)
標高三千メートルのトイレ。ふむ。旅は自分探し、主体的な選択の連続とな。 |
| 2004/03/16-8895 |
| 家にいるのが何より好き |
岸本葉子 |
文春文庫 |
2002年3月10日第1刷 |
毒毒度:2
|
“それにしても、この検査をつつながくこなすには、かなりの運動神経が必要である”
“三十三歳の私がこうなのだから、七十や八十のおばあさんが、あの動きについていけるとは思えない。台の上で骨折した人も、ひとりくらいいるのではないか”(「人間ドックに行こう」)
岸本葉子まとめ借り中だというのに、追加借り。ご主人が購入した本を友人は先に読んでしまい、さらに私にまた貸ししているのであるが、これでよいのか。ご主人は気づいていない風だというのだが、はて。
ひとり旅でおなじみの岸本さん、30代の日本ひとり暮らしもの。ゴミの出し方や買っても着ない服問題、テレビドラマにはまる話などなど。引用箇所には爆。 |
| 2004/03/15-8896 |
| 肉体への憎しみ |
虫明亜呂無 玉木正之=編 |
ちくまブックス |
1996年10月24日第1刷発行 |
毒毒度:4
|
| “その間、選手はだれとも語らず、言葉のない肉体をとおして、自分と語り、自分で語るたのしみをおぼえ、そのたのしみの及ぶ範囲を伸縮する自分を意識して走りつづける。彼のたのしみを傷つける最大のものは、彼のあずかり知らぬたのしみが彼以外の人間によっても数多く体験されていると知らされることである。マラソンはレースであり、競技である。闘争である。だから、マラソンは宿命のように、自分以外の相手を徹底して傷つけることによって成りたっているスポーツだと言いかえてもよい”(「海の中道」)
奇しくも、Qちゃん落選の報。「走り去った後方には瓦礫の山しか残らないほどの暴力的な走り」と二宮清純が表現したあの走りはアテネでは見られないことになった。 |
| 2004/03/14-8897 |
| 寄り添って老後 |
沢村貞子 |
新潮社 |
1991年11月20日発行
1992年3月5日9刷 |
毒毒度:1
|
| “私はもの心ついたときから、どうしてもいやなことはしなかった。いつも、自分がしたい、と思うことだけをしてきた……と、いうことは、ずっと遊んでいた、のと同じことになる。なるほど--だから、後悔することもないし、なかなか面白い一生だった”(「遊ぶって、なに?」)
これも母の遺した一冊。朝ドラで「おていちゃん」が放映されたのち購入したと思われる。母はわが家の社会的な面一切を担当していた。彼女の本棚は朝ドラのヒロインものや、『サラダ記念日』などいわゆるベストセラーが多かった、つまり私の買う本をダブることはゼッタイないのであった。
沢村国太郎(著者の兄)の家紋・菱寒菊をあしらった装幀、これも安野光雅。 |
| 2004/03/13-8898 |
| 秘密のダイエットケーキ |
マドモアゼルいくこ |
21世紀ブックス |
1980年11月15日初版発行
1981年9月20日第22版発行 |
再 毒毒度:-3
|
| 《アーモンドショコラ》製作。生クリームは七分立てするし、卵は卵黄と卵白に分け、卵白は完全に泡立てるという、このシリーズの中ではかなり手の混んだ方ではないか。たいがい女性には評判いいが、男どもはどうもパンチに欠けるとかいいやがるのである。 |
| 2004/03/13-8899 |
| よい旅を、アジア |
岸本葉子 |
講談社文庫 |
1996年12月15日第1刷発行 |
毒毒度:2
|
| “何を見てもそれほど驚かなくなっていたけれど、船首の方の陽当たりのいい甲板に、保健体育の筋肉の図みたいにまっ赤な筋があらわになったまるごとのイヌが干してあったのにはおそれ入った”(「揚子江を下って考えた」)
『ふわっとブータン、こんにちは』と同じ作者の本をまとめ借り。ぐんぐん読めるアジアな旅もの。台湾青年に思いを寄せられたり、現地の新婚さんたちと共にツアーしたり。。。偶然今日の朝日新聞土曜版に岸本さん登場。その後虫垂ガンで闘病生活を送ったとのことで、驚いてしまった。今は材料を工夫したケーキなどを作ってストレスを発散させているという。 |
| 2004/03/03-8900 |
熱砂の放浪者
グイン・サーガ第93巻 |
栗本 薫 |
ハヤカワ文庫JA |
2004年2月15日発行 |
毒毒度:2
|
“何百年生きようが阿呆は阿呆だし、十歳でも聡明なものは聡明だ。なぜ、魔道師というやからは、せっかく学をおさめ、魔道を学び、聡明になるためにこそありとあらゆる修業をしながら、かんじんかなめのそのようなところがそのようにわかっておらんのかだな”
“もはや、おぬしは、中原にとっては文字通りの守護者、守護神であり、それこそヤヌスにも匹敵する偉大な存在なのだよ、グイン”
“すべての死の物語はたったひとつであり--それには、たったひとつの死でも、何百万のたったひとつの死が集まったものでも、すべて重さは等しいのだ”
ついにこの日が。アモンとともに古代機械によって転送されたグイン。着いた先はかのノスフェラス。グラチウスが連れとなり、ノスフェラスの、そしてグイン自らの謎を求める旅となった。しかし百戦錬磨の?魔道師、闇の司祭グラチウスをも、しょう気に満ちた《グル・ヌー》の中核へ入ることを躊躇わせるのだ。死してもなお《グル・ヌー》に魅せられる《北の賢者》ロカンドロスの導きにより、グインはついに夢で見た星船と対面する。銀色に輝く星船の秘密とは? さらにはアモンとの再対決が待ち受ける次号。
登場するのはグイン、グラチウス、ロカンドロスという小人数ゆえ、対話の中身が濃い。死と生、かなり哲学的な今号であった。これから一週間はひたすら仕事。 |
(c) atelier millet 2004
contact: millet@hi-ho.ne.jp