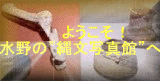
| 岐 | 阜 | 県 | 久 | 々 | 野 | 町 | の | 堂 | 之 | 上 | 遺 | 跡 |
|
堂之上遺跡は飛騨川上流、標高約700mの高地に位置し、昭和48年以降7次に亘る発掘調査の結果、縄文前期から中期を中心とした典型的集落が、約7,500㎡の小舌状台地にほぼ完全な状態で残されていた。 飛騨山中奥深くに残された数少ない本遺跡は、飛騨川を見下ろす台地上にあり、往時から今日まで地形の変化を殆ど受けずに集落跡の姿を留めており、学術上も重要な遺跡として認められ、昭和55年国の史跡に指定された。
出土遺物は多量の土器・土製品・石器・石製品・炭化物などが出土しており、地理上の中核的位置関係や出土した土器形態から東西日本・表裏日本との文化伝播・交流等複雑に交錯する地域的様相が明らかになったと云う。 |
 遺跡現場Ⅰ
遺跡現場Ⅰ
 遺跡現場Ⅱ
遺跡現場Ⅱ
|
本遺跡公園は資料館と共に昭和57年に完成した。 飛騨地方の縄文遺跡は標高500~800mの間に所在するが、本遺跡は700mほどの高地にあり、堂之上縄文人は厳寒期を乗り越える方法を知っていたと云える。 |
 以下文字列にポインタをおくと、クリ材を使った藁葺復元住居がご覧になれますよ! 以下文字列にポインタをおくと、クリ材を使った藁葺復元住居がご覧になれますよ!  |
|
住居址群の密集・重複が激しく、一時期に属する住居址を特定することが困難であった。 しかし台地南東部に存在する2棟の円形住居址と東部に存在する長方形住居址は重複することなく、時期的・構造的にも前期中葉・後葉・中期中葉と各時期の典型的構造を持つ住居として復元された。
方形住居は切妻風、円形は寄棟風の屋根を持っている。 |
 台地中央広場
台地中央広場
 配石土壙群
配石土壙群
 彫刻石棒
彫刻石棒
|
台地中央部の一帯は、約150箇所の土壙群が密集していたと云う。 土壙は大小様々で、深さも30cm~2mほどの掘り込みがあり、内部からは焼土・焼骨・木炭などが含まれているケースもあったと云う。 配石土壙は、立石を伴うモノ、平石が置かれているモノに分類されるが、その違いとは? これらの土壙群は住居群地域からは分けられ、食糧貯蔵用やお墓の用途に供せられたと考えられる。 飛騨地方の縄文中期には北陸・信州との文化交流が強く窺え、北陸地方に出土例が多い彫刻石棒の発掘はその一例と云える。
|
|
信州地方の影響が色濃い土器類、東日本・太平洋岸地方との交流を窺わせる各種アクセサリーなど高度に発達した生活文化を持っていたと云える。 又石棒及び陰石の出土例は、集落や子孫繁栄を願っていた証として間違いないと見られる。
内陸にあり険しい山々に囲まれた飛騨地方は、東西南北に通じる格好の地理条件を最大限活かし、 本遺跡には未発掘地域が残されており、現状牧草地として保存されていることから、将来の発掘チャンスに期待したい。 |
 特に縄文前期中葉から中期終末期までの長期間に亘る竪穴住居址が、中央広場の土壙群を取巻く形で43軒も良好な状態で発見されたが、岐阜県下では最大規模の集落跡と云われている。
特に縄文前期中葉から中期終末期までの長期間に亘る竪穴住居址が、中央広場の土壙群を取巻く形で43軒も良好な状態で発見されたが、岐阜県下では最大規模の集落跡と云われている。 密集・重複が激しい住居址群
密集・重複が激しい住居址群 独自の縄文文化を築いたと考えられる。
独自の縄文文化を築いたと考えられる。