![]()
●購入のキッカケ
単なる下駄代わりではなく、ノーマルのままで走行性能が高く、運転とメンテナンスの両方について、練習用になるもの。社外パーツも豊富にありそうなもの。ということで選択。個人的に2stミッション車(一応)に一度乗ってみたかったというのが大きいです。エンジンメンテが取っ付き易そうというのもありました。でも実際は時間的な理由から、車体以外は殆どいじっていない(改造じゃなくってメンテナンス)です。もっと時間が欲しい.......。
なおこのバイクは2003年12月、個人売買により引き取られていきました(輸送は業者さん)。大事にしてもらいなよ〜。
●インプレッション
ノーマルで購入し、エンジンオイル添加剤のスーパーゾイルを入れ、チェーンを交換しました(RK GP420MS)。アクセル開け始めのガツンとくる感じが減少。しばらくそのままで乗ってみたけれども、低回転はそれなり。7000回転あたりから力が出て、結構なスピードが出ます(メーター読みで約ぬわわKm)。ただ出足は遅いので(上手に半クラ使う技術がない)、もう少し楽に加速できる車種を、現在物色中。
なお現状がほぼノーマルなので、この状態でのインプレです。
| 長所 | 高回転での鋭い加速。9000回転あたりからぐんぐん加速します。 キック始動ですが、一発でかかります。冬場も楽勝。 意外なことに低速トルクも充分。カブ系エンジンと比べれば、倍くらいエンストしにくいと思う。低速でかなり粘ります。 剛性感がある(と僕は思う)ブレーキレバー。コントロールしやすいです。 原付にしては足回りがしっかりしていること。社外パーツも結構あります。 80なのでリミッターないですよ〜。 |
 |
| 短所 | 眠そうな低回転域。一応走るけど、6000回転以下は回っているだけ。 サイレンサーから多少オイルが飛び散ります。大きくアクセルを開けると、結構煙がすごい。 2スト独特の甲高い排気音。好きな人にとっては長所? 小さいため、足回りに泥汚れがつきやすい。あと段差の大きい歩道に乗り上げたりすると、アンダーカウル下部を擦ってしまう。 |
●改良点
塗装
| 購入時の外装が、自家塗装の黒で塗りたくったような悲惨な状態だったため、塗り替え。どうせ塗るならカッコ良い方がいいので、レプソルカラーにしました。 使った塗料は2種類。すべてスプレー缶です。 ・車体色の塗料 ・塗装の保護膜としての上塗り(クリア) 車体色の方は、エナメル塗料の白・青・赤・黄の4色を用意しました。ラッカーよりも若干乾燥が遅いですが、発色が良いのが長所です。 上塗りクリアの方は、デイトナから発売されているウレタンクリアにします。これは二液性塗料で、使用前にキャップを押し込んで混合し、一度に使い切るものです。一本¥2,500くらいと高価ですが、耐ガソリン性があるため、ガソリンタンクなどに使用しても安心です。 各種マーキングは、タミヤの1/12模型('98 NSR500 Doohan仕様)からデカールを拡大コピー。 当然そのままでは使えないので、車体に合わせてデフォルメを施し、型紙を作成します。具体的には長さをつめたりして、車体のずんぐりむっくりした雰囲気に合わせました。ゼッケンNoなどは半分くらいの切り詰めでちょうど良いです。 実際の作業は、色の切り替わり部分にマスキングテープを貼り、そこに型紙からマークを写し取ります。写し取った線の通りに、デザインナイフでマスキングテープを切り取ります。あとは他の部分を新聞紙等でカバーし、順次塗装しました。あまり細い部分は滲んでしまってうまくいかないようです。写真では実際には使用しなかったビバンダム君も写ってます。 注意する点は、新聞紙・広告等の一枚でカバーしたところに、塗料がべったりつかないようにしましょう。塗装面に記事が写ってしまいます(一度失敗済み)。そうしたところにはきちんと専用のマスキングテープを使いましょう。 あとウレタンクリアを吹き付ける前に、下塗りは十分乾燥させましょう。このように重ね塗りを繰り返したものは、一週間だと足りないかもしれません。結果、塗装後に一部が縮れてしまいました。 出来上がりは写真のとおり。遠目にはきれいです。近づくと.....微妙ですが、初回なのでまあよしとします。二度とはやらないけど。 |
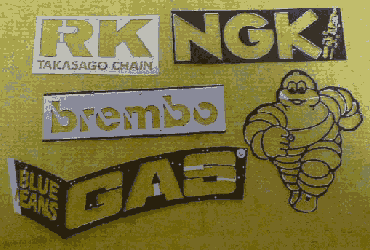 |
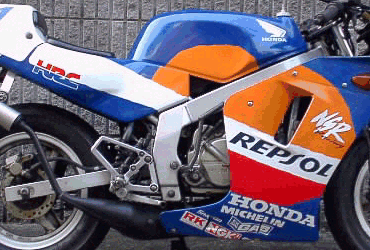 |
スクリーン作成
| 購入時に車体についていたものが、くすんで透明度がないため、新たに作り直しです。素材はホームセンターなどで購入しましょう。今回は、アクリサンデー㈱のサンデーPETで作ります。クリアのプラスチックって、割れやすいですが、これはペットボトルの素材の樹脂と同様のものなので、柔軟性があって割れにくいです。これなら大丈夫。 実際の作成は、まず型紙を作ります。素材には傷防止のためのクリアフィルムが貼り付けてありますので、そこに形を写し取り、切れ味の良いカッターなどで切り出します。カウルと現物あわせで穴あけをして、あとは熱湯につけて丸めてやれば完成です。90℃くらいで変形しますが、力を入れているとかなり急激に変形して、シワになってしまうため注意が必要。 装着すると、右のようになります。純正部品の3分の1以下のコストで製作でき、透明度もばっちりです。ここまでが原状回復作業というところでしょうか。 |
 |
イリジウムプラグ
 |
NGKのイリジウムプラグです。 デンソーのやつの方が良さそうですが、実売価格が安かったのでこちらにしました。 あんまり期待していなかった効果の程は.......。 低速がはっきりと力強くなります。もともとついていた標準プラグが消耗していたことを差し引いても、かなり違いがあります。 高回転域では、違いはわかりませんでした。あってもわずかだと思います。 点火系もチャンバーもフルノーマルなので、換えるともっと良くなるかもしれません。 車両を手放してしまっため、NSRでは確かめようもありませんが.......。 特にネガティブな面もないですし、明確な効果が現れるので、費用対効果は良いと思います。 折を見て、デンソーのイリジウムパワーも試してみたいと思っています。 |
|
| アーシング はやりのアーシングです。これは専用品があるわけではないので、自前でケーブルや端子を調達して、自作します。 ケーブルは家にあったオーディオ用(スピーカー)ケーブルを使用。OFC(無酸素銅)という純度の高い銅線を撚って1.5mmの線径にしたもので、効率が良さそうです。 端子は秋葉原の高架下の電子部品店で買いました。圧着用のペンチも忘れずに。丸端子の大きなもの(繋ぐ線が細いタイプ)は、8mmのものを購入(左側。右は10mm)。 圧着ペンチは、端子のつくりが、大まかに二種類(裸線を噛んで留めるだけのタイプと、線と皮膜部分の両方噛んで留めるタイプ)あるので、兼用タイプ(¥3,000)を購入しました。ただし、兼用のは留められる大きさが限られてくるので、余裕のある人は専用品をそれぞれ買うと良いでしょう。 値段はばら売りで、丸端子 ¥20、ギボシ端子 ¥10、ギボシカバー ¥10 で、100個入くらいのパッケージ(箱入)でまとめ買いすると、半額になるそうです。これに消費税がかかります。 バッテリーターミナルのマイナスに戻すので、二股になる端子と、そのカバーも用意します(こちらは¥20)。 今回は、シリンダーヘッドとバッテリーのマイナスを繋ぐ線を作りました。シリンダーヘッドボルト〜マイナス端子で約80cm。点火強化用ですね。市販のアーシングキットはオルタネーターやライトなどからも繋いでいるようですが、私の場合、夜間はコイツでは殆ど走らないのでライト強化は不要です。 効果の程は.....非常に良いです。もともと暗いライトも明るくなりました。アイドリングが若干上がり、一週間ほど乗らないと数回キックしないと始動しなかったのですが、一発始動するようになりました。明らかにエンジンも力強くなりました。コストパフォーマンスは最高です。 |
 必要部品と工具はこれだけ!  片方がバッテリーへ、もう一方が シリンダーへつながります。 なお、バッテリーへつながる側は、 写真右側の端子にするのが原則 です。カバーがすっぽり被さるので、 ショートを防止できるからです。 |
|
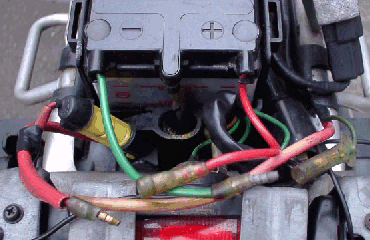 マイナス側(緑)配線を加工しますが、念のためプラス側(赤)も外します。 |
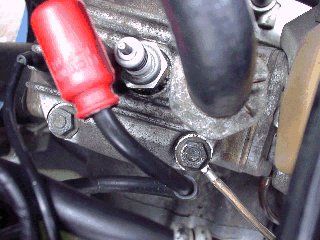 アース線をシリンダーヘッドナットで締め付けます。 |
|