ネット仕事術トップ < BACK | NEXT>:オープン性が人材を呼ぶ
 |
 Lesson Lesson |
9 | ネットが創る知の経済=ウィキノミクス ① ネットでつながる人材の諸島たち |


Q子 雑誌連載のウィキノミクスの回、よく分かんなかったですぅ。もしかして、整理しないまま掲載しちゃったんですか? B男 それに、ウィキノミクスって言葉、メジャーになってないスよね。 亭主 ぐ、ぐぅ・・・。 まあ、
少し詰め込みすぎだったかもな。 |
連載した同名の記事を大幅に加筆修正したものです。
 ウィキノミクスとWeb 2.0
ウィキノミクスとWeb 2.0
|
|
亭主 ウィキノミクスは、ウィキペディアでおなじみの「Wiki」とエコノミクスをくっ付けた造語で、2007年に出版された書籍「ウィキノミクス」で初めて紹介された。
この本は、書名のとおり、開発や生産など経済分野で始まったネットによる協働を解説しているのだが、発売と同時にビジネス界のみならず一般にも話題になった。その理由は、それまで曖昧模糊として捕らえどころのなかった「Web 2.0」を実務にどう適用するか、が提示されていたからなんじゃ。
Q子 ウィキノミクスとWeb 2.0って、どこがどう違うんですか?
亭主 まあ、視点の違いといえるかな。本の内容からは外れるが、重要なポイントだから図で比較してみよう。
Web 2.0の視点 |
ウィキノミクスの視点 |
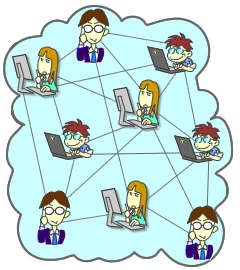 |
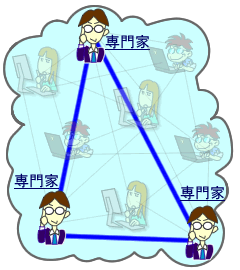 |
B男 あれぇ、Web 2.0の図から、単に「専門家」って人たちを抜き出しただけじゃないスか?
亭主 そのとおり。
まず、Web 2.0の方だが、図のようにネットで個人や小組織が情報発信能力を獲得した結果、
マスメディアや企業・行政による情報発信の独占が崩壊して、情報の流通経路の拡散とフラット化が進んだ状態じゃな。
しかし、「仕事」の面から考えてみてくれ。ネットが繋がったからといって、仕事を素人に相談したり、依頼する会社があるじゃろうか?
B男 まあ、ないでしょうね。
ネットがなかった時代 |

|
ネットが人材をつなぐ時代 |

|
亭主 いつの時代も、ビジネス(仕事)をダイナミックに進化させるのは、異業種も含め専門家たちの連携だ。
しかし、つい最近まで、専門家が「自分の知識や能力を生かせる場」を探したり、お互い同士が自由に交流したりするのは、大変なことだった。 組織やマスメディア、コネを媒介とする限り、広い範囲で個人的な接触を持つことは難しいんじゃ。
「専門家」を、研究者、技術者、法律家、クリエーター、自治体職員、企業、大学、NPO、などと読み替えてみると、よく分かるだろう。
上の図のようにネットがなかった時代、専門家たちは、音信不通の大海の中に点在しているようなもんだ。だから、ここでは彼らを「人材の諸島※」と呼ぶことにしよう。
※書籍「ウィキノミクス」では「備えある人材」と呼んでいる。
ところが、専門家たちを隔てていた壁を、ネットは一気に取っ払ってしまった。
つまり、ウィキノミクスの最大のポイントは、ネットの力で「人材の諸島」を直接結び、能力を活用することによって、新たな事業の展開や高度化が図れるということなんじゃ。
B男 だけど、そんなことは今までも、仕事の中でやってきたことっスよね。
Q子 そうか! ネット以前は、必要な人材を集めるにも、専門家側が自分が活躍できる場を見つけるにも時間と経費が掛かりすぎるんで、社内とか委託とか狭い範囲で妥協して、せこせこやるしかなかったってことですね。
亭主 そういうことじゃな。
それが、ネット検索やブログなどのツールがそろってからは、ほとんど無料で短期間に、広大な大海を越えて人材の諸島が結び合うことができる。
その効果を如実に示すのが、さまざまなオープンソースの成功だ。特にLinuxは、趣味で作ったOSを公開したところ、ネットの拡大と共に世界中の優秀なプログラマたちが寄ってたかって改良に参加してきた。今ではスーパーコンピュータや携帯電話に使われるほど、高い信頼性を獲得してしまったんじゃ。
B男 どうして、そんなに専門家が集まったんでしょうね?
ネットという羽を得て専門家 |
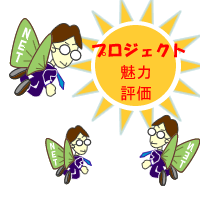
|
亭主 オープンソースの成功で認識された事実なんだが、専門家は金銭的な対価とは別のレベルで、興味が湧き、能力を評価してもらえるプロジェクトに自ら参加しようとする。ウィキノミクスの重要なポイントじゃ。
このような個人的な嗜好は、以前の経済活動では意識すらされていなかったが、ネットがそのパワーを集約した結果、ビジネスや仕事の進め方にに大きな影響を与えることが証明されたわけだ。
 ウィキノミクスは実践されているのか
ウィキノミクスは実践されているのか

Q子 Linuxが成功したのは分かったけど、プログラマやソフトウェアって、すごい特殊な世界ですよね。ウィキノミクスの仕事の進め方が一般の企業や行政にも効果があるとはいえないと思うんですけど・・・。
亭主 書籍「ウィキノミクス」では、LinuxやIBM、ウィキペディアなどのIT関連以外に、ボーイング、P&G、ロゴ、BMWなどの企業での成功事例も紹介されている。
これらの会社は、ネットだけを使ったわけではないんだが、その事業展開がウィキノミクスの仕事の進め方に沿っていたため、組織を超えた専門家を結集することができ、大きな成果を上げているという。ウィキノミクスの考え方が、ネット以外の場所でも適用されつつあるんじゃな。
本の副題の「マスコラボレーションによる開発・生産の世紀へ」とは、このような事業の進め方が一般化する未来を指しているんだ。
B男 うーん、具体的なイメージがわかないなぁ。 第一、自治体職員の仕事にどう関係してくるんですか?
亭主 それを説明する前に、まず、本の中で整理されている、ウィキノミクスの4つの基本原理を示しておこう。
|
[ ウィキノミクス・4つの基本原理 ] ① オープン性 : 参加の開放 ② ピアリング : 参加者同士の対等性 ③ 共有 : 知的所有権優位の抑制 ④ グローバルな行動 : 国境・組織を越えた共同作業 |
亭主 実は、ウィキノミクスという言葉ができるとっくの昔に、自治体はウィキノミクス流の仕事の進め方に直面しているんじゃよ。
次回からは、この4つの基本原理から、自治体職員にとってのウィキノミクスを考えてみよう。
B男 げっ、続くのかよ・・・
本シリーズの登場人物 |
||
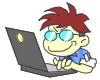 |
 |
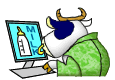 |
| B男 入庁7年目。不勉強を不遜な態度でごまかす名人。 |
Q子 入庁3年目。空気を読まない質問で場を凍りつかせる才女。 |
亭主 入庁xx年目。種族不明。 最近、忘却力がレベルアップしている。 |



 NEXT:オープン性が人材を呼ぶ
NEXT:オープン性が人材を呼ぶ