







[デジタル機器のお話し Vol.06, 2000年07月17日UP]
皆さん、「色」って何か知ってますか?。もちろん誰でも知ってると思いますが、「色彩学」などという学問もあるように、 ちゃんと勉強すると結構難しいもんなんです。まあ、ここでそれを始めたらとても書ききれるもんじゃないんで、 あくまでも「デジタル」の画像処理に役立つ「基本」の部分を書いてみようと思います。 (ちなみに、今回のHPは画像が多くなります。お使いのモニターを調整してご覧下さい。)
※今回は「色」の話しなので説明以外の「色」は全てグレーにしています。
・画像の基本
さて、「色の基本」を話すにも、ただ「色」について話してもさっぱり役に立たないですよね?。 (皆さんだって、何に使うのか分からない話しを延々聞かされても嫌でしょうし..) そこでまず画像についての基本的な話しをさせていただきます。「画像」というのは写真もイラストも全部入りますが、 それを構成する要素は下のように分かれます。
  |
これはいわゆる画像の「明るさ」のことです。ただし、これだけをいじって明るさを調整するのはやめましょう。 なぜなら濃度とコントラストは切り離せない関係なんです。 例えば、「Photoshop」では、「イメージ」の「色調補正」というメニューに、「明るさ・コントラスト」という1つの項目になっています。 また、印刷やプリントでは「濃度」という言葉を使いますが、モニターやプロジェクターのように光らせる場合は「明度」と言われることが多いです。 ちなみにこの「濃度(明度)」は色には関係ありませんが、鮮やかさに影響を与えます。 | |
  |
コントラストは英語だと「対比」という意味なんですが、画像で言うと「メリハリ」といったところでしょうか。 でも、写真にとっては「階調(トーン)」を左右する重要な項目です。きれいなトーンに仕上げるには上の濃度と同時にいじるため、 慣れないと結構苦労すると思います(最初は練習するならモノクロ画像にしてやりましょう)。 感覚的には「シャープネス」に効くためか、日本人や初心者は高くしすぎる傾向があります。 これは「色」には直接影響しませんが、色の見え方に効果を与えます。 | |
  |
これは色そのものの項目で、「あざやかさ」といえば誰でも分かりますね。でも、派手にすればいいというものではありません。(^_^;) 女性の化粧と同じで、全体は自然な感じにして「ポイント」を設けるのがコツです。具体的には、「濃度」と「コントラスト」 をきっちり合わせた後、自然な感じに全体の彩度を上げます。 もっと鮮やかにしたい場合は、ハイライト手前から中間濃度の彩度を「髪の毛のメッシュ」を入れるように、部分的に鮮やかにします。 間違ってもハイライトや中間濃度〜シャドウの彩度を上げるのはやめましょう。 | |
  |
皆さんが「色」という言葉を聞いて、真っ先に思い浮かべるのがこの「色相」ではないでしょうか?。 いわゆる「色味(いろみ)」とかいわれるものなんですが、世の中には「赤っぽい青」とか「空の青」なんてわけのわからない「色」が存在します。(^_^;) 手相のように「相」という文字がついているように、色は相関関係で出来ています。でも、占いのようにいい加減なものじゃなく、色には法則があるんです。 だから適当に色をいじっても、思った色や欲しい色は出て来ないんですよね。つまり今回のテーマなんですが、この法則を皆さんに知ってもらおうと思います。 |
・色の基本
|
色の法則というと難しく聞こえますが、右のグラフを見てください。これが法則です。つまり、色の関係ですね。
この図は上の画像の要素から「色相」だけを取り出したものです。(これに「明度」と「彩度」を加えると、
「色立体」という3Dグラフになるのが「色彩学」の話しです。)
ちょっとややこしいですが、これを憶えるだけで画像レタッチ(特に色補正)が非常にやりやすくなると思います。 右の図にはR,G,B,Y,M,Cという記号が並んでますが、 これはR(レッド:赤), G(グリーン:緑), B(ブルー:青), Y(イエロー:黄), M(マゼンタ:?), C(シアン:藍)の色を表しています。 それぞれがどんな色かは文字の書いてある「丸」を見ると分かりますが、ほとんどの皆さんがB,G,R,Yは知ってるんじゃないでしょうか?。 ところが「C:シアン」と「M:マゼンタ」は「色」を口にするときに余り使いませんよね?。 (実は、みんなが知ってると思ってる「赤・青・黄色」には落とし穴があります。この後で説明します) そして、ここは大切なところなんですが「六角形」で表しているように、色には「隣り合った色」と「反対の色」があります。 隣り合った色は「近い色」で、色を「修正する」ときに重要になり、「近似色」といいます。 これと同じに反対の色は全体を「補正」したり、「彩度を上げる」ときに重要になります。 そしてこの「反対の色」を色彩学では「補色」と呼びます。 | 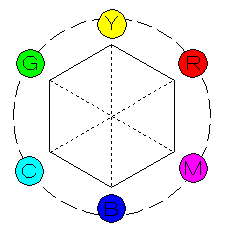 |
| 色にまつわる仕事をしていると、いろんな事を耳にします。例えば、食品関係は商品のパッケージに「Y−R」の範囲をメインに使います。 これは「食欲の沸く」色が食品の色と共通しているからだそうです。逆に清潔感を出す場合は「B−C」の範囲、なぜかメンソールは「G」だけだそうです。 ちなみに企業イメージをあらわす「コーポレイティッドカラー」ですが、興味のない人に印象づけるには「近似色」を避けるのがセオリーです。 でも、例外で成功した例には「Y−R」を使った「Kodak」や「Mc.Donaldo」がありますよね。(^_^) |
・色補正の実践
さて、本題ですが、これが分かると何に役立つんでしょうか?。それは色の「傾向」と補正のときの「方向」がわかるんですねぇ。(^_^) つまり、先程の「空の青」は「シアン」であり、「赤っぽい青」は「マゼンタに近いブルー」だということわかります。 この法則は「座標」になってますので、例えば「赤っぽい青」を「青」にしたいときは「マゼンタ」を減らすか、「シアン」を足せばいいわけです。 また、空の青を強調したければ、「シアン」を増やすか「レッド」を減らせばいいんですねぇ。実は簡単なことだったんです。(^_^)V
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
でも、実際に色補正をやろうとすると、そう簡単にはいきません。じゃあ、何が難しいんでしょう?。ここで上の写真を見てください。 この写真はそれぞれの色を強くかけて並べたものですが、下の色の記号をつけずに1枚だけいきなり見せられたら「何色に偏っている」かわかるでしょうか?。 おそらく、プロでお仕事をしている人でなければ、わからないですよね。つまり、何色に偏ってるかを「見極める」ことが難しいんです。 (実際の色補正ではこれほど極端な色じゃなく、もっと微妙な色を扱いますし、中間の色なども出てきて大変です。)
・色補正のコツ
では、具体的にどうすれば色について良くわかるようになるでしょうか?。これは場数を踏むしかありません。正直なところ「慣れ」なんです。 でも、それだけでは「役に立たないマニュアル本」や「画像合成くらいしか教えない雑誌」と変わらなくなってしまいますね(^_^;)。 ということで、今までおやじが教えてきたなかで感じた「コツ」をお教えしたいと思います。
| ビギナーの方を見て驚くのは、いきなり色を変えようとします。確かにいい時もありますが、その前に「明るさ」や「コントラスト」を調整しましょう。 順番で行くと「1.明るさ・コントラスト」「2.色相」「3.彩度」になります。また、そのために必要なこととして、 スキャナで画像を読む時は「コントラスト」と「彩度」を下げることです。ハイコントラストや派手な色は一見きれいですが、非常に補正しづらいデータになります。 デジカメの場合は、メーカーや機種によってかなり違いますので、後で補正しづらいような画像のものは避けた方がいいと思います..。 (ある雑誌で、実に補正しやすそうな Nikon D1 の画像を「眠い」とか「彩度が低い」とか書いてあったのには驚きました。) | |
| 皆さんからよく聞く「写真が青っぽい」ですが、「ブルーっぽい」と「シアンっぽい」が混同してるケースが多いです。
(上の写真の「B」を良く見てください。画像で言うところの「ブルー」は少し紫っぽい青になります)
そして、本当にブルーだったら補正色は「イエロー」です。
もしイエローを足して画像が黄緑っぽくなったらそれは「青っぽい」じゃなくて「シアンっぽい」色だったわけです。
その時は、色を元に戻して「レッド」を足しましょう。 #以前、おやじがプリントに「青っぽいね」と指摘したら、いきなり「レッド」を足した人がいました。(^_^;) その人いわく「青の反対は赤ですよね。」 (おやじ絶句..) | |
| 青と同じで、「写真が赤っぽい」という言葉も良く耳にします。そして「レッド」と「マゼンタ」が混同してるのも青っぽい写真と同じです。 (上の写真で良く見比べてください。一般的には、どうも「M」を「赤っぽい」色と思ってる人が多いように思います。) この場合も、レッドだったら補正色は「シアン」です。くれぐれも「ブルー」を足したりしないで下さいね(^_^;)。 「マゼンタ」の補正色も「グリーン」になりますから、赤っぽい写真の補正に「青」が出てくるわけはありません。 (一般の人はなじみが少ない色のせいか、自分の良く知っている「青」を使いたがるようです) ちなみに、写真で言うところの「マゼンタ」はピンクっぽい色で、「レッド」は焼けたような汚い色です。 | |
| 小学校低学年でやたら「赤・青・黄色」と教えるせいか、日本人の中には間違った「三原色」が身についてるのかもしれません。 「赤」や「青」の次は「写真が黄色い」といわれますが、ほとんどの方が「イエロー」と「グリーン」を使い分けてないようです。 (上の「G」と「Y」の写真を見て区別がつきますか?。もしつくようであれば、かなりの目の持ち主です。) おやじはビギナーから「写真がグリーンっぽい」と言われたことはほとんどありません。たいていの場合「黄色い」か「汚い」のどちらかです。 また、「赤と青」の場合と違い補正色が全く分からないのも困りものです。「イエロー」には「ブルー」、「グリーン」には「マゼンタ」で補正します。 |
・色補正の実例
さて、最後に今までおやじが相談された実例を用いて、「色補正」についてまとめたいと思います。
・「空が赤い」
電話で相談されて困ってしまいました。地球上で夕日でなければ空は「青い」ものです。もちろん夕日じゃないというので、
色々話したんですが、どうも空が「シアンブルー」から「ブルー」にいっちゃたようです。南国の海辺でモデルが写ってる写真には良くありがちなんですが、
顔を健康的にするつもりで「マゼンタ」を上げすぎると、空が「ブルー」になります。一般的には「ブルー」は「紫」に見えるらしく、それで「赤い」と言ってたそうです。
・「緑が汚い」
別に環境問題を相談されたわけじゃありません。風景写真の「森」や、料理の写真で使われる「野菜」なんかの「緑」が汚いそうです。
電話で話してると、何故汚いか分からなかったんですが、「新鮮さがない」という言葉でピンと来ました。グリーンは「イエロー」と「シアン」
で出来ています(G=Y+C)。この内、イエローが多くなると緑がしなびて見えます。逆に、シアンの多い「緑」は「新鮮さ」や「若葉」などのイメージになります。
多分、何らかの理由で「イエロー」に寄ったんでしょう。当然、「ブルーで補正してください」だったんですが、電話の相手は「?」だったようです。
・「ラーメンがまずそう」
いまだに分からないんですが、電話でこんな相談も来ました。「とんこつスープの色が白く出ない」とか、「北方醤油スープが透き通って見えない」など、
具体的に言われれば少しは想像できたかもしれないんですが、これには困りました。ただ「まずそう」としか言われなかったので、結局お手上げになったんですが、
ひょっとすると、それは「本当にまずそうなラーメン」だったのかもしれません..。(^_^;)
ところで、今回書いてみて思ったんですが、読み返すと「色」についてのほんの「さわり」しか書いてないんですねぇ。 色の話しが難しいのはわかってるんですが、「カラーバランス」の一部しか説明してないんですよ。 (このほかにも「階調バランス」や「グレーバランス」などがあります) ということで、さらにもう1つ「色の基本(銀塩感材版)」を追加して、今度は感材の突っ込んだ話も書いてみようと思っています。
色の話しが得意な‘おやじ’ですが、残念ながら「あっちの方」の色については苦手です..(^_^;)。では、今日はこの辺で..
※このコンテンツは全て2004年以前に書かれたもので、情報によっては現在と合わないこともあります。
※もし内容について確認したいことがあれば、「写真相談室」へご質問ください。