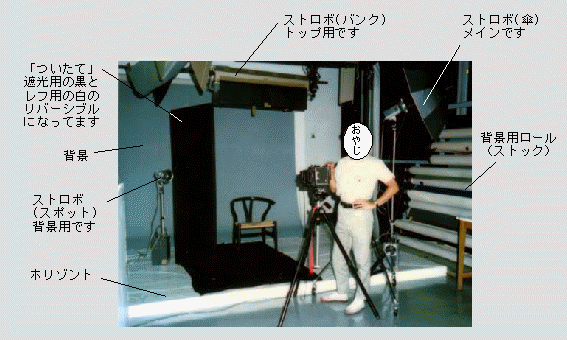スタジオのペテン師
【 商品写真の作り方について... Vol.07, 2002年12月01日UP 】
「ステージの魔術師」はお客に喜ばれますが、商品撮影の世界も良く似ています。
写真の発明家とされるダゲールも本業は「騙し絵」を描いており、何の変哲もない絵画が裏から光を当てた瞬間に変化するという見世物師でした。
これは裏にも絵を描いておくだけの「大道芸」的なもので、今の芸術や写真とは程遠い技法ですね。
ところが広告写真や商品撮影には、このような「騙す」要素も重要になってくるんです。
ということで、おやじが仕事をやっていた頃の「ペテン師」ぶりをお見せしましょう。
なお最初に断っておきますが、今回の写真と撮影法は「15年前」の仕事をしていた頃です。現役の人には「古い」と感じるかも知れませんが、
「基本」の部分はそれほど変わってないと思います。あと、おやじは本当のペテン師ではありませんので、勘違いしないように。(^_^;)
・スタジオという場所
 |
スタジオにも色々あって、撮るものや会社でぜんぜん違うものですね。
おやじが勤めたのは歴史のある企業のものだったので、最初に見た印象は設備が古かった(汚かった)です。
すぐに新築したスタジオに引っ越すことになったんですが、そこが「雑然とした場所」であることには変わらなかったですね(^_^;)。
左の写真の奥がスタジオになってるんですが、外から見て分かるように天井が高いです。普通の住宅の2階分はあるんじゃないでしょうか。
手前にあるのは小道具や照明で、発泡スチロールで作ったレフ板やディフューザーが置いてあります。
どれも高価なものではないですが、カメラマン達で工夫して作った大事な撮影道具です。
スタジオの天井にはレールが縦横に走り、照明装置やクレーンのようなものが設置してあります。
こう書くと設備のおかげでいい写真が撮れると思うかもしれませんが、答えは「NO」です。
設備が無くても何とかするのが本当のプロで、腕が悪ければどんな豪華スタジオでもいい写真は撮れないでしょう。
機材や設備にこだわらない...つまり、商品写真は撮る人のイメージと創意工夫です。 |
右がスタジオの中ですが、人物用の基本的なセットを組んでいます。
メインの傘がずいぶん遠いですが、これはモデルが座る前だからです。実際には、顔に出来る影を見ながら、
傘の位置を移動します。
トップライトのバンクボックスに黒紙が下がってるのは、トップライトが顔に入らないようにする工夫です。
背景用のストロボは、メインの明るさによってバランスを調整します。
なお、この時おやじは24歳なんですが、歳に似合わない服を着ています。
これは会社で決められた「作業服」で、おやじの趣味ではありません。(^_^;) |
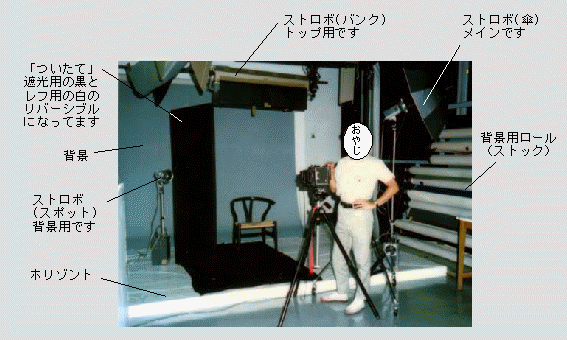 |
・カメラマンの服装
おやじは今でもそうなんですが、黒っぽい服しか着ません。今は単なる好みかもしれませんが、カメラマンは仕事上「黒」しか着れないことがあるからです。
もちろん、反射で服の色や光が被写体に当たるのを防ぐためですが、役者の偽カメラマンが派手な服着てるとびっくりします(^_^;)。
なお、友人にコンサートを撮ってる奴がいますが、機材のロゴにさえ黒テープを貼り、忍者のように全身黒ずくめです。
|
・ライティングの専門用語(1)
スタジオでの撮影には、色々と専門用語が出てきます。会社や個人で呼び方が多少違ったりしますが、もともと「俗称」なのでどうでもいいことかも..(^_^;)。
上に出てきた「傘」はアンブレラという拡散用の道具です。「ヘッド(大型ストロボの発光部)」に付けて使いますが、雨の日に差す傘とは違います。
(ちなみに、若きおやじは雨の日にアンブレラを差して寮に帰り、次の日に怒られました)
「バンク」は箱状の発光部で、中に「発光管」が直接入ってるヘッドです。発光部には乳白アクリルがはめ込んであり、巨大な発光面積で拡散光を作れます
(車を撮るときなどに使うバンクは、巨大なものと聞いてます)。「ボックス」と呼ばれる箱状の拡散道具もありますが、これはヘッドにつけるアクセサリーですね。
|
上のセットで撮ったのがこの写真です。モデルが掘りの深い外人さんだったので、基本的な「レンブラント」ライティングです。
左からレフ板で影を弱めてますが、基本的には右上からの傘をメインにした照明です。髪の毛が黒なので、
背景と分離するためにトップを使ったようです。背景は雲(もやもやとした模様)に変えて、
背景用ストロボのスポット(ハニカムグリッド)ははずしたようです。
今見ると両肩に当たった光がうるさいので、トップをスポットにした方が良かったみたいです。
でも、当時はモデルさんにポーズをつけたり、服を選ぶのに手一杯だったんでしょう(^_^;)。
どうでしょう?。この写真から、あんな汚いスタジオで撮ってるとは思わないのではないでしょうか。
落ち着いた雰囲気に見えますが、撮影は時間との戦いなので実はとてもあわただしい状況なんですよ。
クライアント(依頼者)は上がり(結果)しか見ませんが、このギャップが面白かったりします。
|
 |
・ライティングの専門用語(2)
「レンブラント」は説明するまでも無く、あの有名な画家のレンブラントのことです。彼のように肖像画を描くわけじゃなく、陰影のつけ方のことです。
顔の片側上方から光を当てて「鼻の影」を唇の端に流し、シャドウ側の眼の下に逆三角形のハイライトを作ります。彼の絵を見るとわかりますが、
人間の顔を一番「美しく」かつ「個性的」にみせるライティングといっていいでしょう。ただ、このライティングは欧米人にはいいんですが、
日本人の「鼻」ではうまく影が出ません(T_T)。そのため、あくまでも「基本」として「応用」することが大事です。
|
・ペテン師の魔法
さて、ここからいよいよ「商品撮影」のテクニックですが、当たり前ですが「いい写真」にしなければなりません。
つまり、綺麗なものは「きれいに見せる」ことが目的になります。まあ、簡単に言うと、それらしく見せるためには「手段は選ばない」ということです(^_^;)。
[作例1]
 |
まず最初は、液体やガラスを写す基本です。作例のように「透過」で撮るのがもっともきれいに見えます。
「これ」を見ればわかりますが、ライティングはシンプルでレフ板も使っていません。
説明だと簡単そうですが、「ガラス磨き」と「ホコリ対策」は結構大変だったりしますけどね(^_^;)。
背景のグラデーションをストロボの距離で調整し、グラスの輪郭が消えないように露出を決定します。そこへ色付きの液体を「きれいに写る」濃さに調整して入れます。
なお、チューブを使ってそっと入れないと、コップの内側に跳ねた水滴がつきます。
ちなみに、使っている液体は透明度のいい「染料」です。中には、市販のうがい薬やトイレの洗浄剤も入っています(^_^;)。
ワインの撮影もそうですが、まともに撮るとイメージより黒っぽく写っちゃうんですね。つまり「おいしそう」に見えない。
だからカメラマンは薄めて作った「赤い液体」で、偽りのワインを演出したりします。
※ビールのCMを見るとわかりますが、ジョッキは下や後から「光」を当てて透過光にしています。
|
[作例2]
 |
今度は上の応用になりますが、化粧ビンのようにラベルやフタがある場合です。こうなると、完全な透過ではシルエットになる部分が出てしまいます。
ということでストロボの位置を真下に移動し、床からのライティングに変えています。こんどはレフ板をかなり使うことになり、
「このような」セットになっています。
「作例1」と違い透過と反射のバランスは、レフ板の距離を変えて行います。また、床からの距離がそれほど取れないので、
ストロボとアクリル板の間に「黒紙」を入れ、穴の大きさを変えてグラデーションをつけています。
この作例はカメラアングルをやや上から撮っています。水色のビンのように真っ直ぐなものがあると、実際にはやや頭でっかちに写ります。
4×5であればちょっとアオリを入れるだけですが、ブローニーや35mmでは形の補正ができません。
商品撮影では4×5が必要ですね(^_^;)。
※これは練習なのでたくさん置いてますが、実際の仕事でこんなに並べるとピントが苦しくなります。
|
[作例3]
 |
商品撮影である限り、いろんな「商品」を撮らなければなりません。例えばスイミング用品なら、それに見合った場所が必要です。
でもプールを借りきってロケをすると、お金がかかりすぎますね(^_^;)。というわけで、ペテン師はスタジオにプールを作るわけです。
まあ、実際に作るわけではなく、プールサイドの雰囲気を出すだけですけどね。
ちなみに、この作例は小道具でたまたまあった「黒タイル」を使い、これをベニヤ板に並べて敷いただけです。
タイル職人が見たら、「目地」が打ってないのですぐに気づくと思います。
でも、水をたらして写真で見せると、周りが見えないのでシャワールームっぽく見えますよね(^_^;)。
ライティングは「こう」なっており、
典型的な「天トレ」です。技術的には難しくないですが、うまく水滴が落ちないと何度もタイルを磨くことになります。
この撮影は早かったんですが、長丁場にだと水が乾きます。そんな時は「グリセリン」を使って注射器でたらし、水滴の代わりにします。
このアングルだとトレペが写真に入りやすいので、先にカメラをセットしてからギリギリまで下げていきます。
床に並べた商品にピントを合わせるには、4×5でアオルのが一番楽です。もし35mmでやるなら最小絞りまで絞って、
露出に合うようにストロボの出力を上げるしかないでしょうね。
余談ですが、このフィルムはEPRです。
ハイライトからシャドウまで「色浮きが出ない」見事な階調バランスです。その上赤の発色に濁りがない。ポートレイトから商品撮影までこなせる、全く恐ろしいフィルムです。
日本のメーカーがお手本にするのがよくわかりますね(^_^;)。
※ちなみに「作例2」は某国産メーカーのリバーサルです。グラデの階調に青やマゼンタが浮き出てます。
|
[作例4]
 |
さて、物や場所の「ペテン」の次は、時間を偽ってみたいと思います。
おやじも出来ればフランソワ・ジレのように、
自然光スタジオでのんびりと仕事したいです。でも、現実の仕事が「短納期」であるため、実際の時間を待たずに写真を撮らないといけません。
そのためには、窓がない暗いスタジオで「時間のイメージ」を作り出すわけです。
この作例は「朝」のイメージで撮ってます。なぜ朝を感じるかというと、窓の光の方が明るいからです。
つまり、人間が「経験」的にそう感じるポイントを写真で表現するわけです。
この「窓」は撮影用の小道具で、枠の穴があいただけの「板」です。ガラスの代わりにトレペが貼ってあり、その向こうにストロボがあります。
セットを横から見ると「こう」なっていて、
レースのカーテンは窓枠にかけて押しピンで留めてるだけです。
なお、この写真には「決定的な間違い」があります。それは、置いてあるのが「シャンパン」と「クルミ」という点です。
絵作りで夢中だったおやじは、先輩に笑われるまで気づきませんでした(^_^;)。おやじは朝まで飲んだりすることもありますが、
普通の人は朝から酒を飲むことはありませんね。やっぱり置くなら「牛乳」「朝刊」「パン」でしょう。
※おやじが勤めたスタジオには、たくさんの「小道具」がありました。ここに写ってるのも、全部小道具です。
画面に入ってる「観葉植物」もそうで、枯れないよう毎日沢山の鉢を外に出すだけでも大変な作業でした。
このセットを応用して、ストロボをタングステンに変えれば「夕方」にできます。
もちろん、ただ置きかえるわけじゃなく、レフ板の位置や光量のバランスも変えないといけません。
商品撮影では「照明」を操ることが出来ないと、時間の演出も出来ないんです(^_^;)。
|
[作例5]
 |
さて、最後は「遊び」の写真ですが、現実には出来ないことをでっち上げる「ペテン」です(^_^;)。
広告写真にはいろんな要求が出てくるので、そんな写真は「撮れません」とは言えないんです。
今はデジタルで処理できるんでしょうが、当時はカメラマンの発想で色々撮ってました。これはそんな1枚で、飛び出す歯ブラシです(笑)。
被写体を針金やテグスで吊れば、実際に浮かせることは出来ます。でも写真にその影や糸が写りますし、透明な物体では目立ってしまいます。
じゃあストロボなので「せーの」で投げれば空中で止まると思うかもしれませんが、都合のいい位置に写るまで何百枚も撮ることになるでしょう。
というわけで「タネ明かし」ですが、
実に単純な目の錯覚を利用してます。
人間には経験から来る「思い込み」があって、写真で縦位置に見せると「上辺が上」と勝手に思います。
でも実際にどっちの向きから撮影しようが、それはどうでもいいんですね(円谷特撮方式)。
というわけでこの写真は90度回転させてあり、下から照明したアクリル板にコップと歯ブラシを横に寝かせて撮ったものです。
写真下部のテーブルのように見えているのは、アクリル板の上にトレペを置いたものです。
それらしく見せるために、台形に切りました。また、コップが浮かんで見えるように、黒い紙をアクリルの裏に貼って作ってます。
写真だと適度にボケるので、これを「コップの影だ」と思い込むんですね(^_^;)。
※観察力のいい人は、歯ブラシの影がないことに気づくでしょう。
これはあくまでも遊びでやってますが、意外と応用できるテクニックですね。カメラマンは暇な時には、こんな馬鹿げた発想で仕事の練習をしています。
|
・商品撮影というもの
さて、スタジオカメラマンの「ペテン師」ぶりがわかっていただけたでしょうか?。ある意味報道写真の正反対にあるものかもしれません。
というのは、報道は「事実」を曲げて伝えるわけもいかず、過剰な強調も出来ません(やってるマスコミもありますが..)。
それに対し、コマーシャルでは出来るだけ目的を良く伝える「演出」が必要になります。もちろん材質や機能を偽るわけにはいきませんが、
より魅力的に写す必要が出てきます。まあ、やり過ぎは問題かもしれませんが、写真だけで結婚相手を決める人はいませんし、
「お見合い写真」のようなものと捉えていただければいいかも..(^_^;)。
・商品撮影のノウハウ
おやじは大学を出てすぐにスタジオに入りました。企業の社内スタジオなので、一般のスタジオとは多少違う環境でした。
でも、学校のように商品撮影を一から教えてくれるようなスタジオは、多分何処にもないと思います。
つまり、アシスタントについて先輩のやり方を見たり、コマーシャル雑誌の写真を見ながら自分でセットを組んでみるしか学ぶ方法はありません。 |
店内に戻る
TOPに戻る