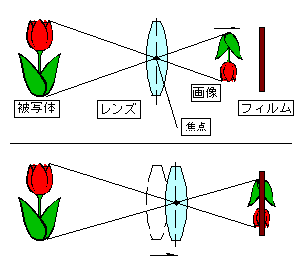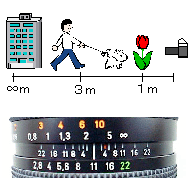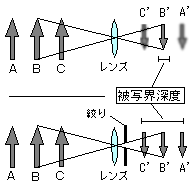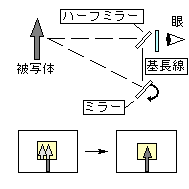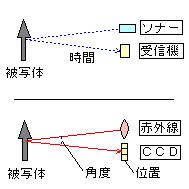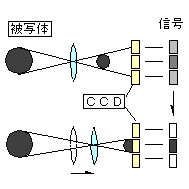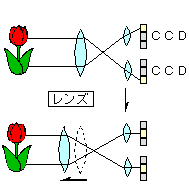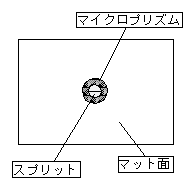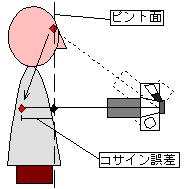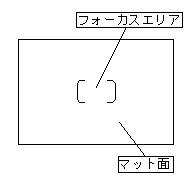ピントの合わせ方
[写真一般のお話し Vol.07, 2001年06月11日UP]
オートフォーカス(以下「AF」)が全盛の今に、こんな話をする必要があるのかという気もしますが、現実には悩んだりする人がいるわけです。
考えたんですが、おやじがピントで苦労したことないのはマニュアルフォーカス(以下「MF」)から触ってるからかもしれません。
実は一見万能なAFにも、苦手なものがあります。そして、その「苦手」を知ると、ピント合わせの「コツ」がわかるかもと思いました。
ということで、今回はたまたま「MFからAF」への変革期にカメラを使ってたおやじが、
ピント合わせの「歴史」と「仕組み」について書いてみようと思います。(^_^)
・「ピントを合わせる」って?
ピントを合わせるって、どう言うことでしょう?。まず、右の図を見てください。
広角でも望遠でも、撮影用のレンズは全て「凸(トツ)」レンズになります。このトツレンズは「焦点」を中心にして、
「上下逆にした画像」を反対側に作ります。これをフィルムに写し取るのが「写真」なんですが、
「画像」と「フィルム」を一致させないとぼやけた画像しか記録できません。そのためにレンズを「移動」させることを「ピントを合わせる」と呼んでます。
具体的なレンズの移動は、フィルムとの距離を変えればいいのでレンズを「前後」させます。でも、人間が手で前後させるとやりにくいので、
ネジをつけた「リングを回して」前後させるのが一般的です。こういう仕組みを「ヘリコイド」といいますが、微調整がしやすいので今でも主流になってます。
なお、一眼レフというのは、このフィルムのところに「擦りガラス」状のスクリーンを置いて覗いているようなものです。
(もちろん本物のカメラは「ミラー」で方向を変えているわけですが、原理は一緒です。)
つまり「ピント合わせ」とはこの画像(「結像」と呼びます)を目で見てるわけで、
はっきりしたり、ぼやけたりするのは、この画像が前に行ったり後に行ったりしてるわけです。
どうです、おわかりになりました?。(^_^) |
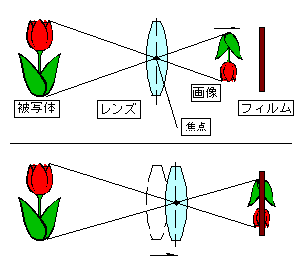 |
【ピント原始時代】
さて、ピントを合わせるということを説明しましたが、実際にカメラでやると難しいみたいですね。
おやじはスクリーンで合わせるのにもすぐ慣れましたが、目が悪かったりすると辛いみたいです。
ということで、もっと簡単に合わせる方法がないかとカメラメーカーがいろいろ模索しはじめました。
以下に、ピントの合わせ方の種類を歴史に沿って書いてみます。
・「目測」
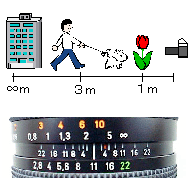 |
この方式は「目測式」と言って、きわめて原始的なものです。つまり、目で見て被写体まで「何m」かを推測するわけですね。
レンズには「距離目盛」や「距離マーク(山や人、花マークなど)」が付いていて、「うーん、大体3mくらいかなぁ」とかいって自分で回すわけです。(^_^;)
最近はあまり見ませんが、昔の安いコンパクトカメラはみんなこのタイプでしたね。35mmレンズだと15m以上は無限遠(∞)でいいので、
目測が「大体」でも結構実用になるわけです。また、スナップにも使える手段なので、レンジファインダーや一眼レフでやる人もいますね。
ただ、AFが一般になった今はあまり見かけませんし、意味がないかも知れません。
[おやじの一言]
ま、目測だけに自分の「距離感」を鍛えてください。それ以外やりようがありません。(^_^;) |
・「固定焦点」
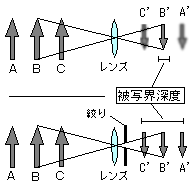 |
これも「固定焦点」と言って原始的なもので、焦点を「固定」しちゃう方式です。
「えっ!」と思う方もいるでしょうね。だって、固定しちゃったらピントが合わないわけですから(^_^;)。
これは「パンフォーカス」と言って、「被写界深度(ピントの合う範囲)」を利用しています。
つまり、広角レンズをある程度絞り込めば、被写界深度がほとんどの距離でピントをカバーしてくれるわけです。
この方式は安いデジカメやコンパクトで見かけますが、一番ポピュラーなのは「使い捨てカメラ」でしょう。
あれは高感度フィルムを使用することで、「F11」まで絞っても写せるようになりました。
広角レンズとあいまって、そこそこのピントを実現できます。
[おやじの一言]
動かすところがない以上、何も考えることはありません(^_^;)。 |
【ピント中世時代】
上の二つはピントを合わせようというやり方じゃないですね。あくまでも「使える」部分で利用してるだけです。
そのせいで、いくつかの「制約」があります。例えば、被写界深度が深い広角レンズはいいんですが、
望遠レンズだとピンぼけが多くなりますし、絞りもあまり開けられないです。
というわけで、距離を測る機械=「距離計」で合わせる方法が出てくるわけです。
・「二重像合致式」
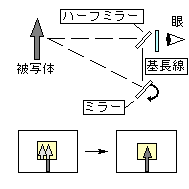 |
この距離計は割と古くからあったもので、「三角測距法」と言います。
昔数学で習ったはずですが、三角形の1辺(基長線)と角度から距離を出します。
二つの鏡で画像をファインダーに導く仕組みですが、ファインダーの真中が距離計の部分になります。
ピントを回すと連動したミラーも回るんですが、この時片方のハーフミラーに画像が重なります。
目で見てぴったり重なるとピントが合う仕組みです。
高級なレンジファインダーや中判カメラが使ってますが、AFのせいで減りましたね。
レンズの明るさに関係しないので、ファインダーも見やすくてピントを合わせやすい方式です。
基長線が短いと精度が落ちたり、望遠がやや苦手だったりもしますが、いい距離計には違いないですね。
余談ですが、世界初のAFカメラ「ジャスピンコニカ」は、この仕組みを使ってました。
人間「眼」の部分を「CCD」に置き換えた発想で、距離情報でレンズを動かしたわけです。
[おやじの一言]
実は「距離計」のデキがピントを大きく左右します。買う時によく選びましょう。(^_^) |
「ジャスピンコニカ」
コニカは世界初のカメラを沢山作ってますね。今のカメラなら当たり前ですが、ワインダー内蔵の一眼レフもコニカが初めてです。
他にも、コンパクトにストロボを内蔵させた「ピッカリコニカ」で大ヒットさせましたが、これも世界初でした。
そして、ピッカリコニカにAFを組み込んだのが「ジャスピンコニカ」だったんですが、
暗いとピントが合わないし、被写体によっては役に立たないAFはとても不満でした。
ただ、高価で基本性能も良くないカメラがそこそこ売れたので、「AFは売れる」と証明するには十分だったようです。(^_^;) |
・「アクティブ方式」
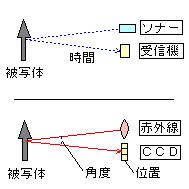 |
AFカメラを欲しがる初心者が多いことに気付いたメーカーは、こぞってAFの開発を始めます。
最初に登場したのはコニカに近いやり方で、CCDで光を受けて角度で測距する「パッシブ(受動)方式」でした。
ところが、暗いところや模様のない被写体にはAFが機能せず、カメラ側が「照射」して距離を測る「アクティブ(能動)方式」が出てきました。
左図の上が音波を発射して帰ってくるまでの時間で測距する「ソナー方式」です。そして、下は近赤外光を発射して角度を測る「赤外線方式」です。
ソナーはポラロイドがSX−70という機種で採用しましたが、構造が大きく電池を消耗するので普及しませんでした。
(音波が跳ね返る「ガラス越し」などでピントが合わないことも問題でした。)赤外線のAFは、キヤノンが「オートボーイ」という機種に採用し、
暗いところでもピントが合うと当時は大ヒットしました。今はほとんど見なくなりましたが、昔は主流になったこともあるAFです。
[おやじの一言]
今は採用されたカメラがほとんどないですね。昔は一眼レフ用のレンズもあったんですけどね。(^_^;) |
「アクティブAF」
一時期はアクティブAFしかピントが合わないと言われたことがあり、AFコンパクトではオートボーイが絶賛されていました。
でも、アクティブAFにも欠点があります。それは、照射する赤外線の「届く距離」までしか測れないことです。
つまり、せいぜい5mまでしか役に立たないわけで、広角の35mmレンズはいいですが、望遠やズームには対応できなかったんですね(^_^;)。
現在はCCDの性能も上がってますし、ストロボ時は補助光を使えばいいので、またパッシブ方式に戻っています。
(もちろん初期のようなミラーは使わず、ラインセンサーになったCCDなどで測ってるはずですが..) |
【ピント近世時代】
ここまで書いたピント合わせの方式は、どちらかというとコンパクトカメラで実用になったものです。
決まったレンズしか付けられず、ワイド系で記念写真用と条件を限定できるから実現した部分があります。
ただ、そうなると人の気持ちは贅沢なもので、「一眼レフもAFにしたい」といわれるようになりました。
ということで、80年代後半に入るとAF一眼レフへのアプローチが始まります。
・「コントラスト検知式」
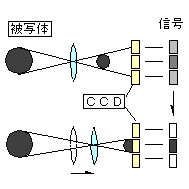 |
いろんなレンズを付ける一眼レフは、より正確な距離を測る必要があり、今までの方法で測るのは不可能でした。
そこで、直接レンズから「情報」を取り出す方式が考えられました。それがこのコントラスト検知方式です。
レンズから光を導いて、ボディに付けたCCDでコントラストを測るわけです。
画像がボケるとコントラストが下がるのを利用して、ピントを検出する方法です。
この方式で各メーカーからAF一眼の試作機が発表され、いくつかは高価ながら市販されました。
ところがほとんど実用にならず、全く売れませんでした。理由は、ピントが合うのがものすごくトロいんです。
この方式だと、ピントがずれた「方向」がわからず、レンズを前後させる必要があったんです。
結局手で合わせる方がずっと速く、一向に先の見えない時代でしたね。
[おやじの一言]
ところがこの時、1社だけが水面下でとんでもないAFカメラを準備していたんです。(^_^;) |
・「位相差検知式」
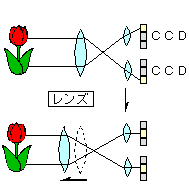 |
各社がAF開発に熱心だった時期に全く動かなかったミノルタが、突然AF一眼レフを発売しました。
方式は「位相差式」といって、ピントが「どれくらい」「どの方向に」ずれてるかを検知できるので、
レンズを動かす方向と移動量が一発で測れる優れものです。レンズから導いたスリット光を、
ラインセンサーのCCDを使って位相(ズレのベクトル)を検知したんです。
このカメラが発売後、全てのカメラメーカーが真似をしました。そして、現在はAF一眼の主流になったわけです。
でも、この方式でも万能ではなく、いくつか欠点はあります。暗いところで精度が落ちる点や、模様のない壁などは苦手です。
発売当初、プロは使いませんでしたが、それでも馬鹿売れするほど当時としてはピントが速かったんですね。
ベストセラーになった後、米国の某H社に特許で訴えられたのは最大の誤算だったでしょうけど..。(^_^;)
[おやじの一言]
以後、ミノルタはMFをやめたので、おやじはコンタックスを買うことになりました。(^_^;) |
「ミノルタα7000」
レンズやシステムまでを一気に発売したので、他社が追いつくのに2〜3年かかったほど先進的なカメラだったようです。
おやじはピントが合わないと切れないシャッターや家電品みたいなデザインが嫌いでしたが、ピントに苦労してた人には朗報だったでしょう。
AFの仕組みも画期的でしたが、いつまでもレンズが動くと「不安」を感じるからと、被写界深度内ならレンズが止まるなど工夫もあったようです。
もっとも、某家電メーカーがビデオ用AFの研究のために分解したそうですが、
「えっ、そんなすごいカメラだったの?」と答えたほど中味はありふれていたようですが..。(^_^;) |
さて、ここまで難しい話ばかり書いたんですが、少しはピントの合う仕組みがわかっていただけたでしょうか?。
別に詳しくなる必要ないんですが、距離計が「苦手」にしてるものが何となくわかっていただけたんじゃないでしょうか?。(^_^)
・距離計が苦手なもの
1.暗い
目で合わせる時でも、暗いだけでずいぶんやりにくいですよね?(^_^;)。AFだって「CCD」を使ってますが、暗いとこは苦手なんです。
MFなら明るいファインダーが頼りになりますが、AFは一般的には高いカメラの方が暗さに強いようです。
なお、この対策用にストロボから補助光が出るものもありますが、メーカーオプションの純正ストロボに限られますね。(^_^;)
2.低コントラスト
あまりない被写体かもしれませんが、「一面の白い壁」や「一面の白い雪」などは、どこにピントを合わせていいのかわからない時があります。
AFは特にこれが苦手で、染みや傷でもいいので「何か」ないことにはピントが合いません。最近はAFエリアも複数あったりしますが、
ピントが合わない場合はカメラを振って合うところを探した方がいいでしょう。
3.連続した模様
人間は混乱しないんですけど、シマシマとか水玉とか「連続した模様」があるとCCDが誤作動するようです。
特に、模様がCCDのライン方向と平行だとAFは機能しないので、最新のカメラでは縦横に複数のCCDを並べています。
事前にテストして、自分のカメラが苦手なものは知っておいた方がいいですね。(^_^)
4.速い
AFも進歩したんですが、あまり早く動くものには対応できなかったりします。といっても、プロスポーツのカメラマンでもなければ、
MFよりAFの方が速かったりします(^_^;)。一眼レフのAFなら、一般的な撮影では何の問題もないでしょう。
もしどうしても満足できないなら、MFでプロ並に鍛錬するか、プロ用のAFカメラを使いましょう(^_^;)。
・MF一眼レフの基本
もうやる必要ないのかも知りませんが、MF一眼レフのピント合わせのコツを書きます。
これを知っててもAF全盛の35mm判じゃ意味ないですが、大判や中判カメラのためにはいいですよ(^_^)。
おやじと同じ物好きな方はお試しください。
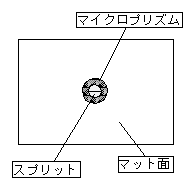 |
一般的なMFカメラのファインダーは左のようになっています。真中にあるのは「プリズム」式の距離計で、
中央が「スプリット(縦線が上下でズレる)」、その周囲が「マイクロプリズム(画像がチラチラする)」と呼ばれます。
その外側の「マット」部分は擦りガラス状になっていて、ピントのボケ具合がわかりやすくここで合わせるのが基本です。
ところが、大抵の人はまず真中のプリズムを使いますね(^_^;)。実はこのプリズムは設計するF値があらかじめ決まっていて、
だいたいF2.8になってます。この時プリズムが使えるのは、開放が「F1.4〜F5.6」までのレンズです。
プリズムは暗いズームなんかだと使えないしマットがあれば十分なので、プロは「全面マット」にしてる人が多いみたいです。
別に使わなきゃいいだけのことですが、ど真ん中にあって邪魔なんですよね。(^_^;) |
さて、具体的なコツですが、おやじの基本として「マット面」で合わせることをお奨めします。理由はいくつかありますが、
一番の利点は「ボケが確認できる」ことでしょう。そして、先に構図を決めてからピントを合わせます。
ピントリングの回し方は、初めは「大きく、すばやく」回し、行き過ぎたところでさっと逆に戻します。
これを2〜3往復させながら合わせるんですが、徐々に「小さく、ゆっくり」回すようにします。
ところで、普通はピントが合ったらシャッターを切るわけですが、中には先に合わせて構図を変える人がいます。
ピントを合わせてから構図を変えると、ピントがズレることがありますのでご注意を..。(^_^;)
「コサイン誤差」
細かい話かもしれませんが、コサイン誤差なるものがあります。これは、ピントを合わせた後でカメラの向きを変えると起きる現象なんですが、
ピントが甘くなるのでプロの中には結構気にする人もいるようです。
いつも出るわけじゃないんで無視してもいいと思いますが、被写体に近づいたときや広角レンズでは影響が大きいみたいです。
例えば、ポートレートは「目」にピント合わせるといいますが、右図のようにまずファインダーの真ん中でピントを合わせたとします。
(ピントが合った距離は目の「赤丸」の位置です。)
次に、このピントのままで構図を変えると、本来「黒丸」の位置にないといけないピントが奥にズレてしまいます。
これが数学の「コサイン」の関係から出る誤差で、「コサイン誤差」と呼ぶわけです。
まあ、構図を決めてからピントを合わせる癖をつければいいことですけどね。(^_^;) |
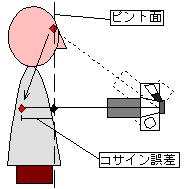 |
・AF一眼レフの基本
次はAF一眼レフですが、各メーカーや機種によって性能も使い方も違いますので、細かな話はお持ちの説明書で確認してください(^_^;)。
おやじも1台持ってますが、あんまり使わないので自信がないです。(確かに楽ですが、面白味にかけるんです..)
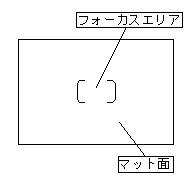 |
いまどきこんなシンプルなAFのファインダーはないと思いますが、共通して書けるところってこんなもんですよね(^_^;)。
実際にはいろんな「エリア」が表示されていて、露出やら距離やらを測るわけです。
でも、大まかに言うと「マット」のスクリーン部分と、AFが働く「測距エリア」に分かれます。
AFエリアは、昔は小さな「丸」や「線」だったんですが、最近は「でかい四角」や「巨大な六角形」だったりしますね。
理由は距離を測るCCDはライン状なので、1本だとピントが合わない方向があるからです。
そのため、カメラによっては複数のCCDを組み合わせるんですが、並べ方はさまざまで「十字型」や「H型」などがあります。
また、中には複数の測距エリアを持つカメラもあるようで、凝ったものになると見つめた部分のエリアでピントを測ってくれるようです。
ちなみに、測距用のエリアもプリズムを利用してピントを合わせるようになってます。
そのために設計されたF値があるのはMFとおんなじで、それによって使用できるレンズの開放F値の範囲があるそうです。
あまり暗いズームを付けると、AFでもピントに苦しむのはそのせいですね。(^_^;) |
さて、ここでおやじの持論なんですが、AFカメラは「AFで撮る」方がいいです。というのも、MFで使うとマットでピントが合わせ辛いからです。
カメラにもよるんでしょうが、一説にはAFのためにファインダーを明るくする必要があり、それで精度を下げてるとも言われています。
スクリーンのマットは明るくすると光が拡散しないため、ピントの「山」がはっきりしなくなるんです。
この説が嘘かほんとか知りませんが、使いにくいAFレンズを手で回すより、AFで割り切って使った方がストレスにならないです。(^_^;)
なお、具体的なコツはないです(^_^;)。というのも、カメラによって違うからで、皆さんがお持ちのカメラの「特徴」や「クセ」
を良く知ることが一番ですね。あえて挙げるとしたら、「AFロック(メーカーで呼び方が違う)」を使うことくらいです。
AFが思ったところにピントを合わせてくれなければ、合うところでロックをかけて構図を振るしかないです。
ただ、この時中央のエリアを使用すると、前述の「コサイン誤差」が出る時があるので注意してください。
−ピンぼけ写真−
おやじは思うんですが、「ピンぼけ」ってそんなに恥ずかしいでしょうか?(^_^;)。
まったく合ってなければ写真になりませんが、少しくらい外れてても別にいいと思います。
というのも、ピンぼけを怖がってシャッターを切らない方がもっと問題で、いつまで経っても写真が上達しないからです。
いい写真はピントが合ってた方が「もっといい」でしょうが、ピントが合ってるだけの写真では「いい写真」にはなりません。
初心者の特権で「ピントなんかいつか合うようになるさ」と考えて、堂々とピンぼけ写真を作ってみてはいかがでしょうか?。
シャッターチャンスを増やしていけば、たまたま合う時もありますから..。(^_^) |
店内に戻る
TOPに戻る