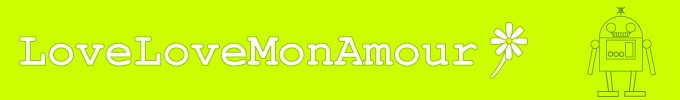
|
キミのフェロモン 後編
上空から見た都市の姿が映し出される。外国の都市だ。カメラは降下し、地上へ近づいていく。ビルに囲まれた交差点の上で降下が止まるのと同時に、交差点の上に黒い点が溢れてくる。カメラのアングルが切り替わり、交差点を行きかう人々の姿がいくつもの方向から映し出される。老若男女、様々な人が通り過ぎていく。 やがて信号が変わって人の流れが止まり、今度は車が走り始める。巨大なトレーラーが視界を埋め尽くしたところで、視点は再び上空へ戻った。そして地表に沿ってゆっくりと動き始める。 ビルの林を瞬く間に通り抜け、平屋建ての住宅地が広がり始める。 『自分の体重の四百倍のものを持ち上げ、』 男の渋い声の英語のナレーションと共に字幕が映し出される。 『千七百倍のものを引っ張り、』 『垂直の壁を登り、』 『時に空を舞う、』 画面は住宅地を通り過ぎ、農地を横切り、森林を超え、その速度を速めていくつもの街を駆け抜けていく。 やがて海の向こうに新たな大陸が姿を現す。 『女王とその子供達を守るために』 『針を持ち、酸を吐き』 『力をあわせて闘う』 カメラは熱帯雨林の中を走っていた。見慣れない形をした木々の間を縫っていく。 ふいにその動きが止まる。 熱帯雨林の中。風がないのか揺れる木々もなく、動くものは何も見えない。鳥の鳴く声すら聞こえない静かな世界。 時間が止まっているかのようだった。 静止している世界。 “自然”が溢れているはずなのに、それを感じさせない世界。 しばらくして小さな音が聞こえてきた。それは少しずつ大きくなっていく。 なにかが近づいてきている。 それに気がついた時、画面の一部が黒で塗りつぶされた。その黒はあっという間に画面いっぱいに広がって行き、多重に重なった不協音が大きくなる。 アリの大群だ。 場所はアマゾン、グンタイアリの大群が巨大なスクリーンを埋め尽くしていく。竹緒は見たことのないど迫力の画面に心を振るわせた。 近づいてきたグンタイアリの集団は画面の下半分を完全に黒で塗りつぶし、次々と通り過ぎていく。多分、カメラは上方に固定されているのだろう。そんなことを考えていると突然視界が揺れた。竹緒の視界がではなく、カメラの視界がだ。 小刻みに振動していた視界が突然横倒しになり、バウンドする。画面が荒れ、ノイズが走る。 カメラを固定していた三脚が倒されたのだと分かる。 しばらくして荒れていた画面が収まると、空が映し出されていた。うっそうとした森に囲まれた青い空。アリの軍団の音は続いていたが、それはあまりにも平和な光景に見えた。 そこに突然一匹のアリが現れ、カメラに向かってぐわっと口を開いた。 その瞬間、場内ではいくつもの小さな悲鳴が聞こえた。 ドキュメンタリー映画とは思えない、パニック映画なみの演出だ。 竹緒も少し驚き、身体を硬直させてしまった。 百音に見られなかっただろうか? そっと隣の席に目を向ける。隣からは悲鳴は聞こえてこなかったが、百音はあの手の演出に強いほうなのだろうか? 百音は首を垂れていた。最初は眠ってしまったのだろうかと思ったが、映画は始まってまだ五分も経っておらず、いくら興味のない内容だったとしても眠ってしまうには早過ぎる。 竹緒はスクリーンからの明かりを頼りにして、百音の顔を覗き込んだ。 学内一の美少女は白目をむき、泡を吹いて失神していた。 「どこまで覚えてる?」 「カメラが倒れて、空の中にアリが出てきたとこ」 「へぇ、頑張ったじゃない。私としてはその後の、antって文字が動いて、いっぱいのアリになるところの方が気持ち悪かったけど」 「止めてよ……」 ようやく起き上がった百音は、想像しただけで気持ちが悪くなったのか、口を押さた。 竹緒が失神した百音を場外に担ぎ出すと、南田と加賀見、それに草津も出てきてくれた。今は廊下のソファに寝かせて看病しているところだった。 「しっかし、五十鈴さんがアリが苦手だなんて知らなかったな」 南田がほっとした顔つきで言う。 「苦手なの、小さいのがいっぱい動いているのが。それに小さいくせにアップになったらすごいリアルでしょう。ああいうところも嫌い」 アリマニアの竹緒からしてみればアリの魅力を根底から否定された意見だったが、そんな風に感じる人が少なくないことも知っていたので、特に反論はなかった。しかし、それならば分からないことが一つある。 「だったら、なんでアリの映画なんか観に来たんだ?」 空気が凍るとはこういうことなのかと竹緒は実感した。 それをのんびりと実感していてはいけないのだということは、ひしひしと感じていた。 これが地雷を踏んだという奴だ。 そしてそれを体現するものとして、先ほどまで気分悪そうに横たわっていた百音が、怪しげなオーラを身にまといながらゆっくりと立ち上がった。 「今日という今日は絶対に許さない」 冷たい声が映画館のうすぐらい通路にひびく。 お団子にされていた髪がほどけて、ばさっと落ちる。 「ぎりぎりまで待つつもりだった。いいえ、ぎりぎりまで待ったわよ。私は十分に我慢した。でも、あんたは思い出さなかった。全部あんたが悪いんだからね」 百音がばっと顔を上げる。 今朝、待ち合わせ場所で見たかわいらしさなど、遥かかなたに消し飛んでいた。 目の前にいるのは般若であった。 竹緒は恐怖に震えながら必至に弁解する。 「考えた、考えました。でも分からなかったんだ。結局オレは何を思い出せばよかったんだ」 声が震え、足をがたがたと震わせながら交代する竹緒に、百音が吼えた。 「私に、結婚してって言ったことよ!」 衝撃の告白に、その場にいた全員が息を飲む。 「私がこの街から引っ越した日、あんたはわざわざやってきて、結婚してくれって言ったのよ。私はあんたのことなんかあんまり知らなかったけど、でもとても嬉しかったの。本気にしたの。えぇもうそりゃバカみたいだって分かってるわよ。友達にもさんざんバカにされたわ。子供の約束よ。案の定あんたは全く覚えていなかったし、子供の約束なんか信じているほうがバカだって言われたわ。でも私はずっとその言葉を信じてたの。パパが仕事に失敗して生活が苦しかったときも、その言葉を頼りに頑張ってきたの。パパの仕事が回復して、パパもママも嫌がったけど、私が説き伏せてこの町に帰ってきたのはあんたに会えるかもしれないって思ったからよ。まさか本当に会えるだなんて思ってなかったけど、でも、同じクラスになって、隣の席になったの。凄いじゃない。奇跡じゃない。なのになんであんたは全部忘れて、自分は関係ないって顔をしているのよ!」 百音は一気に怒鳴り散らした。のぞきこんできた係員を、南田がなだめに行く。 息も荒く、百音は睨みつけてくる。しかし、睨まれても竹緒の頭はパニくるばかりで記憶はちっとも呼び覚まされない。 百音に告白をした? いくら子供のときとはいえ、そんな重要なイベントを忘れているだろうか。 オレはそんなことを口走る子供だったのか? つーか、やっぱり子供の約束なんじゃないか。 しかし、憤怒の表情をした百音にそんな反論をするほどの勇気はない。 修羅場に似合わない、いつもどおりの落ちついた声で聞いたのは加賀見だった。 「五十鈴さん、この町から引っ越したのって何歳頃?」 「幼稚園の時よ」 「新井くんはずっとこの町に住んでいるの?」 「いや、小学校のときに転校してきたんだけど……」 「ふへぇ」 百音がマヌケな声を上げる。 「人違いね」 そして加賀見は冷酷に断を下す。 「え、でも、アライタケオだし、メガネかけてるし、チビだし……」 そんなにあっさりと長年の想いを潰されてなるものかというように百音は食い下がっていたが、新たな刺客として立ち上がったのは、幼稚園時代からの友人であるはずの草津だった。 「それって、もしかしてアラブ王のことなんじゃない」 「アラブ王?」 「あれ?知らないの?あのあだ名ができたのはももちゃんが引越した後だったかな?幼稚園の男の子でね、ある時期に女の子に結婚してくれって言いまくった子がいたの。クラスの女の子はみんな言われたんじゃないかな。私も言われたし。いつもあだ名で呼んでるから忘れてたけど、そいつの名前もアライタケオだったよ。確か、「アラ」は荒ぶるで、「タケ」」」」」」」は武器の「ブ」だったけど。女の子全員と結婚するって言い出したから、それじゃアラブの王様だって話になって、名前も「荒い武おー」でアラブ王って読めるから、そんなあだ名がつけられたの。あはは、ももちゃんもしっかり告白されていたんだね」 満足気に頷いている草津に、加賀見が尋ねる。 「そのアラブ王は今どこにいるの?」 「工業高校に通っているはず。昔はチビだったけど、すんごい太っちゃって貫禄があるから、今でもアラブ王って呼ばれているみたい」 「つまり?」 竹緒にもはっきりと状況が分かっていた。しかし、ここは冷静な加賀見にはっきりと結論を聞かせて欲しかった。 「壮大なる勘違いね」 加賀見は期待通りの仕事をしてくれた。 そして、百音は脱兎のごとく逃げ出した。 あっという間に姿を消した。 「ももちゃん」 草津がその後を追いかける。 「新井くんも追いかけて」 「え、でも……」 加賀見の言葉に竹緒は躊躇する。今までは百音が自分に興味を示す理由が分からなかったが、今ははっきりとしている。人違いをしていたからだ。今の百音には、竹緒にこだわる理由はどこにもないし、むしろ勘違いしていた恥ずかしさから、会いたくない気持ちが強いはずだ。 でも……、 「好きなんでしょ」 その声に押されるように竹緒は走り出した。映画館の外に飛び出したときには百音の姿も草津の姿も見えなかったが、迷うことなく走った。 走った先に百音はいる。それにはなんの根拠もなかったが、竹緒は本能にひかれるように、ただ走った。 ゴールデンウィーク初日の早朝、竹緒は駅で意外な人物に出会った。いつもなら意味深に現れるその相手も、今日この場所で竹緒に会うのは予想外だったらしく、驚いた顔を見せた。 しかしそれも一瞬のことで、すぐにいつもの笑みを顔に張り付かせた。 「おはよう、タケ。朝早くからこんなところでどうしたんだ」 「ちょっと用事があって。そっちこそどうしたんだ」 「デートだよ、デート」 「なんだ、新しい彼氏ができてたのか」 「妬けるか?」 「別に……」 「もしかして、」 陽雪は形相を崩す。 「百音に会いに行くのか?」 あいかわらず勘が利く。おかしな邪推をされても面倒なので、竹緒は正直に答える。 「そうだ」 「住所を知っているのか。タケもなかなかやるもんだな」 「教えないぞ」 「私を誰だと思っているんだ。教えてもらう必要はない」 さすがだなっと呆れる。百音の新しい住所はトップシークレットのはずなのに。 一週間前の日曜日。つまり映画の翌日。 五十鈴家は突然出奔した。 隣に住む澤井家が気づかなかったぐらいに見事な夜逃げであった。夜逃げとは言っても今回は父親の事業が失敗したのではなく、昔の人間関係がわずらわしくなって引っ越したらしい。それならば普通に引っ越せば良さそうなものだが、近所に引越しの挨拶をするのも面倒くさかったのだろう、というのが大筋の見方だった。竹緒は知らなかったが、裏ではかなりのごたごたがあったらしい。 月曜日、百音は登校しなかった。 「オレも詳しいことは知らないんだ」 担任の岩坂先生は頭をかきながら、家庭の事情、とだけ転校の理由を告げた。 新しい連絡先を知らされている生徒はいなかった。 様々な推測や噂がと飛び交った。 竹緒も問いただされたが、不機嫌そうに「なにも知らない」と告げると、すぐに引き下がってくれた。百音が竹緒に絡んでいたのは人違いだったという話はしっかりと広まってしまっていた。わざわざ傷を広げようとする心無いものはいなかったし、百音に関する情報源としての価値も下がっていた。
みんなの勘違いのおかげで、こうしてノーマークで百音に会いに行ける。 しかし、最後の最後でミスをした。パパラッチに偶然出会ってしまい、そしてその目をごまかせなかったようだ。 「そんなに警戒しなくてもばらしたりしない。そうだ、一つ頼まれてくれるか。私を友達だと思っているのなら一度連絡が欲しい、こう伝えておいてくれ」 「連絡先は知っているんだろ」 「タケは百音から直接聞いたんだろう?残念ながら私は正規のルートではないからな。でも、タケがちゃんと聞き出せていてくれて嬉しいよ」 「おかげさまで。分かった、伝えておく」 あの日、竹緒は映画館から逃げ出した百音を捕まえることができた。 そして、気がついたばかりの気持ちを正直にぶつけた。 その返答が、明日中に引っ越してしまうという決定事項と、新しい連絡先だった。 「まだ時間はあるか?最後に一つ、訊きたいことがあるんだけど」 竹緒の問いに陽雪は頷く。 「澤井さんは、なんでオレと付き合ったんだ?」 これから先、百音とどうなるのかなんて分からない。 確かに住所を教えてもらうことはできた。でもそれは付き合いが始まったって意味じゃない。スタートラインにつく権利を与えられただけだ。むしろこれまでの罪滅ぼしだとか、恥ずかしすぎて気が動転していただけなのかもしれない。 今日も会うことは了解してくれた。でも、会った先になにが待っているのかなんてまったく分からない。 少なくともこれまでの経緯を考えたうえで、バラ色の未来が待っていると期待するほど竹緒は楽観主義者ではない。 これからも頑張らなければならない。 その為にも、新たなスタートラインにきっちりつくためにも、この疑問は解決しておきたかった。 「こだわるんだな。分かった、話す。でも、聞いても怒るなよ」 そう言って陽雪は薄く笑った。 「私は人を好きになったことがないんだ。もちろん、親兄弟や友達に対する好きじゃなくて、恋をする好きだ。中学生にもなると好きな人ができてくるだろう。友達の話を聞いていて私はとても羨ましかった。私も人を好きになってみたくなった。でも、人を好きになるにはどうすればいいのか分からなかった。その時になって、その相手に出会えば、自然に好きになることができる。そんなことを聞かされても私は全然満足できなかった。人の恋愛話を聞きまくってすっかり耳年増になった。知識はどんどん増えたけれど、人が本当にそんな感情を持ち、そんな風に変わってしまうだなんて信じられなかった。だから高校に入学したら絶対に人を好きになろうと思った。色んな人と付き合って、好きになれる人を探そうと思った」 結論はともかくとして、竹緒にもうなずけない話ではない。 恋に恋するお年頃という奴だ。陽雪も普通の、年頃の女の子だったということだ。ついでに一つの疑問も解決する。 「それでタイプがバラバラなのか」 陽雪が高校に入学してから付き合った男は五人、見事にタイプがバラバラである。色んなタイプの人間と付き合うのが目的だったのだとすれば、実に分かりやすい。 「生理的に嫌いなタイプは外したけど。でも、誰も好きになることができなかった。一緒にいたりして楽しいと思うことはある。でもそれは友達と一緒にいるときの楽しいの延長線上にあるもので、私が知りたい「好き」って感情じゃなかった。残念ながらタケのことも好きになることはできなかったよ。良い友人でいて欲しいとは思うけどな」 「オレだって、澤井さんを好きにはならなかった。これからも友人であって欲しいとは思うけど」 陽雪と付き合ったのは状況に流されたからだけだった。竹緒も陽雪に対して、友情に毛の生えたような感情しか持つことはできなかった。 でもその経験がなければ、百音への気持ちに気がつかなかったかもしれない。 「でも今は好きな人がいるんだろ。先を越されてしまったな」 「それだけ頑張っているなら、そのうちにできるだろ」 「だと良いな」 陽雪は「にっ」と笑い、時計を見た。竹緒が乗る電車の時間も近づいている。 「そういえば、新しい彼氏は公開しないんだな」 これまでは陽雪に新しい彼氏ができるとすぐに噂としてその情報が流れていたが、今回は聞いていない。 「今回は忍ぶ恋を試してみているんだ。それじゃ、百音によろしく」 陽雪はすちゃっと手を上げて去っていった。そのまままっすぐ改札に向かうのかと思いきや、その足取りが不意に横にそれ、道端で新聞を読んでいた中年男の腕を捕まえた。中年男は慌てていたが、すぐに腕をとられて引きずられていった。少女は中年男からは見えないように、竹緒にVサインを送ってくる。 中年男はサングラスをかけ、キャップを目深に被っていたが、丸顔に猪の首の姿は見間違えようがなかった。 竹緒のクラスの担任である岩坂先生だ。 「今回は教師かよ!」 しかもよりにもよって岩坂! 竹緒はその積極性に呆れながら、別のプラットホームへと歩き始める。 初夏の晴れた日に、アリの雄たちは空に舞い上がってダンスを踊る。女王アリは、一番気に入ったオスをパートナーに選ぶ。 人間だって同じだ。一生懸命ダンスを踊って見せるしかない。 竹緒は電車に乗り込み、窓の外を見る。 とても気持ちよくダンスが踊れそうな青空が広がっていた。 了
|