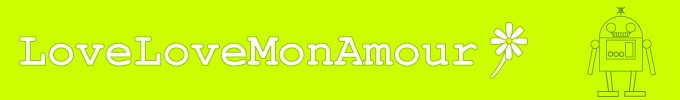
|
パワーポイント
翌日の午前中は羽生先輩に従って関係部署や、取引先を回った。二割であろうと三割であろうと、値引きをするのであればうちの部署だけで決められる話ではない。関係する部署や取引先に説明しなければならないし、お願いをしなくてはならない。 急な仕様変更はどこの世界でも嫌われる話だが、不思議なことに今回はどこも協力的だった。 午後は、「資料を作っておけ」との言葉を残して、羽生先輩は一人で出かけていった。前日とは違い、今日はすぐに資料作成を始めることができた。 関係先が前向きに引き受けてくれたのだ。当事者が頑張らないわけにはいかない。 「なんだ、まだやってたのかぁ」 羽生先輩に声をかけられて、いつの間にか定時を四時間も過ぎていることに気がついた。我ながら集中していたものだ。事務所に残っている人間はまばらになっている。 「羽生さんこそ、こんな時間に戻ってきたんですか?」 「お前がまだ残っているんじゃないかと思ってなぁ。飯は食ったのか?駄目だぜぇ、飯は食わなきゃ」 「羽生さんは?」 「食った」 言ってモニターを覗き込んでくる。そこにはプレゼン用資料作成ソフトが、色鮮やかな画面を表示している。 「相変わらず、細かい画だなぁ」 「羽生さんのがシンプル過ぎるんです」 近づいてきた口からアルコールの匂いがしたのに少しカチンときて、以前から思っていたことを言ってしまう。 「シンプルかなぁ」 「ほとんどテキストを貼り付けているだけじゃないですか」 「グラフも使ってるぞぉ」 「たまに使っているだけじゃないですか。先週の部会用の資料でも、オレが言うまでグラフを入れてなかったじゃないですか。そのグラフだって、ソフトが自動的に作ったのを使っただけで自分で編集はしなかったでしょう」 「そうだなぁ。でも、シンプルなのは悪いことか?」 「シンプル イズ ベストって言葉ぐらい知っています。シンプル過ぎるって言っているんです。ソフトの能力を全然生かしきれていないじゃないですか」 「生かしてなくても、相手に伝わればそれでいいじゃないか」 「伝えるなら、強い印象を与えられたほうが良いじゃないですか。その為にこれだけの機能がついているんじゃないんですか?」 自分でも口調が刺々しく、大きくなってきているのが分かった。しかし羽生先輩はいつもどおりにひょうひょうとしたままだ。それがオレを更に苛立たせる。 「機能を使えば分かりやすくなるものでもないだろう」 「分かりにくいって言うんですか?」 ついに怒声を上げてしまう。 機能は使えばいいってものじゃない。機能を無駄に使われた資料は、分かりづらくなるだけだ。そんなことは分かっている。 オレは大学時代に教授の発表会用資料作りを散々させられた。教授は凝った資料が好きな人だったので注文は多く厳しかったが、おかげでかなり鍛えられた。その頃は不満たらたらでやっていたが、今では感謝しているぐらい、プレゼン用資料作成には自信を持っている。ソフトの機能を最大限に使い、その上で分かりやすく仕上げているはずだ。 「分かりやすいと思うよぉ」 気に入らない点を指摘されるなら、まだ納得できる。しかしあっさりと認められるとバカにされているようでイライラは更に強くなっていく。 羽生先輩はそんなオレには構わず、資料を最後のページまで見てから、ひょいっと顔を上げる。 「いいんじゃないか。少しだけ見積もりが甘い点があるけど、それは明日計算してから送るから、修正してちょーだい」 「話をすり替えないで下さい。機能を使うかどうかって話はどうなったんですか」 「えー、今からその話をするのかぁ?早く帰りたいんだけどなぁ」 「羽生さんが言い出したんじゃないですか!」 「んんん、そうかぁ。その話がしたいかぁ」 無精ひげが伸び始めている下あごをポリポリとかいて、先輩はどかっとイスに座った。 「お前はこれを作るのに何時間かかった?昼からずっとやっているなら八時間か。じゃあ、オレの作るレベルの資料なら何時間で作れた?」 「四、・・・・・・三時間もあればできました」 「四時間としようかぁ、ちょうど定時だしなぁ。つまり、オレレベルの仕事であれば残業をせずに帰れたわけだ」 この人はなんでこうもすぐに論点をずらすのだろうか! 「レベルを落とせって言うんですか?それで契約が取れなかったら、意味がないじゃないですか!残業代と契約とどっちが大事なんですか」 「いやいやいや。契約を取るのは大事だよ。でも分かりやすい資料があることが、イコール契約を取ることじゃないだろ」 「自分にできるベストを取っているだけです」 「ベストかぁ・・・・・・、自分の得意分野を頑張ることだけがベストだとは思わないけどなぁ」 その一言には少しどきっとさせられたが、ただの苦し紛れの一言にしか思えたから引かなかった。 「得意分野を売りにするのは当たり前じゃないですか」 「それも一理あるよなぁ」 先輩はまたしてもあっさりと認めながら立ち上がった。ひょいっとカバンを持ち上げる。 「明日の朝、先方にアポイントを取ってくれ。オレとお前の二人で行くから。それから明日の午前中にもう一つ資料を作ってくれるかなぁ。今作った資料をオレレベルに作り直して。後でそれを比較するから。な」 全く釈然としない命令だったが、それに逆らったところで引いてくれないのは分かっていた。この人は、普段はひょうひょうとしてとらえどころがないが、こうと決めたときには絶対に引かないのだ。 「分かりました」 憮然と答える。どちらが良いのか、思い知ればいい。 「今日はもう帰れぇ。それじゃぁ、お先にぃ」 「お疲れ様でした」 気がつくと事務所に残っているのはオレだけになっていた。 パソコンを閉じ、片付けを始めると、カバンの底にネコミミを見つけた。 取り出してじっと見つめる。ふにふにと揉んでみる。手触りも追求しているのか、かなり気持ちがいい。 周囲をゆっくりと見回し、誰もいないことを確認してから、頭へと持っていってみた。 真っ黒な窓に、ネコミミをつけた男が反射されて、こちらを見ている。 ネコミミをゴミ箱に放り込んで事務所を出た。羽生先輩に対する怒りはいつの間にか消えてしまっていた。 ぺろぺろぺろぺろぺろ 「ひゃぁあ」 事を終え、ネコミミを入手することになった長い理由を説明していたところ、急に耳を攻められて、オレはみっともない声を出してしまった。千晶はその声を面白がって攻める手、ならぬ舌を強める。 オレは耳が弱い。とんでもなく弱い。攻められると抵抗できない。 疲れているときに攻められると逃げることもできなくなり、精根尽き果てるまで攻められてしまう。そして千晶はこれをチャンスとばかりに精根尽き果てるまで攻め立ててくるような女だ。 今日はなんとか力任せに引き剥がし、逃れることができた。 素早くベッドの反対側に回り込んで、逆に襲い掛かるポーズを取る。 狙うは千晶の耳。 彼女はオレ以上に耳が弱い。ちょっと指で触れただけでも身体を強張らせる。しかしオレがそこを攻撃することは滅多にない。後でとんでもなく怖い目にあわされるからだ。 「はい、終わり終わり」 しかし千晶はすぐに対峙するポーズを解き、服を着始めた。 耳を攻められるのが嫌なのもあるだろうが、なにより休憩時間がもうすぐ終わりだ。 「はい、ネコミミ」 頭から外したネコミミをベッドの上に投げ、洗面所の方に行く。 「でもあれだねー」千晶は化粧を直しながら言う。 「耳が四つもあるってことは、弱点が四つもあるってことだ。それは大変だ」 若村みそのに電話をかけながらその話を思い出し、確かにそれは大変だなとあらためて思った。 でもそれよりも、電話をする時は、受話器をどっちの耳に当てるのだろうかと気になった。電話の構造的にネコミミまでは届かないか?特注の電話があるのか? 「分かったにゃ。それではお待ちしていますにゃ」 電話の向こうの若村みそのはそんな妄想には応えてくれず、 「分かりました。それでは明日十時にお待ちしております」 と普通の対応をしていた。もちろん、どちらの耳に受話器を当てているのかなんて分からない。耳が弱点なのかどうかも分からない。 でもそんなのは問題じゃない。 彼女は目下の興味の対象ではあるが、同時にビジネスの相手だし、今のオレには後者の立場をより重要視しなければならない。 再訪問日の朝には、ようやくそこまで気持ちを切り替えることができていた。 あの日の帰り道、羽生先輩に言われたことがようやく理解できた。 「準備はできたかぁ」 その先輩はいつもと同じように気の抜けた調子で訊ねてくる。 「はい、ばっちりです」 力強く答えた。 カバンの中のノートパソコンには心血を注ぎこんだプレゼン資料が入っている。昨日の午前中、オレは指示通りに飾り気のない資料を作った。それをチェックした羽生先輩は、 「どっちの資料を使うかは、お前に任せるからぁ」 と言った。 先輩の意図していることも理解できなくはなかったが、それでもオレは自分の意思を通し、ソフトの機能を限界まで使い尽くした方を選んだ。そのことに対するコメントはなかった。 二人でタクシーに乗り、輝星コーポレーションに向かう。 空はぼんやりと曇っている。しかし帰り道には、この雲を吹き飛ばすぐらい晴れやかな気持ちで出てくるだろう。 輝星側は担当の女性が別件で欠席している以外は前回と同じ三人構成だった。 男性、関課長に続き、若村みそのが入ってくる。 今日もその頭にはネコミミがくっついている。 くっついているではなく生えているか。 耳が生えているとは言わないか。耳がついている?耳がある?ネコミミがある? ちょっと混乱気味になったところで、気がつくと目の前に若村みそのが立っていた。 「今日はよろしくお願いいたします」 と言って頭をちょこんと下げる。 一緒にネコミミがちょこんと下がる。 「あ、ああ……はい。こちらこそ……」 答えながらも目をそこから反らすことができない。 意識していないのに、意識しないようにしているのに、しないようにすればするほど、視線が、意識が、そこに吸い込まれていってしまう。 オレの目の前でネコミミがひくひくしている。 ひくひく、ひくひく…… 「ひっ」 突然の悲鳴に我に変えると、黒いネコミミに何かがくっついていた。目を凝らすと人間の手だと分かった。誰の手だ?と辿っていくと自分の手だった。 オレはいつの間にか若村みそののネコミミを掴んでいて、彼女は体を強張らせていた。 「す、すみません」 急いで手を引いたが遅かった。 若村みそのはそのまま部屋から出て行った。少しなみだ目だった気がする。 「あ、あの」 助けを求めようとすると、他の三人は顔を伏せていた。 「いけませんなぁ」 「いけませんねぇ」 関課長の苦言に羽生先輩が応じる。 「これはセクハラになるんじゃないですか」 「そこはこれまでの御社と弊社との付き合いを考慮していただきまして。今回は御社の要求をすべて呑みますので、それでどうかご勘弁いただけませんか」 羽生先輩はそう言って、契約書を一枚差し出した。オレは知らない契約書だ。内容までは目に入らないが、部長のサインがすでに入っていることは分かった。 「もちろん、弊社も御社とはこれからもいい関係を続けていきたいと思っています」 関課長はおごそかにその書類を受け取り、部長のサインの横にペンを走らせる。 なにが起こっているんだ? オレはパニくったままだった。 なにが起こっているのかさっぱり分からない。 正しくは、何が起こっているのかを理解したくなかった。 若村みそのはそのイニシャル、MWを取って、メンタルウェポン(Mental Weapon)と呼ばれており、この業界では有名人らしい。 「ミャアウェポン(Mew Weapon)ってのもあるけどなぁ」 そんな解説はどうでもいい。 とにかく、輝星コーポレーションにネコミミを持つ女性社員がいることはよく知られていることであり、同時にその精神攻撃兵器としての役割も知られていた。 輝星コーポレーションがどうしても譲れない案件が出きた時、若村みそのは登場する。始めて彼女に会った人間はどうしても彼女のネコミミを触ってしまうのだそうだ。 「里崎君はよく我慢したな。私なんか会って五秒で触っちゃったよ」とは部長の言である。 「一回目を乗り越えたから、もしかしたらと思ったんだがな」 その期待には応えられなかったわけだ。 触ってしまったが最後、セクハラが声高に叫ばれるこのご時世では、引かざるを得ない。 「もっとも、みそのちゃんが出てきた時点で道は二つしかないんだけどねぇ」 彼女が交渉の場に出てきたこと事態が最終通告なので、輝星側の条件を全面的に受け入れるか、断るかの二つしかない。 よって今回も、オレがどんなに素晴らしい資料を作ったとしても、ネコミミを触っても触らなくても、三割カットがくつがえることはなかったのだ。それゆえ、羽生先輩はすぐに東西奔走して輝星コーポレーションの条件を受け入れる根回しを行い、部長のサイン入りの契約書を用意していたのだ。 「オレがやってたことはなんだったんですか……」 会社に戻ってから裏事情を明かされたオレは、デスクに突っ伏した。 部内の人間には連絡が回っていたらしく、あちらこちらからくすくすと笑う声が聞こえてくる。どうやらオレが触るかどうかは賭けの対象にもなっていたらしい。 「良い勉強になっただろう。立派な資料を作ることが、良い仕事だとは限らない。その時その時で、一番適した方法を見つけないといけないんだなぁ」 「分かりましたよ」 本当に良く分かった。 夜の事務所で先輩相手に感情を高ぶらせていた自分が恥ずかしい。 「まぁそう落ち込むなぁ。使う場面はなかったけど、お前の資料が良くできていたことは認めるから。ご褒美にこれをあげるからさぁ」 羽生先輩はそう言ってオレの頭になにかをつけた。 手で触ってみる。覚えのある触り心地だ。 顔を上げると、周囲から一斉に爆笑が起こった。 何が起こっているんだ? いや、何が起こっているかはもう分かっていたが、それを認めたくはなかった。しかし、ノートパソコンをゆっくりと開け、モニターを見て確認した。暗いモニターの中にはネコミミをつけたオレの姿が写っていた。ゴミ箱に捨てたはずのネコミミが、頭の上に乗っかっている。 笑い声はまだ続いている。むしろ部内からフロア全体に伝染していっている。 「喜べぇ。今日は部長が慰労をかねて飲みに連れて行ってくれるそうだぁ。ただし、お前はネコミミを外すの禁止な」 先輩が更なる笑いを呼んでいる。 女子社員が「私も行くー」と声を上げているがちっとも嬉しくない。 溜め息と一緒に頭を下げると、片方のネコミミがぽとっと落ちた。 了
|