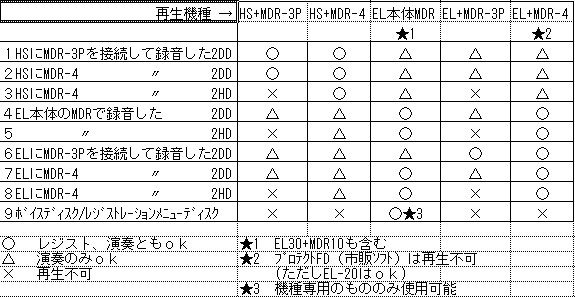
もっと知りたいEL90/87
エレクトーン機能の雑学を、毎月一話読み切りでおとどけします。
1 MDRについて その(1)
で、第1回目はMDR4について。
これはMIDI対応になっており「MDR3Pとどう違うの?」「HS8でMDR4は使えるの?」などいろいろな疑問をお持ちかとおもいます。
それで、表にまとめてみました。
MDR互換表
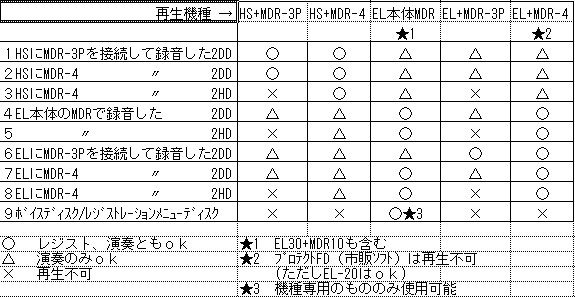
EL90にMDR4をつないで市販ソフトのコピ−を取ろうとしたアナタ。ソウハトンヤガオロサナイ。残念でした。が、なぜかEL20にMDR4をつないだ時だけヨミコミができるのは不思議ですね。
2 MDRについて その(2)
今回は、レジストの読み込み方イロイロ。
「そんなのプレイボタンを押せばいいんでしょ。」な−んて言わないで
少しつきあって下さい。
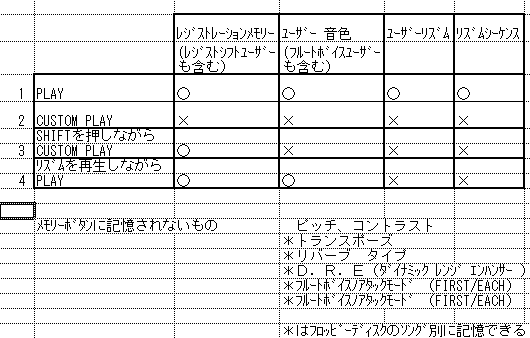
まずPLAYとCUSTOMPLAYのちがい。表を見ればわかると思いますが、
CUSTOMPLAYでは何も読み込まれない。でも、、
演奏が入っている場合(メモリ−の切替がコントロ−ルで入っている場合も)CUSTOMPLAYを押せばすぐに00秒から始めることができます。
つまりEL本体にPLAYボタンを使って一度レジストを読み込めば、あとはCUSTOMPLAYを押せば良いわけです。(時は金なり)表3はウラ技です。ユ−ザ−に関するものを使っていなければこの方が速い。(お試しあれ)
表4は何でしょう?「中途半端なものはキライ!」というアナタ。
知って得する情報はアシタノココロダ!
3 MDRについて その(3)
表4はどういうことかというと、EFなどで大曲を弾くとき「メモリーが16個じゃ足りない…あと1000個はほしい(マサカ!)」と思ったことはありませんか?
ELの場合リズムを走らせていても(もちろんシーケンスを使用中でも)ほかのSONGを読み込むことができるのです(HSはできない)。この時ユーザーのリズム・シーケンスの情報が読み込まれたら困りますよね。で、表4のようになるのです。センサイなプレーヤーは1曲で4つも5つも読み込みます。さすがプロのこだわりですね。
これを応用すれば、レジストのガッタイも簡単。例えばAさんBさんがそれぞれの得意分野を活かし、FDを持ち寄ったとします。
Aさん=ユーザーリズム・シーケンス
Bさん=レジスト・ユーザー音色
1 AさんのFDを読み込む(PLAYボタン)
2 リズムをスタートさせる
3 BさんのFDを読み込む(PLAYボタン)
4 リズムを止めて他のSONGにメモリーする
これを愛のガッタイレジストと言います(ウソ)
4 MDRについて その(4)
愛のガッタイレジストその2
「レジストはできたんだけど、あとひとつインパクトのある音があれば…」
そう思ったことはありませんか?そう、世の中はインパクト次第。
インパクトさえあればキムタクでもボケられる。『ウチの敵はジャニーズ事務所でっせ。
SMAPにボケられたらかなわんわ』吉本興業専務談。
というわけで愛のガッタイレジストの登場となります。
ピンチを救う愛こそ本当の愛です。「自分でユーザーボイスを作っているヒマはない…
(講師は忙しいんだ!)」「友人にユーザーボイスのコレクターがいる」
どうやってコレクションするのでしょう?
世の中には、プレーヤーのコンサートのあと集めて(?)いる人がいるとか…。
トミオカヤスヤさんはアンコール曲のおじぎと同時にリセットレジストを読み込んでいる!
さすがプロのこだわりですね。
で、やり方は…。
1 ユーザー音色が入ったFD/SONGを読み込む
2 ボイスエディットボタンを押しながらユーザーボイス(もちろん欲しいユーザー
音色を選んでから)を押す
3 VOICE EDITの画面のOL(アウトプットレベル)を1つだけ動かす
(上下どちらでもよい)
4 FDを抜く(ボイスエディットボタンが点灯したままの状態で)
STOPボタン)
6 ユーザー音色を登録する(SAVE画面)
7 ボイスエディットを終了する
8 レジストをメモリーする([M]ボタンを押しながらRECORDボタンを押す)
これで完成です。なぜアウトプットレベルを動かすのかって?(パラメーターのどこでもいいのですが)
こうすることによって「これは私が作った音ヨ」とコンピューターをダマスわけです。
5 ボイスエディットの第一歩
私はよく人に「エディットした音を見て下さい」と頼まれることがあります。そんな時にはまず「音、出してみて!」と言います。
すぐにエディット状態にできる場合は(レベル1)には「どのパラメーターイジッタの?」と聞きます。
さらにちゃんと説明ができる場合(レベル2)には「じゃ、また」
と言って帰ります。(何のこっちゃ?)
ちなみに、レベル1でつまづいた場合は人のウワサ話でモリアガリます。レベル2でシドロモドロの場合には良い曲集でも紹介してお茶を濁します。
世の中には無理なことを言う人もいるもので「(オペラ座の怪人の)
カミナリの音がほしい」とか「(ワルツィングキャットの)犬の鳴き声がほしい」とか…
でもそれは整形外科の(シンセサイザー)の領分であって、エレクトーンはいわゆる美容院(メイク)の世界です。よく肝に銘じるように!
それではEL90全音色の秘密を公開しましょう。ポイントはAWM音源とFM音源のブレンドにあります。(このあたりは「ここが知りたい!EL90/87 Q&A」P50〜P62を参考にして下さい)なお、アウトプットレベルがそのままヴォリュームになるとは限りませんので耳で確認が必要です。
この表は6年前作成したもので一度も更新していないので、あまり信用しないように!自分で確かめましょう。
「かくれ音色」というのはバランスが少ない方の音源に何が入っているか、ということです。
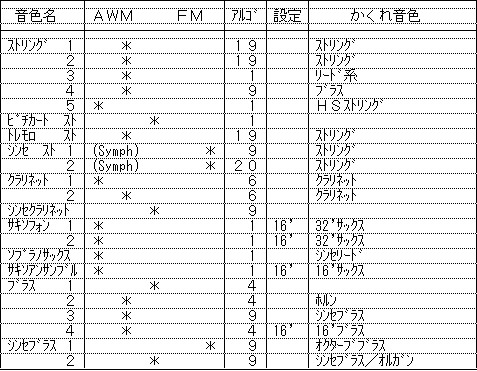
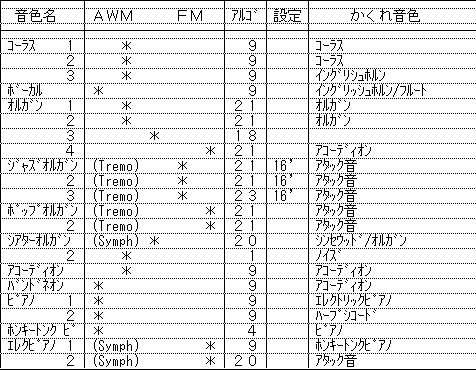
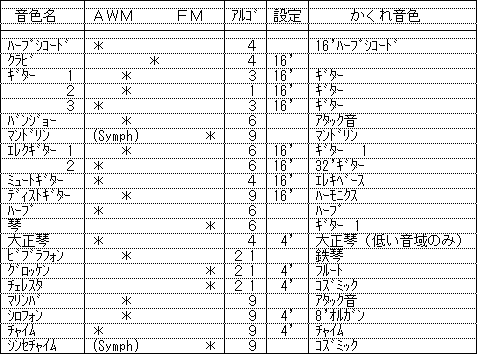
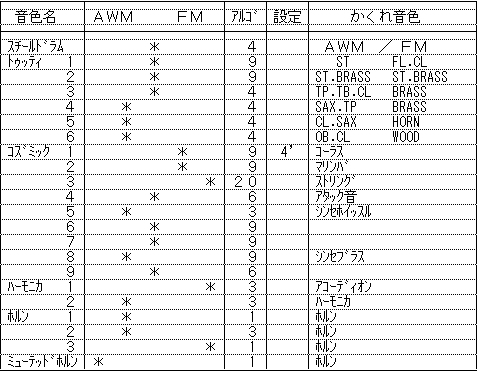
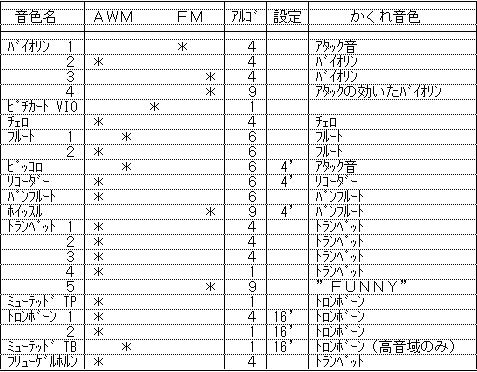
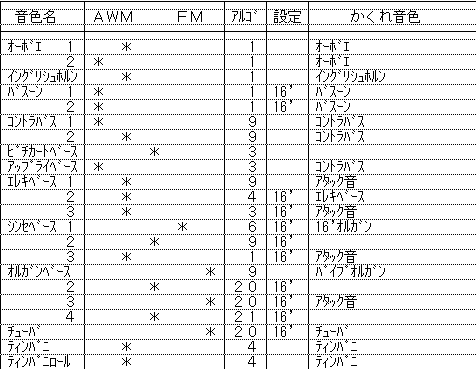
ELシリーズはすべて上位互換性を持っています。つまり、下の機種のデータは上の機種でチュウジツに再生できるということです(出力や構造の違いで音量バランスは少し変わりますが)。
が…ひとつだけウマクイカナイトコロがあります。大きな声ではいえませんが(ここだけの話)。
それはユーザーボイスです。
例えば、EL37からEL90へデータを移した場合を考えてみましょう(えっ、37はボイスエディットがないじゃないかって?でもボイスディスクがあるでしょ)。
37のユーザーにボイスディスクの[1]ピアノと[2]エレクトリックピアノを登録します。
それを90で呼び出すと…あら不思議、[2]はそのままですが[1]の音は少しちがいますね。(この音はFMのニオイがする)。
どういうことかというと、AWM音源が切り離されしまうのです。[2]はFM音源のみで作ってあるので大丈夫(37に戻せば[1]もちゃんと音が出ます)。
ただし、90で音量バランスを変えるなど上からレジストを書き込むと、37に戻したときには音が変わってしまいます。
8 魔法のディスク その1
レジストメニューディスクをご存知ですか? これはさまざまなレジストのパターンが、あらかじめ記憶されているFDのことですネ。エレクトーンを購入すると付いてきます。(ただしEL20/27/30は本体内蔵)。
EL90/70では1枚になっていますが、EL50は別のディスクになっていて持ち歩きにはめんどうですね。そこでコンピューターでそれぞれファイルを見ると… A>Dir
下の表のようになっています。
RGM_35.DAT EL70用レジストメニュー (イ)
RGM_36.DAT EL90用レジストメニュー (イ)
RGM_3D.DAT EL50用レジストメニュー (ロ)
ですからこれをまとめるには(ロ)を(イ)にCOPYします。こうすれば(イ)のディスクを1枚持っていればどこへ行っても大丈夫。ついでに言えば、EL20用レジストメニュー(EL27に付いてくる)のファイルネームは
RGM_43.DATです。これも(イ)に入れてしまえば4種類のデータが1枚のディスクで管理可能になります。
こうしてできた(イ)のディスクのバックアップをとりたいときは必ず{DISKCOPY}で作ってくださいね。
新春よもやま話(壱)EL90の大変便利なディスプレイ。たくさんの情報がいちどに把握できて、とても助かります。
パターンプログラムやボイスエディットの終了時にはとてもテイネイな言葉までいただき、ヤマハの
良心を感じます。が、DISKのFORMAT時には知らん顔。「CAUTION!」と3回ぐらい
点滅してもいいと思うのですが、、、。
(弐)みなさんEL90はどんな部屋においてありますか?我家は30畳のアビテックスにスタンウェ
イ2台と特注のアレンジ机、ELXの白と黒が部屋の真ん中にドーンと…なわけないでしょ。
貧乏人の悲しさで、初夢もせいぜいこんなところ。せっかくエレクトーンのウラ側がきれいになったの
に、カベに向かって弾いている現実。私はフタを机代わりにしているありさまです。が、音を出したい
時手が入らない(前田憲男さんのようにマージャンしながらスコアは書けない)そこで提案!
フタにストッパーをつけて手が入るようにしましょう。こうするとアレンジも楽ですよ!(誰か作っ
て!)
(参)リズムプログラムでシェーカーとカバサの音が反対のような気がするのですが…。
おなじドだから間違えた…なんてことはあるハズがないですよね。私の耳が悪いのでしょう。

