- 引込脚といっても、予め脚を引き込めておいて手投げし、ゴムが開放すると脚出しをして降りてくるというものです。グリーンパークには脚出しで離陸後、脚を引き込めて上昇し再び上空で脚出しをして降りてくるタイプを作っている方がいらっしゃいます。その上、博物館モデル並みの精密さですからまさに芸術品です。恐れ入りました!
- 脚の骨はt1.2のピアノ線で真鍮パイプの軸受けにより回転します。ピアノ線はクランク状に曲げられていて、脚だしの状態では先端がステンレスの板バネに開けられた穴に入るようになっています。(脚がロックの状態)
- 引き込むときは、針金などで翼の下面に開けた小さな穴からステンレスバネを押してやればロックが外れ脚が引込み可能になります。
- 脚を完全に引き込み、胴体側の車輪カバーで押さえてストッパーを掛けます。この状態でゴムを巻けばストッパーが掛かったままになります。
- 胴体後部のゴム掛け用の穴は長穴になっていてゴム掛けが前後に動くようになっています、ゴムを巻くとゴム掛けが長穴の前に引き寄せられます。ゴム掛けには航空ベニアで出来たリンクが通してありゴムが巻かれることで索が引かれます。索はバネで常に機首側に引く力がかけられています。
- 索がゴムの力で後に引かれるとストッパーが車輪カバーを押さえるようになっています。この状態で手投げします。
- 上空でゴムが開放すると索がスプリングの力で前へ引かれストッパーが外れます。脚は自重(フリクションがあるときはスプリングで押し出す)で開き、ピアノ線の端がステンレスバネを押し上げて穴に入り脚が固定されます。
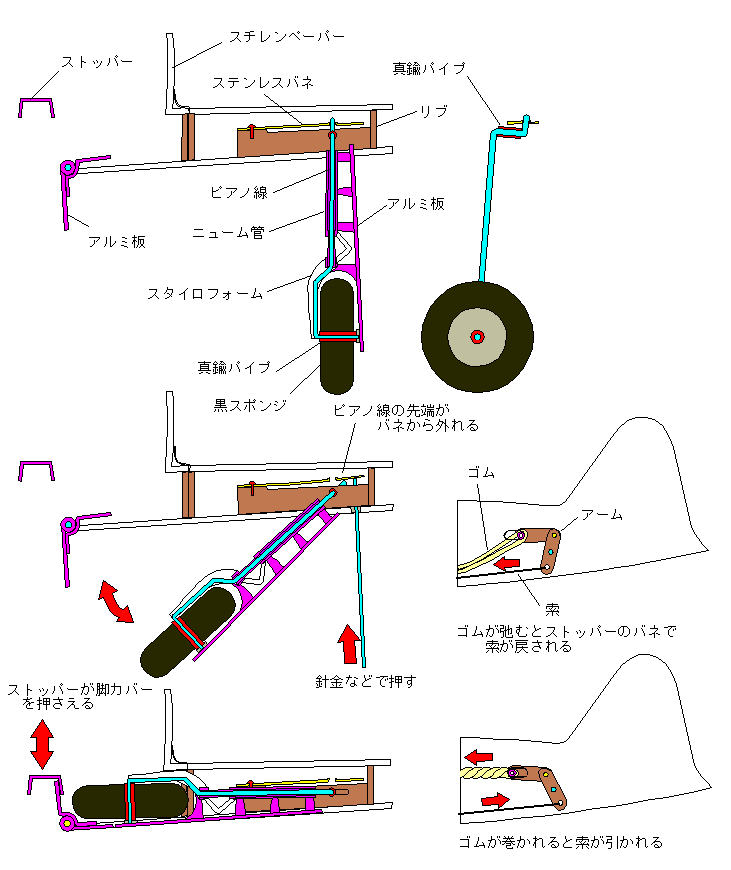
表紙へ リストへ
リストへ 次へ
次へ