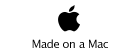ここでは当院で使用している炭酸ガスレーザーの活用方法について簡単に述べてみます。
1.歯肉の炎症軽減
歯槽膿漏の急性発作、智歯周囲炎、歯周膿瘍などの急性炎症がある場合、炎症部位へのレーザー照射により、症状の改善が早くなります。
2.口内炎、アフタ、ヘルペス、義歯による褥創の鎮痛・消炎
病変部への1~2回のレーザー照射により、症状は劇的に改善され、治癒も促進されます。
3.抜歯後、歯周外科治療後の治癒促進、疼痛緩和
抜歯や歯周外科治療の後に、処置部位をその周辺も含めてレーザー照射しておくと、止血と血餅形成が促進され、術後の疼痛や腫脹が軽減し、創の治癒も早くなります。
4.メラニン色素の除去
歯肉に沈着した黒っぽいメラニン色素はそのまま放っておいても問題ありませんが、沈着が強い場合は審美的に良くありません。2~3回のレーザー照射によりかなり効果があり、明るく健康的な色になります。ただし、重症の場合は数ヶ月後に再発することがあるので、再照射が必要です。
5.小帯切除への応用
メスによる切除に比べ術式が簡単で、出血もなく縫合が不要。術後の疼痛も少なくなります。
6.歯肉の切除
冠(かぶせもの)をいれるために、歯を削った後に歯型をとる時、歯肉が歯を覆ってしまいうまく型がとれないことがあります。また、義歯をつくる際、ぶよぶよに腫れた歯肉があると義歯がうまく合わない場合があります。レーザー照射してこのような歯肉を除去すると、出血も少ないのでその後の処置がスムーズに進み、治癒も他の方法より早くなります。
7.知覚過敏処置
むし歯でないのに冷たいもので歯がしみる人は多いですが、これは歯肉が下がったために歯の根元が露出してしみる(象牙質知覚過敏症)、あるいはさらに、強い横みがきのために歯の根元がすり減った(クサビ状欠損症)ためにしみることが多いようです。レーザーを歯またはその根元の粘膜に照射すると、鎮痛効果があります。ただし、効果は個人差があり、効きが悪い人はさらに2~3回繰り返します。
また、そのほかの炭酸ガスレーザーの応用方法として、

・歯内療法への応用
・顎関節症への応用
などがあり、これからもますますその応用範囲が広がると考えられています。
左の写真は炭酸ガスレーザーのハンドピース部ですが、先端から下方にガイド光が照射されているのがおわかりになると思います。(実際にはレーザー光は目に見えません。)
レーザー光はこのようにごく小さな範囲をスポット的に照射するため周囲組織への影響が少なく、また組織への吸収は表面から0.1~0.2mmと極めて表在性であり、深部組織への熱的障害が少ないといえます。
以上述べてきたように、炭酸ガスレーザーは正しい使い方をすれば安全性に問題はなく、臨床上の有効性も高いと言えましょう。