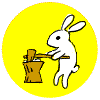 旨味をまして出番を待ってま〜す
旨味をまして出番を待ってま〜す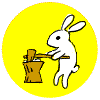 旨味をまして出番を待ってま〜す
旨味をまして出番を待ってま〜す だらだらと、暑い日が続いていますが、お元気ですか。
ここにきて、朝夕は少ししのぎやすくなりましたが、今年の夏は長くて厳しい暑さでしたね。
体の方も疲れがたまっていて、少し涼しくなっただけでもホッとした気持ちになります。
さぁ!これから、味覚の秋の到来。
この夏に失った気力と体力を、おいしい旬の食とますます旨味ののった日本酒でゆっくりと取り返したいと思っています。さて、酒蔵では呑みきりも終わって、そろそろ酒造りの準備が始まっている頃でしょうか。
当店にも、続々と「ひやおろし」など秋の限定品が入荷予定です。楽しみにしていて下さい。
1升ビンの限定品、買って帰りたいけれど「一人だからなぁ」とか「冷蔵庫に入らないからなぁ」という声をよく聞きます。1升瓶の日本酒をおいしく飲みきる方法があります。
それは取り分けです。ご自分で飲んだ4合ビン2本を用意します(よく洗って乾かしておく)。買って帰られた1升のお酒を、この2本のビンに取り分けます。
この時に守っていただきたいのは、口もとをまでピッチリと満量いれるということです。
なぜ。ピッチリと満量を入れていただきたいか?
それは、日本酒に空気がふれて酸化するのを防ぎたいからです。そうすると、4合ビンに2本分と、ちょうど今日の晩酌分の約1合半が1升ビンの中に残ります。4合ビンは冷蔵庫の中に入れていただいて、今日は1升ビンの中に残ったお酒を楽しみます。
残り2本は後日ゆっくりと楽しめばいい。
こうしておけば、全く同じとはいきませんが、開栓時に近い状態で味わうことができます。
4合ビンでも同じこと、お酒は強くないけれど、美味しい日本酒をゆっくりと楽しみたい方。
ビンの中のお酒の量が少なくなって空気の量が多くなると、お酒はどんどん酸化して品質が落ちてしまいます。
そこで、早いうちに300mlビン(生酒などの)に口もとまで入れて、冷蔵庫で保存すれば、ゆっくりと楽しむことができます。これからは、秋の限定品のシーズンです。1升ビンでしか発売されない商品も多くなります。ぜひ、取り分けで、新しい味にチャレンジしてみて下さい。
もう一つ、新しいお酒を買われる前に、今飲んでいるお酒を少し残しておいて下さい。新しいお酒との飲みくらべです。
イメージよりも、並べて飲みくらべると、新しい発見もあったり、また、自分の好みもハッキリして、とても面白いですヨ。ただ、酒好きにとって、この少し残すって、けっこう難しいんだけどね。
酒造りの最中、酒母室の作業をよくよく観察すると、酒母係(蔵ではモト屋といいます)が、ときどき酒母タンクのところへ行って、小さい柄杓で水を掛けているシーンに出会います。
その様子は、お茶室で釜から湯を汲むように優雅に見えます。また、神社のおまいりするときに手水で手を清め、口をすすぐあの神聖なしぐさのようにも見えます。
あれは何をやっているのでしょうか。
これが汲み掛けをしているところなのです。
酒母はモロミの仕込みの15分の1ぐらいです。モロミと違って、なかなか沸いてきません。量が少ないこともあって発酵が遅いのです。でも、部分々々は発酵していますからこれを掻き回して平均にしたいのです。ところが小さいといっても洗濯機の水槽ではない。
簡単に掻き回せません。
酒母づくりには「櫂で潰すな、麹で溶かせ」という格言があります。酒母ができていく過程を酒母の溶けぐあいで計ります。
溶けぐあいが悪いと、モト屋は叱られるのが恐いので櫂ですり潰してしまうことがあります。
そこで、酒母が溶けるのは麹の酵素力によるのだということを教えるために「櫂で潰すな・・・」ができたのです。
酒母の中のどこに酵素はあるのでしょう。酵素は麹にあります。そして仕込み水に溶け出しているのです。そこで知恵者が思い付きました。
「あの、お茶漬けのような酒母の中の水を取り出して飯の部分に掛ければいい」。発明はこうしてできるのです。
でも、お茶漬けの中からお茶をどうやって取り出すのでしょう。茶漬けなら茶碗を傾け、ごはんが流れ出さないように箸で押さえるぐらいで済みますが、小さいとはいえ酒母タンクは、ちょくちょく傾けられるものではない。傾けてもどれほど水を汲めるか。
また考えました。飯のようになったところに穴を掘って、回りからジワジワと水分を浸み出させる。これならうまくいきそうです。
やってみたら、その穴は井戸のように深いほどいいことがわかりました。が、飯の壁が崩れてきます。
崩れないようにするには、堀った穴に籠を差し込めばいい。
こうして酒母の中の水分だけ集めることができました。
モト屋さんが、ときどき柄杓で汲んで掛けているのが「汲み掛け」です。汲み掛けによって「櫂で潰すな、麹で溶かせ」が可能になりました。
でも、あまり単純な作業ですから、忘れてしまうことが多いのです。忘れてはせっかくの名案も台無しです。別な知恵者がいました。こちらは機械いじりが好きでした。
汲み掛けの籠をアルミ製にし、それに小型のポンプを付けました。ついでにポンプの圧力を利用して排出孔を回転させました。
無人の酒母室で、汲み掛け装置は酒母の水分を汲んでは、野球場のスプリンクラーのように回転しながら汲み掛けしています。
そろそろ、秋の訪れを感じますね。自然の恵みをいっぱいうけて黄金色に色づく稲穂。
稲刈りの声が聞こえ始めます。時同じくして酒蔵も徐々に活気にあふれてきます。今年の冬に仕込まれたお酒は、お蔵の中での静かな眠り(熟成)から醒め、私達の元へ限定品や、ひやおろしなど、様々な形でまろやかで美味しそうな顔をして届けられます。
それと並行して、お蔵元には杜氏さんと共に蔵人達が酒造りにやって来ます。酒造りが始まります。これから約半年、正月なしの酒造りのスタートです。夏の間、静かだった酒蔵の煙突から毎日、蒸米の蒸気があがり、蒸されたほのかに甘く感じる酒米の香りが蔵を満たします。そして12月頃には、新酒がぞくぞくと出そろいますが、みのりの秋、旨酒が疲れた体を心から思いっきりリラックスさせてくれますよ。
さぁ、ゆっくりと楽しみましょう。
お待ちかねの入荷です。酒仙一献は富山、満寿泉の秋から冬の季節限定のお酒です。今年の酒仙の口当たりはしなやかで軽やかな印象を受けます。お客様も”あっ酒仙だっ!もう
そんな季節になったんですね〜”なんてかかえて帰ってくれます。
季節感のある酒だなぁとつくづく感じます。
720ml・・・1,750円, 1.8リットル・・・3,250円
1997年ヴィンテージ純米大吟醸と純米原酒セカンドのワイン瓶が入荷しております。
昨年度は初年度ということもあり、純米大吟醸は予約のみで完売してしまい、ご迷惑をおかけしました。本年度は前注予約は取っておりませんが、入荷量は限られておりますので、なかなかお越しになれない方はご一報くだされば、押さえておきますヨ。
MASUIZUMIスペシャルワイン瓶は、満寿泉蔵元、桝田隆一郎氏が、さらなる日本酒の可能性を模索して生まれました。ただワイン瓶に貯蔵しただけではありません。酒の仕込み配合にもこだわり、ワイン樽による熟香味にもへこたれない日本酒で仕上げてあります。新しく生まれるであろう日本酒の世界の一辺に迷い込みそうです。
きっと新しい体験になると思いますヨ。
純米大吟醸720ml・・・4,000円,
純米原酒720ml・・・2,050円
やわらかな吟香と、力強くバランスの良いお酒です。のどに落ちるまぎわのナシの様な含み香がなんとも言えません。
720ml・・・3,500円
昨年にひき続き今年もおいしい。”有機米しずく”は1年に春と、秋と、年末と3回ぐらいは楽しんでいただきたい。どの時のお酒が旨いか?それは、その人の好み。上質のくだものがどんどん熟してゆく様にこのお酒も変わってゆきます。一つのお酒の変化を1年を通して追ってみるのも楽しいです。
720ml・・・1,700円