/// 華厳寺は鈴虫寺 /// (03/01/22)


|
今回は洛西続きで妙徳山華厳寺を 訪ねましょう。 さて華厳寺って何処と思われる方も おられるかと思いますが、鈴虫寺と 聞けば誰もが思い当たるところです。 鈴虫寺は宣伝熱心なので、ガイド ブックの広告などにもよく載って いるので、一度は見られたことがある のではないかと思います。 今は臨済宗永源寺派の寺院ですが、 華厳寺と名乗るには訳があって、 この華厳寺の開基は華厳宗を復興 しようとした鳳潭(ほうたん)和尚で あると云うことにあります。 前回は地蔵院で破戒僧、一休宗純の 話題に触れましたが、この鳳潭和尚も 一休宗純に負けず劣らずの奇僧だった ようです。一休宗純もそうですが、 この場合の言葉使い、破戒僧、奇僧の 意味合いには親しみと尊敬が込められて いるようです。 |

|
鳳潭和尚は承応三年(1654)、江戸時代 前期に現在の富山県石動に生まれます。 12才で出家し比叡山での修行の日々を 過ごしますが、30才頃の逸話が残ります。 延暦寺での仏法勉強、日毎に講義内容は 難しくなり学生は一人抜け、二人抜けし、 やがては鳳潭一人になってしまいます。 講師は「明日は講義を中止しようと 思うが…」と鳳潭に問いかけます。 すかさず鳳潭は「明日は学生を集めて 来ますから」と答えたと云います。 さて、講義当日、講師は異様な光景を目に することとなります。 そこには鳳潭が座して、周囲には伏見人形 (土偶)が並んでいたと云います。 鳳潭いわく「これまでの学生はこの土偶に 等しい学生で、真の学生ではありません。 これまでそのような学生に講義をされて きたのですから、これからも同じように、 この土偶にも講義を続けて下さい」と 答えたと云います。 |

|
この答弁にすっかり感心した講師は講義を なおも続けたそうです。 あまり使いたくない言葉ですが、俗に箸 にも棒にもかからない、どうしようも ない人に対して「でくのぼう」と云う 言い方がありますが、この”でく”とは 人形のこと、「でくのぼう」と云うこの 慣用句の由来はこの話にあると云われます。 また、酒屋で偶然目にした大福帳、 今で云う経理の帳面ですが、その大福帳が 火事で焼けた時には、鳳潭の偶然目にした 記憶によって完全に書き戻されたとも 伝わる天才僧でもあったようです。 このような由来から入学、勉学のご利益が 伝わっていたりもしますが、何故かこの 鳳潭和尚の御影を戸口に貼ると盗難除けに なるとも云われます。 なんで?、どうして?、って状況ですが、 この疑問、いつか解決しましょうか。 |
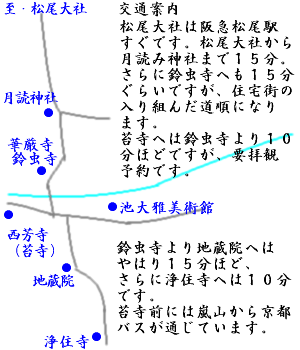 |
今ではこの鳳潭和尚の話より、鈴虫、幸福 地蔵の話の方が知られているかな〜。 鈴虫の寿命はわずか110日、鳴くのはその 一生の最後の20日間だけだそうです。 鈴虫寺では28年間にも渡る研究、飼育の 成果としてほぼ毎日孵化させることに成功し、 今では一年中鈴虫の音が聞こえるお寺に なっています。 もう一つ幸福地蔵の話、このお地蔵さんは 珍しく草鞋(わらじ)を履いています。 このお地蔵さんに願いをかけると、お地蔵 さんは一軒づつ願い事を尋ねに来てくれ、 そして必ず一つだけ願いを叶えてくれる そうです。 鳳潭和尚は享保八年(1723)に華厳宗復興の 一翼を担い華厳寺を建立しますが、 その華厳寺も三代にして臨済宗に鞍替えして 今に伝わります。今では鈴虫、幸福地蔵の 話題で知られる華厳寺ですが、華厳寺と云う 名の由来に奇僧、鳳潭和尚を思い出せば きっと幸福になれるかな。 |