/// 知恩院、七不思議 /// (05/07/15)
この前は”知恩院の忘れ傘”の話題でしたが、今回は七不思議。 何で七つなんだ、五不思議とは言わないな〜、 語呂がいいからでしょうか。 なので七つ用意しなければならない訳ですが、知恩院の七不思議は 昭和の頃の資料、知恩院の説明には書かれているのですが、 明治の頃での書かれている書物、資料には見あたらない。 私が調べた、見た限りの話なので、定かではないですが、知恩院の 七不思議は後世の作?? 知恩院の不思議とは、忘れ傘、鶯張りの廊下、白木の棺、抜け雀、 三方正面真向の猫、大杓子、御影堂屋根瓦、瓜生石、数えると八つに なってしまいます。 |
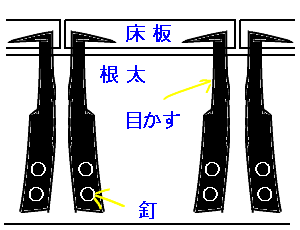
|
忘れ傘は前回紹介しましたので、まずは、 ”鶯張りの廊下”。二条城の代わりと なる機能も有していた知恩院は、二条城と 同じく、侵入者除けのために将軍の休憩 部屋だった部屋を中心に、大方丈、 小方丈を囲む廊下が鶯張りとなっています。 廊下において土台の根太(ねだ)に板を 固定するために、「目かすがい」と云わ れる金具を使いますが、その”目かす” の穴と固定する釘が擦れて、あの鶯の ような、「キュッ、キュッ」と云う音が 出るそうです。 |

|
”白木の棺”。 三門の二階に置かれた棺で、中には 木像が安置されています。 なんでも三門建設における予算超過の 責任を取り、自刃した造営奉行の 五味金右衛門夫妻が彫った木像だと 伝わります。 ”抜け雀”。 これは大方丈にある襖絵のことで、描かれ た雀が飛び出してしまったとか、書き忘れ、 こじつけって書けば怒られるかな〜〜 ”三方正面真向の猫” 大方丈の杉戸に描かれた狩野信正の筆に なる猫の絵です。確かにどちら側から 見ても正面を向いているように見えます。 いわゆる騙し絵です。 |

|
”大杓子”。 大方丈廊下の梁に置かれている杓子で、 長さ2.5m、重さ約30kgもあります。 古い書物には節分の時に、この杓子を 持って「めしとったり」と声を掛け ながら各部屋を回ったとあります。 今は、「すべての人々が救い取られる」と、 一切衆生救済を表に掲げます。 う〜ん、微妙にニュアンスに違いがあるか。 ”御影堂の屋根瓦”。 御影堂の屋根最上段に瓦が数枚置かれて いるのを見ることが出来ます。 残されていると云った方が正しいのかも 知れませんが、これは今だ、完成して いないことを具現しようとするもの、 今後も益々発展することを願うものだとか、 また一説には、完成していないことを示し、 幕府より資金を得るための方策とか云われ たりします。 |

|
”瓜生石” 黒門前の交差点にある石。知恩院が 二条城の代わりとなる建築であったと 紹介しましたが、その二条城から続いて いる抜け穴の出口だとか、また、その昔、 この石に瓜が生えて一夜にして花が咲き、 実が成ったそうです。 その実には「牛頭天王」との文字があった とかで、祇園社の祭神が瓜生山から降臨 されたと伝わります。近くの粟田神社は 牛頭天王を祀り、粟田祭における剣鉾の 「瓜鉾」は、この石から生まれた瓜を象る と伝わります。 また、節分には豆を自分の歳より一つ多く 瓜生石に供える風習がありました。 知らない人が見ると、ただの邪魔な石に しか見えない、交差点の傍らに囲われて 残る瓜生石です。 |