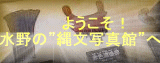
| 山 | 口 | 県 | 下 | 関 | 市 | の | 綾 | 羅 | 木 | 郷 | 遺 | 跡 |
|
綾羅木郷遺跡は、竜王山の東麓を源とする綾羅木川の堆積作用によって形成された綾羅木平野の北側、鬼ヶ城山地から延びる洪積台地の西端部に立地する。
郷台地下に埋蔵されていた良質の珪砂採掘事業推進の圧力に阻まれ、遺跡保存計画は一進一退を繰返していた。 標高8~13mの洪積台地上に位置する本遺跡からは旧石器時代の尖頭器が検出されているが、縄文時代の痕跡はなく、馬蹄形を呈する郷台地上で生活が営まれ始めたのは、弥生前期後半からであったと云う。 しかし弥生中期中頃には海進のためか、一旦より高い尾根に移動し、古墳時代中期に再び居住地として復活したと云う。 |
 遺跡現場
遺跡現場
|
遺跡の範囲は約30,000㎡に及ぶ。 昭和44年本遺跡を保存するため緊急に国の史跡指定を受け、現在は下関市立考古博物館を史跡指定地の南側に配する史跡公園として親しまれていると云う。 遺跡保存か開発優先かという大きな社会問題を克服して誕生しただけに“文化財保護”の象徴として際立っている。
本遺跡の特徴の一つは、1,000基以上の貯蔵穴とこれらを取り囲む環濠にあると云える。今までの調査では台地上に住居址は見つかっていない。 調査された範囲が限定されていることもあり、溝で区画された生活空間の全容解明には程遠く、住居跡が発見されていないこともあり、貯蔵穴群を囲む“貯蔵穴管理用”であった可能性が高いと云われている。 |
|
次に貝殻文付壷・ヘラ描文付壷・石鎌・大型石包丁を紹介する。
 以下文字列にポインタをおくと、弥生時代の象徴と云える生活用具・道具を見ることが出来ますよ! 以下文字列にポインタをおくと、弥生時代の象徴と云える生活用具・道具を見ることが出来ますよ!  |
| 更に大変珍しい人面土製品・土笛についてふれて見る。 |
 人面土製品
人面土製品
 土笛
土笛
|
貯蔵用の穴から発見された土製人形は高さ8.7cm・幅4.1cmで、タマキ貝を使って刺青のような線が刻まれている。
一方弥生前期の土笛は日本列島で最初の発見例として関心が集まったが、中国の殷の時代に盛行した卵形の土笛に類似していることから“陶けん”と名付けられたと云う。 これらの遺物以外にもコメ・ムギなどの穀物やイチイガシ・モモ・ウメ・クリなどの種子が炭化した状態で発見され、又イノシシ・二ホンジカ・タマキ・二ホンサル・クジラなどの骨、マダイ・ハマグリ・ヤマトシジミ・サザエなどの魚介類等々食料残滓も検出されている。 出土遺物については未だに継続的に整理が進められており、この台地に縄文人が居住していなかったかどうかも含めて、新しい発見に期待したい。 |

 明治時代に既に発見されていた本遺跡は、昭和31年に初めて本格的発掘調査が行われ、以降紆余曲折の末、昭和47年まで断続的に発掘調査が実施された。
明治時代に既に発見されていた本遺跡は、昭和31年に初めて本格的発掘調査が行われ、以降紆余曲折の末、昭和47年まで断続的に発掘調査が実施された。 貝殻によって描かれた木の葉を4枚繋ぎ合わせたような“木葉文”はベンケイガイが使用されたと見られているが、この“木葉文”は銅鐸の文様にも描かれ、弥生時代の象徴と見られる由緒ある文様と云われる。
貝殻によって描かれた木の葉を4枚繋ぎ合わせたような“木葉文”はベンケイガイが使用されたと見られているが、この“木葉文”は銅鐸の文様にも描かれ、弥生時代の象徴と見られる由緒ある文様と云われる。