
| 岩 | 手 | 県 | 大 | 船 | 渡 | 市 | の | 長 | 谷 | 堂 | 貝 | 塚 |
|
長谷堂貝塚は大船渡湾最奥の海岸に続く緩傾斜面にあり、現在の海岸より3kmほど北方・標高約20mに位置し、盛川東岸の河岸段丘上に立地する。 昭和30・46年の発掘調査では7地点から貝塚が発見され、縄文中期・後期・晩期から弥生時代にかけての集落跡であることが判明した。 貝層はアサリを主体にハマグリ・マガキ・ウミニナ・アカニシなど、魚類はイワシ・マグロなど、哺乳類ではイノシシ・二ホンジカ・イヌ・タヌキなどの骨類が出土した。 |
人工遺物では土器・石器の他、骨角牙器・骨角刺突具・骨製や貝製装身具・土製装身具、更には仰臥・屈葬人骨などが検出された。 又近年では平成8・9・11年にも断続的に発掘調査が行なわれ、縄文中期の竪穴住居跡40棟・掘立柱建物跡6棟・土壙約200基、縄文晩期の竪穴住居跡7棟・掘立柱建物跡3棟などの遺構が見つかっている。 縄文晩期の集落跡からは直径約11mにも及ぶ環状列石が見つかり、その周囲には柱穴が直径約1m・深さ約2mの掘立柱建物跡が検出され、周辺の土壙墓などと考え合わせると、葬送儀礼の場所と見られる。 |
 長谷堂貝塚
長谷堂貝塚
|
リアス式海岸特有の深い入江・大船渡湾の最奥部に位置する集落跡は、5ha余りの広さに及ぶ。 県立大船渡高校の東南約200m付近にあり、南北に水系を備えた日当たりの良い高台で、海・山の幸に恵まれた住み易い地域であったと思われる。 貝殻の散布範囲は一辺が約7mから15mほどで比較的小規模だが、遺物包含層は広範囲にわたっていたと云う。 砂泥底質に生息する貝類や哺乳類の遺物に比べ、魚骨の割合が極めて低いことから、当集落の生業基盤は木の実・貝類採集と狩猟が主体で、漁労活動は二次的であったと見られる。 |
 牙製垂飾
牙製垂飾
 貝輪
貝輪
 鹿角製用具
鹿角製用具
|
写真左上から牙製ペンダント・貝輪・鹿角製ヤス・モリ・ソケットなどと続く。 鹿角牙貝製品では、ヤス・モリ・ソケットなど鹿角製刺突具をはじめ貝輪やクマの牙に加工した穿孔垂飾品などが検出された。 他にも穿孔骨針・イノシシ犬歯製垂飾品・鹿角に彫刻した装飾品なども出土し、多種多様にわたる。 |
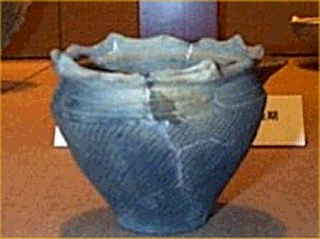 深鉢土器
深鉢土器
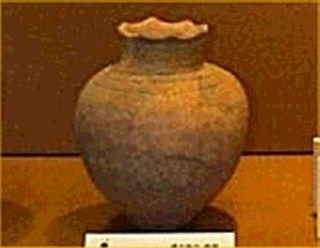 壷
壷
 漆入れ土器
漆入れ土器
|
縄文中期の大木式深鉢土器、縄文晩期の大洞式壷や同晩期の大洞式漆入れ土器などが検出された。 漆入れ土器は底に漆が残り固まった状態で見つかったと云うが、県内では二例目の発見で、貴重な資料として注目されている。漆塗り櫛・弓・椀などに使われたと見られる。 これら以外にも縄文後期の門前式・堀之内式・加曾利式などの土器や県内で初めて弥生時代の甕・鉢などが見つかっている。
気仙地方の遺跡分布によると、縄文終末期には全国最高の高密度で数多くの集落が存在していたが、弥生時代にはその数が激減し、稲作農耕を主体とする |

 弥生時代には辺境の地として大きく変貌したことを物語っている。
弥生時代には辺境の地として大きく変貌したことを物語っている。
