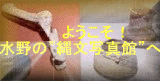
| 岩 | 手 | 県 | 北 | 上 | 市 | の | 八 | 天 | 遺 | 跡 |
|
八天遺跡は開田に伴い発見され、北上川左岸に接する総面積約2haの縄文中期から後期の集落跡として知られている。 仮面習俗の源流とも云える鼻・耳・口の土製品が発見されたことと合わせて、縄文後期最大級の住居跡が見つかったことから、昭和52年に国史跡に指定された。 |
 八天遺跡現場
八天遺跡現場
|
本遺跡眼下に北上川がゆったりと流れ、北上川が遺跡の母であったことが窺い知れる。
本遺跡からは同一形態で10回も建替えを繰り返した大型円形建築遺構が検出され、その規模は最大で長径約17m・短径約13.5m、最小で長径8.4m・短径7.6mもあり、当時としては特大の建物と云える。 この聖なる集会所では後述する“仮面破壊儀式”がしめやかに行なわれていたと見られる |
 鼻・耳・口
鼻・耳・口 鼻・耳
鼻・耳
|
本集落遺跡の中心部に墓壙群が見つかり、そのうちの土壙墓などから合わせて土製の鼻5点・口2点・耳1点、合計8点が検出された。 土製鼻・口・耳には取り付け可能な紐通しの孔が開いており、この種の土製品は宮城県などでも発見されている。 いずれも極めて写実的であり、大きさも人間のそれとほぼ同じで仮面の部分と見られる。
墓壙は南北2.2mを有する伸展葬と見られ、周縁には溝を巡らし川原石が詰まっていたと云う。
一ヶ所から鼻・耳・口と揃って出土したわけではなく、死者に被せた面というより、葬送儀礼に参加した人々が仮面を被って死霊になり代わったと考えられる。 仮面破壊の儀礼が行なわれる程の死者は、極めて異例で特殊な人物であったと見られる。
|
|
本遺跡を取り囲む台地の斜面には様々な遺物が捨てられ、層を成して積み重なって見つかり、これらの遺物の中にはこれら実用或いは祭祀用土器が混じっていたと云う。 これらの厳粛で神秘的にも見える注口土器類も、“仮面破壊儀式”で活躍したかも知れない。 |

 仮面の耳・鼻・口を切り取って葬ったと考えられる。
仮面の耳・鼻・口を切り取って葬ったと考えられる。 以下深鉢土器と壷、壷類、厳粛に装う注口土器そして神秘的な注口土器の順番に、特殊な用途に使われたと見られる土器類を紹介する。
以下深鉢土器と壷、壷類、厳粛に装う注口土器そして神秘的な注口土器の順番に、特殊な用途に使われたと見られる土器類を紹介する。
