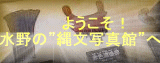
| 大 | 分 | 県 | 本 | 耶 | 馬 | 渓 | 町 | の | 枌 | 洞 | 穴 | 遺 | 跡 |
|
枌洞穴遺跡は名勝耶馬溪附近で山国川に合流する屋形川中流に出来た河蝕による洞穴で、洞穴入口の幅11m・奥行き9m・高さ6mほどの半洞穴を形成している。 当洞穴の発掘調査は昭和49年から57年の間、8次にわたり実施され、その結果洞穴内部は厚い土層が堆積し、その層位は1〜6層に大別され、そのうち5層までが埋葬地であったことが判明した。 洞穴内部からは縄文早期(約8,400年前)から縄文後期(約4,000年前)まで4,000年余りにわたり埋葬された人骨67体をはじめ、埋葬のために持ち込まれたと見られる土器・石器・貝殻・動物の骨・各種装身具などが発見された。 |
 枌洞穴前景
枌洞穴前景
 枌洞穴内部
枌洞穴内部
|
洞穴内部の表面には敷石など正住寺という草堂が営まれた痕跡があるものの、土層には撹乱の跡はなく堆積層は自然状態を保っていたと云う。 洞穴は南面しており、周辺は狭い沖積谷が東西に開け、南北は丘陵が続いている。
 以下文字列にポインタをおくと、平畑縄文人のいろいろな埋葬形態に出会えますよ! 以下文字列にポインタをおくと、平畑縄文人のいろいろな埋葬形態に出会えますよ!  |
|
縄文後期の母子合葬人骨は屈葬され、仰臥の姿勢で埋葬されていたと云う。 屈葬方法は悪霊にとりつかれた死者の再起防止に最適の方法と考えられていたと見られるが、母親の遺体には胸部から腹部にかけて大きな重石が乗せられ(抱石葬)、死者の再起防止に念を押したようにも見える。 一方縄文前期の屈葬人骨には顔面を除き12個の扁平河石で覆われ(覆石葬)、その重力から抱石葬に比べて再起不能を決定付ける必要性があったのかも知れない。
又縄文早期人埋葬の場合、腰の部分を切断して上半身・下半身を分離し、足を放棄して残りを埋葬している。
|
 |
貝輪・玉やペンダント・カンザシ・獣骨製の腕輪などの骨角器等、被葬者の装身具は遺体に装着して副葬されたと考えられる。 被葬者の身分・在りし日の面影が窺い知れる。 |
|---|
|
縄文時代を通じての埋葬が各層毎に確認・研究され、縄文時代数時期にわたる人骨が人類学的に比較研究された成果は特筆に値する。 8年間に及ぶ発掘調査・研究は、複数の大学の考古学者が参加して行われただけに今後新たなスポットライトが当る研究成果に期待したい。 |

 母子合葬の人骨
母子合葬の人骨 縄文時代を遡るほどに埋葬観念・形態が異なり、死者の悪霊に対する恐怖心が伝わってくるように思える。
縄文時代を遡るほどに埋葬観念・形態が異なり、死者の悪霊に対する恐怖心が伝わってくるように思える。