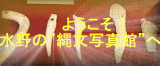
|
|
|
東釧路貝塚は縄文早期から近世にかけて14層以上を持つ複合遺跡で、特に道内の縄文前期(約5,000~6,000年前)貝塚では最も規模が大きい。
昭和33~46年にかけて9回に及ぶ発掘調査の結果、縄文早期以降各期の遺構・遺物のほとんどが認められ、本貝塚のある台地はその核になる部分であることが解明された。 貝塚を乗せた台地の半分ほどが鉄道や道路工事で失われてしまったことは、真に惜しまれる。 |
 貝塚現場Ⅰ
貝塚現場Ⅰ
 貝塚現場Ⅱ
貝塚現場Ⅱ
 貝塚現場Ⅲ
貝塚現場Ⅲ
|
JR東釧路駅後背地の高台に所在し、“縄文海進”がピークに達した縄文前期の大貝塚は東西約120m・南北約90mの範囲に、大小合わせて11ブロックに分かれて貝塚が分布している。 海面は現在より数m高く、暖流のお陰もあり冬の気温は今より5度ほど高かったと見られる。当時現在の釧路湿原は内湾となっていた。
南側の台地には共に東西20m・南北33mほどの大きな貝塚ブロックが相対している。
叉当時の海に面する北側の台地先端には急な斜面に沿って貝類が堆積していたと云う。 住居址は貝塚のある台地では1軒だけであるが、貝塚を取巻く周辺台地上には数多くの住居址が纏まって見つかっている。 |
 貝層断面 貝層断面 |
貝層の厚さは約1mでアサリが全体の70%ほどを占め、カキ・オオノガイがこれに次いで多い。 本貝塚遺跡が外海に近い内湾にある性格上、内湾で採れるアサリが最も多く、叉外海系の貝類をも伴う道内の典型的貝塚と云われる。 暖海性のアカガイ・シオフキなどの貝類も見られる。 |
|---|
 貝の種類
貝の種類
 貝の種類
貝の種類
| アサリ・カキ・オオノガイのほかホタテ・マガイ・ウミニナ・エゾイソシジミなどが見つかっている。 |
 海獣骨類 海獣骨類 |
カジキ・マグロ・スズキなどの魚骨やワシ・タカ・カラスなどの鳥骨の他、イルカ・オットセイ・クジラ・トド・アシカなどの大型海獣類、特にイルカ・オットセイの骨が多量に出土している。 海獣類が動物の骨の90%ほどを占めており、東釧路縄文人は海獣ハンターとして内湾・外湾で活躍していたことが窺える。 大量のイルカ捕獲は、音に驚き易い性格を利用し、現在でも使われている音をたてて大群を湾内に追い込む漁法が使われていたと考えられる。オットセイのほかトド・アシカなど成獣捕獲は、海に生きた猟師の凄まじい海獣狩りの生き様が偲ばれる。 |
|---|
 釣針・髪飾
釣針・髪飾
 銛・縫針など
銛・縫針など
海獣の肋骨製の回転式銛・組合せ式釣針・鋭く尖らせた刺突具など当時の漁労手法レベルの高さが窺える一方、先端に小さな孔を空け、繊細に磨かれた鳥骨製縫針、装飾的に加工されたヘアーピンなど 加工技術は驚嘆に値する。 加工技術は驚嘆に値する。加えて鹿・海獣骨・鳥骨など使用目的に応じて素材を厳選していたプロ加工技師が偲ばれる。 |
 黒曜石器 黒曜石器 |
石鏃・石槍など海獣狩の道具、解体調理用ナイフ、刃の部分が鋸状に刻まれた削器など膨大な量の石器が出土している。 当時の生活様式が実感できる。 |
|---|
 屈葬人骨 屈葬人骨 |
縄文早期~前期の人骨が数体発見されているが、貝塚の北東側の緩やかな斜面には土壙が集中して見つかっており、土壙だけでも200人ほどの埋葬が行なわれていたと見られる。 東釧路縄文人の人骨は分析の結果、“オンコロマナイ型”で道北・北東のアイヌ人の特徴を持っていると云う。 |
|---|
| 縄文前期当時の道東文化は、この地域ならではの独自性に富み、全国規模で眺めると文化の多様性が見て取れる。 |

