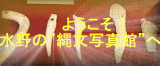
| 岡 | 山 | 県 | 灘 | 崎 | 町 | の | 彦 | 崎 | 貝 | 塚 |
|
彦崎貝塚は昭和23年造り酒屋の拡張工事に伴い発見され、以来再三にわたる発掘調査の結果、20数体の縄文人骨・土器・石器・装身具・獣骨・貝類などが検出され、縄文前期から後期にかけての遺跡であることが判明した。
本貝塚の大半は、残念ながら土取り工事により破壊されたと云う。 |
 彦崎貝塚
彦崎貝塚
 同そのⅡ
同そのⅡ
|
JR彦崎駅南側約200mに位置し、総面積約2,500㎡の広さに及び、岡山県下では最大級の貝塚と云われている。 県の中南部に立地する本貝塚は、北は岡山市・東南は玉野市・西は倉敷市に接している。 |
 人骨の一部 人骨の一部 |
20数体の人骨はほとんどが、最下層の腐植土中に径60~80cmくらいの楕円形に、深さ20~30cmの穴を掘って屈葬されていたと云う。 人骨の分析によると、変形性関節症、軟骨が磨り減った関節面、砂混じりの食物を摂った痕跡が偲ばれる歯群、逞しい上腕骨の発達など厳しい筋肉労働・過酷な生活振りが窺えると云う。成人の骨から推定して彦崎縄文人の寿命は30歳位であったと見られている。 |
|---|
 貝類
貝類
 獣骨
獣骨
|
下層からはハイガイ・カキを主体にアカニシ・ウミニナ・レイシ・シジミなど36種の貝類やイノシシ・シカなどの獣骨が出土した。 上層は礫の混じった貝層で、下層の貝層下の腐植土層中からは人骨のほか、木の実・木炭・灰などが検出されたと云う。 |
 土器片
土器片
 叩石
叩石
|
縄文前期から後期にかけての土器片が見つかり、“彦崎式”としてこの地方を代表する標識土器となっている。 石器類は叩石のほかサヌカイト製の石匙・石鏃・石槍・石錐などが出土した。 |
 貝輪
貝輪
 首飾り
首飾り
|
人骨に混じって貝輪・首飾りなどの装身具が検出されたが、彦崎縄文人の生活文化が偲ばれる。 本貝塚は岡山県下の貝塚発掘の契機となったことで知られているが、灘崎町の歴史は約7,000年前の縄文前期に始まり、水と緑に溢れる美しい自然を先人は見逃さなかったと云える。 |
