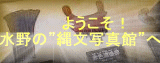
| 長 | 野 | 県 | 飯 | 田 | 市 | の | 縄 | 文 | 遺 | 跡 |
|
飯田市は東を伊那山脈・西は木曽山脈の連山に挟まれ、その中央を天竜川が南下し、所謂伊那谷の南半分に位置し、複雑な段丘地形に起因した豊かな自然の恵みに囲まれている。 豊かな自然環境は約3万年前の後期旧石器時代から人々の定住を可能とし、市内各所には550ヶ所余りの縄文・弥生遺跡が確認されている。
|
| 大明神原遺跡 |
|---|
|
大明神原遺跡は縄文中期の集落で、3年間に及ぶ発掘調査の結果、竪穴住居址39棟・狩猟用の落し穴を含む土壙約800基・集石炉3基などの遺構が検出された。 又イノシシ・二ホンジカなど大型動物捕獲用と見られる落し穴が40基ほど見つかり、深さは1.5mほどにも達する。 |
 大明神原遺跡
大明神原遺跡
 大明神原遺跡
大明神原遺跡
|
写真左が伊那山脈を、右が木曽山脈を望んでいる。 眼下に見える道路建設に先立つ発掘調査で見つかり、伊那山脈及び木曽山脈をそれぞれ背景に、伊那山麓に流れる天竜川を望む高台の尾根に位置している。
|
|
写真の一つは自然の脅威を鎮め敬う献納物の容器に見える、又顔面のような把手を持つ土器か、或いは土偶にも見える。 把手付深鉢土器は、持ち運びに便利なように実用性を加味したセレモニー用具に見えるが・・・・。 土偶は十字架をイメージしているように見え、或いは両手を拡げ踊っているようにも見えるが、左足の一部を欠損しているもののほぼ完形で検出されている。 |
| 増野新切遺跡 |
|---|
|
増野新切遺跡は天竜川右岸の扇状地上に立地し、昭和47年中央自動車道建設に先立つ発掘調査で発見された。 縄文中期後半を中心とする拠点的集落で、78軒の竪穴住居址・一ヶ所に集中する土壙群などの遺構が検出された。 |
 釣手土器
釣手土器
|
釣手頂部に突出部があったらしく破損しているが、高さ38cm・底径19cm前後と最大級のランプ用途土器。 この土器は意図的に破砕され、2ヶ所に分けて置かれ、一方には何かを封じ込めるように礫が乗せられていたと云う。 この地方固有の特殊な意図・慣習があったと推測される。
渦巻文その間に三叉状文を配し、それらを取り囲んで沈線を施している。 当遺跡からは釣手土器以外に土偶・石棒など祭祀用具が多数出土し、特に石棒は家の内部に立てられ、集落の中心的役割を担う家とも見られるが、祭祀をことのほか必要とした集落と考えられる。 |
| 典型的釣手土器 |
|---|
|
釣手土器はランプの役割を果たした土器と考えられるが、その分布地域は甲信越地方と関東地方の一部に限られ、又出土数も少ない。 飯田市内では縄文中期後半の釣手土器が多く出土していると云う。
|
 垣外遺跡の顔面付釣手土器
垣外遺跡の顔面付釣手土器
 栗屋元遺跡の釣手土器
栗屋元遺跡の釣手土器
|
顔面付並びに顔面なし釣手土器の造形・文様など、いずれを取っても独創的で、個性豊かな芸術作品として特筆に値する。 分布地域が山岳地方に多く、山岳信仰の象徴的用具とも考えられる。 |

 以下縄文時代の代表的遺跡を紹介する。
以下縄文時代の代表的遺跡を紹介する。
