| 千 | 葉 | 県 | 千 | 葉 | 市 | の | 加 | 曽 | 利 | 貝 | 塚 |
加曾利貝塚は都川上流の台地上にあり、直径約130mの北貝塚と約170mの南貝塚から成る複合貝塚で、南北合わせた貝塚は8字形をした日本最大級のモノとして知れれている。 又貝塚の規模だけでなく、加曾利E式土器・B式土器の標式遺跡としても名高い。 これら縄文土器などから当貝塚は今から約7,000年前から2,500年前まで続いた縄文ムラであったことが分かっている。 日本全国には1,600ヶ所ほどの縄文貝塚があり、うち関東地方には約1,000ヶ所が分布し、千葉市内には約110ヶ所が見つかり、世界的にも貝塚が密集した地域として知られている。 |
 貝塚現場
貝塚現場
| 約134,000㎡が国の史跡として指定され、公園として保存されている。 クリ・クヌギなどの自然林が繁り、又地形も当時のままを残していると云う。 |
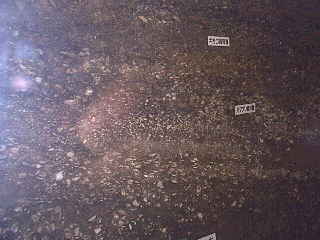 貝塚貝層
貝塚貝層
| ド-ナツ形をした大形貝塚からは、二枚貝のハマグリや巻貝のイボキサゴなど濃い海水の干潟に生息する貝類が多く出土し、わざわざ東京湾まで採りに行ったことが分かていると云う。 縄文中期の北貝塚の貝層断面からは、春から夏にかけてイボキサゴなど小さな貝を多量に採っていたことが分かり、又縄文後期の南貝塚ではハマグリなど二枚貝が大きくなり年間を通じて採っていたと云う。 |
 シカ骨製銛
シカ骨製銛 モリ・釣針
モリ・釣針 土製錘
土製錘| 大形の魚はヤス・モリが使われ、1mを超えるマダイの骨やマダイの頭骨にヤスが突き刺さった例も見つかっていると云う。 マダイ・スズキ・コチ・ボラなどの骨が多く出土していることから春から夏にかけての沿岸漁労が盛んであったと見られる。 |
 加曾利E式
加曾利E式 加曾利B式
加曾利B式| 大正13年の発掘調査でE地点・B地点という場所から見つかったため、上下層位の区分から縄文中期のE式・後期のB式として土器標式となった。 縄文中期は粘土層を使った立体的文様が流行し、後期から晩期のなると様々な形の土器が作られるが、文様は平面的で連続的な区画文様が多く見られる。 |
 屈葬人骨
屈葬人骨 加曾利人骨
加曾利人骨| これら縄文人骨から当時の生活振りが良く分かると云われる。 顔は幅広で彫りが深く、ガッシリとした幅広い顎の骨や歯の磨り減り方は硬いモノを食べたためと見られる。 |
 埋葬イヌ骨
埋葬イヌ骨
| 埋葬された5体のイヌ骨の中には骨折が直った跡が見つかり、狩猟のパートナーとして大切に飼い続けられたことを物語っている。 いずれにしても縄文人骨・イヌ骨は当時の生活文化・習慣などを明らかにしてくれる物証として貴重な遺物である。 厳しい自然環境・災害・疫病など不安な縄文時代を生き続けるためには、様々な祈りを捧げた当時の精神生活が伝わってくる。
写真の順番は先ずはアクセサリー類で、ヒスイ製玉・南方の海でしか棲息していない貝製腕輪・骨や角製カンザシとペンダント・土製耳飾り・骨や牙に孔を空けた腰飾り等々。 これらアクセサリーは相当の時間と労力をかけた精巧な作りで、お洒落目的というより様々な祈りが込められていると考えられる。 次に命をかけて子孫を守り残そうとした、祈りや呪術の象徴である土偶・石棒・石剣で、幼児段階で死に追いやられる当時の環境を如実に物語っていると云える。 最後に当貝塚から出土した2種類の異形土器で、生活の必需品としての器種の多様化と共に、祭祀・儀礼の活発化に伴う儀具として特異な器形、華やかな装飾や色彩を持つハレの土器もその多様性の道を歩んだ。 |
| 以上見てきた通り、加曾利貝塚から出土した遺物は当時の生活文化・精神文化を雄弁に物語っている! |

 以下加曾利縄文人の精神生活をいろいろな出土遺物を通じて追って見る。
以下加曾利縄文人の精神生活をいろいろな出土遺物を通じて追って見る。