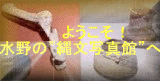
| 鹿 | 児 | 島 | 志 | 布 | 志 | 町 | 片 | 野 | 洞 | 穴 | 遺 | 跡 |
|
片野洞穴遺跡は中川内川の左岸、シラス及び溶結凝灰岩の山地にできた水蝕洞穴で、標高約100mにあり、洞穴の前庭を小川が流れ、床面は水面より約2m高いところに位置している。 志布志町は鹿児島県東部志布志湾奥のほぼ中央に位置し、現在では九州唯一中核国際港湾の指定を受け、大隈地域の拠点都市と位置付けられている。
昭和39年志布志町史編纂事業の一環として発掘調査が実施された結果、縄文前期から弥生時代に至る遺跡であることが判明した。 標準的な地層は9層を数え、地表から185cmほどで地下水が湧き出し、更に約50cmまで発掘調査が行なわれ、それ以下にも遺物包含層が続いていたが、地下水位が上昇し、排水方法を講じなければならず、更なる発掘は不可能であったと云う。 |
 現場遠景
現場遠景
 現場近景Ⅰ
現場近景Ⅰ 現場近景Ⅱ
現場近景Ⅱ
|
洞穴入口は幅約12m・高さ約4m・奥行き約67mあるが、入口より約19m付近で幅5mほどに狭まり、この地点を過ぎると再び広くなって奥行きは更に続く。
表層からは黒川式や網目圧痕文など縄文晩期の土器のほか、弥生から中世の土器類も出土している。 |
 (獣骨・貝類) (獣骨・貝類)獣骨の種類はイノシシ・シカを主体に数多く出土し、魚骨にはサメの歯なども確認された。 その他にもツキノマグマ・イヌ・タヌキ・アナグマ・ノウサギ・ムササビ・サルなど多種類に及ぶ。
貝類は淡水産・海水産いずれも相当量出土した。
獣骨製かんざしは長さ10.3cm・幅1.3cm・厚さ0.3cmを有し、先端が欠失しているので長さ約16cm前後と推定される。 本洞穴遺跡は地下水位上昇のため、必ずしも十分な発掘調査が出来なかったが、県下では最も代表的な洞穴遺跡として広く周知されている。 |
 (釣針・かんざし)
(釣針・かんざし)