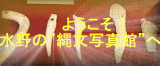
長 野 県 明 科 町 の 北 村 遺 跡
|
北村遺跡は県のほぼ中央・松本平の北端に位置し、町の中央を清らかに流れる犀川沿岸の丘陵に立地している。
|
|
常念岳・鹿島槍ヶ岳など北アルプスの雄大な山並みと安曇野の広がりが眺望できる絶好の立地条件に恵まれ、現在では中央自動車道を見下ろすところに所在する。 約5,000〜4,000年前の縄文中期には、信州中央高地一帯は日本一を誇る人口密集地として、生命力溢れる様々な文様土器に象徴されるように、物心共に豊かな縄文ムラが形成されていた。 しかしその後年間平均気温が2度前後下がると共に、自然環境が大きく変わり、日常生活に支障を来たすまでに至った。 |
 幼児人骨
幼児人骨
|
北村縄文人の人骨は、本遺跡の共同墓地一帯の地下8mほどから見つかり、湧水に守られ、指の先まで骨が残るほど好保存条件に恵まれた。 写真の幼児人骨は現存する10体ほどの完形人骨の一つで、他の成人男女の人骨にはイノシシの牙製ペンダントやブレスレットで飾られていたモノ、顔面が土器で覆い隠されていたモノ、枕石をあてられたモノ、伸展葬や屈葬、抜歯が見られたモノ等々当時の風俗・習慣が垣間見られる。 又石と墓壙を組み合わせた約80基の配石墓には、側縁部に長方形の河原石を立て並べ、内部に大形の扁平礫を敷いたモノ、一方内部に小形の河原石を敷いたモノ、更に内部に敷石を設けたモノ、石棺状配石を箱状に組んだモノ、大形の扁平礫を円形土壙の壁際に立て並べたモノ等々、死者に対する考え方・死者の扱い方などにも一定のルールがあったと考えられる。
更に北村縄文人骨に蓄積した炭素と窒素の“安定同位対比”(生涯にわたり何を主に食べていたかを復元する方法)による食性分析の結果、 |
 当時の衣服
当時の衣服
 当時の履物
当時の履物
|
北村縄文人の想像衣服及びはきものと考えられる。
縄文人の衣服は“カラムシ”などの繊維をむしろ編みのようにした編布で、その痕跡が本遺跡から発見された。 一方履物は写真のような靴型土器や土偶の足などから、わらじぐつのような履物が想像できる。縄文人の生活スタイルが想い起こされる。 |
 石棒
石棒
|
日本海側と太平洋側の文化交流の結節点でもある当地は、経済上重要な位置にあり、沿岸部からは石器・装飾品の材料を入手していたことが判明。 祭りに使われたと見られる石棒のほか、墓石・土偶など祭祀用道具が増えたこの時期は、厳しい自然環境を乗り越え、生き抜こうとしていた北村縄文ムラの苦悩が垣間見られる。 縄文後期を最後に消滅した北村ムラは、約1,700年前・弥生終末以降断続的に人々が住みつき、更に江戸時代から現在まで集落が維持されてきたと云う。 |

 この丘陵地帯には原始から古代にかけて、本遺跡のほか“ほうろく屋敷遺跡”など多くの遺跡が発見されている。
この丘陵地帯には原始から古代にかけて、本遺跡のほか“ほうろく屋敷遺跡”など多くの遺跡が発見されている。 次に長野自動車道の明科トンネル入口付近に広がる遺跡現場・北アルプスを眺望できる現場周辺環境などを紹介する。
次に長野自動車道の明科トンネル入口付近に広がる遺跡現場・北アルプスを眺望できる現場周辺環境などを紹介する。
 北村縄文人のタンパク質の74%はクリ・ドングリ・クルミなど植物性から成り、内陸部に所在する縄文ムラの特性であり、貝塚に見られる沿岸部の縄文人と際立った違いが立証されたと云える。
北村縄文人のタンパク質の74%はクリ・ドングリ・クルミなど植物性から成り、内陸部に所在する縄文ムラの特性であり、貝塚に見られる沿岸部の縄文人と際立った違いが立証されたと云える。