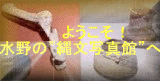
| 広 | 島 | 県 | 東 | 城 | 町 | の | 馬 | 渡 | 岩 | 蔭 | 遺 | 跡 |
|
馬渡岩陰遺跡は帝釈峡一帯の石灰岩地帯に分布する多数の岩陰・洞窟遺跡群の代表的な一つで、昭和36年の林道工事に伴い発見され、帝釈峡遺跡群発見の糸口となった、記念すべき遺跡。 昭和37〜39年にかけて3回にわたる発掘調査の結果、石灰岩の岩壁前面には長さ約20m・深さ約5mに及ぶ遺物包含層の中に縄文前期から旧石器時代に至る5つの文化層が確認された。 旧石器時代から縄文時代へと移行する過渡的な様相を示す、全国的にも数少ない貴重な遺跡であると共に、広島県内では最古の遺跡として比類のない地位にある。 |
 遺跡現場
遺跡現場
 前面馬渡川
前面馬渡川
 遺跡壁面Ⅰ
遺跡壁面Ⅰ
 遺跡壁面Ⅱ
遺跡壁面Ⅱ
|
遺跡現場、遺跡真ん前を流れる馬渡川及び石灰岩が露な壁面など。
帝釈川の支流・馬渡川の右岸にあり、切り立った狭い渓谷に立地する。 |
 (剥片石器及びオオツノジカの骨類) (剥片石器及びオオツノジカの骨類)第5層からは土器を伴わない、安山岩製の横剥ぎ剥片石器や更新世の絶滅動物であるオオツノジカの骨類が出土し、約2万年前の遺物と考えられている。 第4層から出土した縄文草創期の無文土器との関連からも、旧石器時代から土器が出現する縄文時代への移行の様相が明らかになった。
|
 海産貝類等
海産貝類等
 石鏃等石器
石鏃等石器
|
海産貝類と貝輪など貝製品及び石鏃・凹石・磨石など石器類。
海産貝類では、ハマグリ・ハイガイ・サルボウ・アワビ・マガキなどが出土している。 石鏃は香川県産サヌカイト製で、二等辺三角形・正三角形に近い形・両脚が尖る抉りの深いモノなど。縄文前期・早期層からは、石匙・石錘・打製石斧なども出土している。 帝釈峡遺跡群の発掘調査研究は1962年の第一次調査以来、40年余りを経過しているが、既に確認している遺跡群の四分の一にしか過ぎず、完了までには今後更に長年月を要する。
本遺跡群は石灰岩層のお陰で保存状態は良好で、各時期の変遷が層位的につかめると共に、人類学・古生物学など他分野の研究にとっても重要な資料を提供している。 |
 (無文土器)
(無文土器)