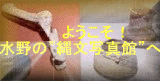
| 鹿 | 児 | 島 | 県 | 大 | 隅 | 町 | の | 鳴 | 神 | 遺 | 跡 |
|
大隅町は鳴神地域一帯に分布する、縄文早期から晩期、弥生・奈良から近世にかけての複合遺跡。 平成4〜7年にかけて土地区画整理事業に伴う発掘調査の結果、各時代の建物跡・道跡・住居址などの遺構のほか、土器・石器などの遺物が出土した。 |
 鳴神遺跡
鳴神遺跡
|
現場には住居が点在する芋畑が広がっている。
「弥五郎伝説の里」で知られる大隅町は錦港湾を見下ろす高地にあり、大隈海峡を流れる黒潮の影響もあり、高温多湿の気象条件は多種類の亜熱帯性植物を育んだ。 |
 様々な石器
様々な石器
 大小の石器
大小の石器
|
埋納されていた様々な石斧、中でも注目は異形石斧。 縄文晩期の埋納石器22点が出土したが、国内最古で最多と云われる。
22点の石斧は、ほとんどが土掘り用道具の打製石斧であるが、中には木を切る丸のみ、根堀用具と思われる石斧など機能性に富んでいる。
|
 やしの木
やしの木
 幾何学文様
幾何学文様
 突帯文土器片
突帯文土器片
|
やしの木が刻まれた土器片、幾何学文様が刻まれたモノ及び二重の刻み目を持つ突帯文土器片。 “やしの木”が刻まれた土器は奄美大島でも発見されており、当時の交易・交流が窺える。 これら縄文晩期の夜臼式土器の文様は、縄文文化終末の土器様式として特徴付けられる。 |

 埋納石斧は供養を意図した祭祀形態であったかも知れない
埋納石斧は供養を意図した祭祀形態であったかも知れない
