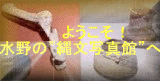
| 神 | 奈 | 川 | 県 | 大 | 磯 | 町 | の | 縄 | 文 | 遺 | 跡 |
|
大磯町は相模灘及び高麗山・鷹取山をはじめとする丘陵に囲まれ、太古の昔から豊かな恵みを約束され、様々な文化を育んできた。
当地方の縄文遺跡は一部中期の土器片などが検出されているものの、本格的集落形成は縄文後期以降と見られる。 又勝坂式・加曾利B式などの土器型式から関東地方の縄文文化圏に属し、特に際立った地域特性は見当たらないと云う。
|
|
石神台遺跡は大磯山塊の西南端の丘陵上にあり、標高約80m、西方に富士山・箱根連山、南方に相模湾を望む風光明媚な高台に位置している。 昭和47年石神台団地造成工事に伴う発掘調査の結果、縄文から奈良・平安に至る複合遺跡であることが判明した。 |
 石神台遺跡
石神台遺跡
 遠景に相模湾
遠景に相模湾
|
既に住宅が密集している石神台地から、写真の通り相模湾を望むことができる。 住居址は見つかっていないが、縄文後期の配石遺構が多数検出され、その下の土壙から25体以上の人骨が出土し、墓壙であることが証明された。 更に弥生時代の方形周溝墓も確認され、この台地が縄文から弥生時代に至るまで墓地として利用されていたと云える。 |
 加曾利B式
加曾利B式
 小型壷
小型壷
|
土壙には加曾利B式土器や一部には中部地方的色彩の強い土器が副葬されていたと云う。 又小型土器が逆位や入れ子の状態で出土したり、ベンガラが入ったままの小型壷や折れた石棒・土偶などが検出され、この付近で埋葬儀礼・儀式が行なわれていたと見られる。 |
|
大磯小学校遺跡は標高約20mの台地上に立地し、現在の海岸線から約400m内陸に当る、縄文後期を最盛期とした遺跡であることで知られている。 今まで校舎改築の度に多量の土器などが出土したが、昭和49年に体育館建設に伴う本格的発掘調査の結果、配石遺構・石囲い炉などの遺構が検出された。 出土遺物では土器が約3,000点、加曾利B式・堀之内式・称名寺式などで、石器では石鏃・打製石斧・磨石・石錘など8種類、少量ながらサザエ・ハイガイ・マガキなどの貝類が見つかったと云う。 |
 遺跡現場 遺跡現場 |
本遺跡の範囲は正確には分かっていないが、現在の当小学校の敷地を含めその北側に中心を持つと見られている。 出土遺構・遺物などから墓域としての性格を持つ。 |
|---|
 深鉢土器
深鉢土器
 注口土器
注口土器
 小型壷
小型壷
写真の通り加曾利B式土器が多く認められたが、中には堀之内式の鉢形土器を被せた甕被葬の人骨が発見され、 全国的にも余り類例を見ない埋葬形態を持ったこの人骨は壮年男性で、上顎の切歯に抜歯が認められたと云う。 全国的にも余り類例を見ない埋葬形態を持ったこの人骨は壮年男性で、上顎の切歯に抜歯が認められたと云う。何らかの理由で身内から忌み嫌われ、祈り払われた埋葬の姿かも知れない。 |

 以下大磯町内の代表的縄文遺跡を紹介する。
以下大磯町内の代表的縄文遺跡を紹介する。
