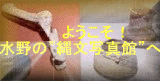
| 滋 | 賀 | 県 | 守 | 山 | 市 | の | 下 | 之 | 郷 | 遺 | 跡 |
|
下之郷遺跡は三上山を頂点として広がる野洲川下流域扇状地の末端に位置する、弥生時代中期(紀元前2世紀後半から1世紀初め)の環濠集落遺跡。 ここの場所は地下の伏流水が地表に湧き出してくるような水源地帯に辺り、集落形成に適した生活拠点であった。又豊富な地下水のお蔭で、木製品など遺物の保存状態が非常に良く、県内でも最も優れた生活・文化情報を残している重要な遺跡と云われている。 昭和55年、下水道工事に伴い弥生時代の土器・溝などが発見されて以来、発掘調査は今回を含め55回に及び、その間大きく且つ多くの濠・井戸跡などの遺構、多量の土器・石器・木製品などの遺物が出土し、中でも9重の環濠を巡らした大規模な弥生「ムラ」であることが判明した。 |
 発掘現場Ⅰ
発掘現場Ⅰ
 発掘現場Ⅱ
発掘現場Ⅱ
 発掘現場Ⅲ
発掘現場Ⅲ
|
本遺跡は「環濠」と呼ばれる大きな溝がムラの周囲に巡らされていて、東西約670m・南北約460mの楕円形を成した約25haの巨大集落跡。
今回第55次の発掘調査では、掘立柱建物3棟・壁立式建物2棟が見つかっている。 今回検出された建物跡は、以前の調査で確認された建物の軸線とも符合するため、区画溝を持つ建物が整然と計画的に配置されていたと見られる。 これら掘立柱建物は屋根の棟木を両端で支える棟持柱があることから、集落全体の宗教儀式・集会などを行なう建物と見られる。
本遺跡は計画的に配置された建物跡としては最古とされる、大阪府の池上曽根遺跡(紀元前1世紀)よりやや遡り、当時の近畿地方の中核集落であることは間違いなく、 |
|
本遺跡からは写真の通り、打製・磨製の石鏃、石剣・環状石斧、戈や柄、弓や楯、銅剣など、他の近隣弥生集落の4倍ほどに達する武器が見つかっており、当時集落の生き残りをかけた「争い時代」を物語っている。 特に銅剣は黒光りする青銅製で先端が鋭利に尖り、全長21.5cmもあり、発見当時茎の下の部分が強い衝撃で折れていたと云う。 形態的特徴から北部九州で発見された銅剣と酷似しているが、滋賀県下では初めてという大変珍しい遺物であった。
これらの武器類は環濠や集落内へ外敵が侵入できないように設けられた棚の出入口周辺から見つかっており、又焼け焦げた弓など、 稲作が定着し、生活が豊かになってくると、外敵に備えるために集落を大きな溝や棚で囲み、将に環濠集落を創り上げていった。
守山市内には本遺跡の他、二ノ畦・横枕・山田町・服部などの弥生集落遺跡が見つかっている。
本遺跡はおよそ2,100年前に戦いや自然災害からムラを守るために厳重な施設が造られ、近隣ムラと戦い、生き抜いた跡であり、やがて |
 「倭のクニ」の一つとしてやがて統一されていくその成立過程に当る集落と考えられる。
「倭のクニ」の一つとしてやがて統一されていくその成立過程に当る集落と考えられる。 次に石剣・石鏃、青銅製戈と石鏃、弓矢、木製楯、青銅製刀剣など当時集落の生き残りをかけた「争い時代」について紹介する。
次に石剣・石鏃、青銅製戈と石鏃、弓矢、木製楯、青銅製刀剣など当時集落の生き残りをかけた「争い時代」について紹介する。
