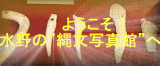
|
|
|
豊里遺跡は女満別町中心部から南西方向およそ5.5kmの地点で、網走川西岸の標高8mほどにある河岸段丘辺縁に位置する。 豊里縄文人は石刃を加工して石鏃を作る、旧石器時代の流れに属する独特の技術を持っていた集団で、この“石刃鏃文化”の源流は中国の東北地方・東シベリヤ地方・サハリン海岸地方などに分布しており、道内では東部海岸(オホーツク海沿岸・釧路・根室・十勝地方の沿海岸地帯)の低位段丘上に限定されている。
本遺跡は道内で最大規模と豊富な石器類を誇り、氷河期が終わりを告げ、地球上が温暖になりつつあった約8,000年前頃に中国の東北地方・東シベリヤ地方などから北海道東部に移ってきたと見られている。 |
 遺跡現場 遺跡現場 |
本遺跡付近は約8,000年前頃には段丘の裾を海水が洗い、陸地ではモミ・トウヒなどの針葉樹やコナラ・シラカバ・ヤナギ・ブナなどの落葉樹が生い茂り、現在より2~3度暖かであったことが分かっている。 叉出土遺物にはイルカ・トドなどの海獣、エゾシカ・クマなどの陸獣、ニシン・ヒラメ・カレイなどの寒冷系の魚類及びブリ・スズキなどの暖流系魚類などが混じっていることからも、気温が現在より温暖であったことが窺える。 |
|---|
 石刃鏃
石刃鏃
 石刃Ⅰ
石刃Ⅰ
 石刃Ⅱ
石刃Ⅱ
|
石刃は生きるための基本的道具として黒曜石を打ち欠き、刃物(ヤジリ)として使われた文化で、大量の黒曜石を不可欠としていた。 石刃は刃の部分が磨耗し易く、大量に必要としたため、一定の方法で連続して打ち欠く技術と黒曜石のような適当な石材を考え見出したと見られる。 |
 石錘・掻器
石錘・掻器
 尖頭器・磨石
尖頭器・磨石
 石斧・砥石
石斧・砥石
|
石刃と共に出土した石器類には、写真の通り石斧・石錘・砥石・掻器・削器・石核など多様性に富み、当時の石刃鏃文化期の生活様式を窺い知ることが出来る。 これらの石器類以外にも凹石・石皿・磨石・尖頭器などの生活必需品と共に、大半が垂飾という装身具も多量に見つかったと云う。 これらの石器類は旧石器時代の終わり頃から縄文時代の初め頃に使われていたと考えられる。 |
 土器片 土器片 |
紐を木片などに縛り付けて土器上を転がして付けた組紐圧痕文様のほか、刺突文・竹管文の文様を持つ“女満別式土器”が出土している。 これらの文様土器が石刃及び石刃鏃と一緒に出土したことから、  縄文早期時代の石刃鏃文化に位置付けている。 縄文早期時代の石刃鏃文化に位置付けている。
|
|---|
| 石刃鏃文化の代表的遺跡として、本遺跡のほか北海道浦幌町の新吉野台・共栄B遺跡や常呂町のトコロ貝塚を今回取上げているが、それぞれご参照頂きたい。 |

