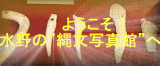
千 葉 県 千 葉 市 の 月 ノ 木 貝 塚
|
月ノ木貝塚は、縄文中期から後期にかけての巨大環状貝塚で、支川都川に向かって突き出た舌状台地上に所在する。
本貝塚は、この台地の先端部、東西150m・南北200mほどの範囲に形成されたが、後世に地形改変の痕跡が見られ、中世に“月ノ木砦”が築かれた際に、切り取られたかもしれない。
1978年に“国史跡”に指定されたが、
|
|
舌状台地の中央部を囲むように竪穴住居を建て、周辺に貝を廃棄していったため、環状貝塚が形成されたと見られる。 写真に見える送電線鉄塔の東南約30mの地点が発掘調査されただけだが、縄文中期を中心とした大型環状貝塚であることが判明。 |
 斜面貝塚
斜面貝塚
 散布貝殻類
散布貝殻類
|
写真のように、台地斜面に貝層が伸びており、斜面貝塚の様相を呈している。
中央部分の地表では貝殻が見つかっておらず、ぐるっと環状に貝殻が散布されている。
貝類は、ハマグリとイボキサゴが主体で、他にはアサリ・シオフキ・ウミニナなど砂浜に棲息する仲間。
一方少量ではあるが、大型ハマグリを焼いた跡も見つかっているから、大型は焼ハマグリにしているなど、 当大型環状貝塚は、干貝加工の工房であり、中央部は作業場であったかもしれない。 |
 復元住居
復元住居
 クジラの骨
クジラの骨
|
写真は、復元された竪穴住居跡及び出土したクジラの脊椎骨。 1951年の発掘調査では、竪穴住居跡のほか、タカラ貝製装身具・アワビ貝殻を使った耳飾りなどの装身具、クジラ・エイ・サメ・フグ・タイなどの魚骨、イノシシなどの獣骨が検出された。
本貝塚東側の谷面には、現在でも栗林があるが、 |

 貝層部が破壊され、当時の集落跡は保存されていない。
貝層部が破壊され、当時の集落跡は保存されていない。
 以下の写真は、“月ノ木貝塚公園”として保存された場所で、公園外には草地・山林・畑などが広がり、叉本貝塚脇には支川都川が流れている光景をご覧下さい。
以下の写真は、“月ノ木貝塚公園”として保存された場所で、公園外には草地・山林・畑などが広がり、叉本貝塚脇には支川都川が流れている光景をご覧下さい。
