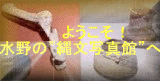
| 長 | 野 | 県 | 上 | 田 | 市 | の | 八 | 千 | 原 | 遺 | 跡 |
|
八千原遺跡は神川の河岸段丘上にあり、平成元年に圃場整備事業に伴う発掘調査結果、縄文中期初頭から後期までの遺構・遺物が多数検出された。
縄文中期は日本列島で縄文文化が最高潮に達した時期で、とりわけ長野県の中部高地は“縄文天国”と呼ばれるほど発展振りを見せた。 |
 遺跡現場Ⅰ
遺跡現場Ⅰ
 遺跡現場Ⅱ
遺跡現場Ⅱ
|
本遺跡の発掘調査により、上田地方にも大規模な縄文集落があったことが初めて確認され、竪穴住居跡は全体で68軒検出され、そのうち床面に平石を敷いた“敷石住居”が34軒と全体の半数を占めた。 更に埋甕27基・土壙8基などの遺構も見つかっている。 |
 以下文字列にポインタをおくと、当地独特の土器文化が窺えますよ! 以下文字列にポインタをおくと、当地独特の土器文化が窺えますよ!  |
|
縄文中期の阿玉台式系統の土器や曾利式土器、後期の堀之内Ⅰ式土器など関東地方の影響が強く見られる。 一方照明具説や香炉説がある“吊手土器”は中部高地を中心に流行し、又酒の醸造具説や口縁部下の孔に皮を張って太鼓として用いたとする説などがある“有孔鍔付土器”も中部地方から北陸地方を中心に分布している。
関東地方の影響を受けつつも、
|
|
黒曜石製石鏃・蛇紋岩製磨製石斧・頁岩製打製石斧・多孔石・石皿・石錘・磨石など実用に供せられた多数の石器類が検出された。 これらの石器類からドングリ・クリ・トチなどの堅果類、ヤマイモ・ユリなどの根菜類、ワラビ・ゼンマイなどの植物性食糧を中心に、弓矢による狩猟の対象となったイノシシ・ノウサギ・キジなど、又川・湖沼での漁労活動を裏付けるコイ・フナ・サケ・マスなど、豊かな食生活が垣間見える。 |
 阿玉台式深鉢土器
阿玉台式深鉢土器 特異な土器文化を持っていたと云える。
特異な土器文化を持っていたと云える。
