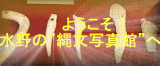
| 千 | 葉 | 県 | 銚 | 子 | 市 | の | 余 | 山 | 貝 | 塚 |
|
余山貝塚は利根川河口域に形成された沖積低地上、標高約7mに立地する縄文後期から晩期にかけての貝塚として全国的に知られている。
長軸約140m・短軸約70mの広がりを持ち、縄文から弥生・古墳・奈良・平安時代に至る長期間にわたって継続した遺跡。 |
 余山貝塚 余山貝塚 |
当貝塚は海退による海水準の下降により出来上がった微高地上に立地し、この微高地を砂州状に延びたもう一つの微高地が取り巻くように延びていることから、魚介類・水鳥などの生息場所として良好な自然環境であったと見られる。 更に後方の下総台地にも獣類が多数生息していたと考えられ、多くの縄文遺跡が長期間に亘り存続できたことは自然遺物や道具から想像できる。 |
|---|
|
当貝塚の特徴は、砂丘貝塚として製塩・貝輪製作・骨角器製作など生産活動の場としての機能が卓越する遺跡であり、埋葬・配石墓など当時の精神活動の場・祭祀地・墓域としての機能についても特徴的な遺跡として注目されている。 以下出土した遺物から、生産活動の場及び精神活動の場を象徴する貝塚の特徴を概観してみる。
 以下文字列にポインタをおくと、生産活動の場を象徴する遺物や精神活動の場を象徴するいろいろな遺物に出会えますよ! 以下文字列にポインタをおくと、生産活動の場を象徴する遺物や精神活動の場を象徴するいろいろな遺物に出会えますよ!  |
|
これら以外にも玉造・石器製作などの生産地として機能した痕跡や、石棒・異形台付土器・手燭土器など精神活動を裏付ける遺物が数多く出土し、又埋葬人骨も多数検出されたと云う。 当遺跡は数千年の長期間継続したことから、その間自然環境の変化と余山人の生活変遷並びに周辺遺跡群との相関関係など当遺跡にまつわる興味は尽きない。 |

 製作工程を表わす一連の貝輪
製作工程を表わす一連の貝輪