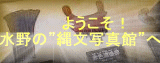
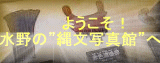
|
縄文人がどんな食物を採っていたかは、今日迄発掘された縄文遺物によりおおよそ見当が付く。 クリ・ドングリ・クルミ・トチなどの木の実の他、魚介類・鳥獣類などは今日我々が食している蛋白・脂肪源の中心的存在であり、調理加工法は別にして今昔大差ないと思われる。
しかし食材質や食住環境など様々な要因が重なり、遺物出土例から見ると魚介類・鳥獣類の遺骸やヤス・釣針・石錘・石鏃などの骨角製・石製捕獲用具が圧倒的に多い。 しかし縄文遺跡が語る食住環境は、食物採集の利便性を身近に据えた格好の場所が圧倒的に多いことは事実である。 |
 トチの実出土状況
トチの実出土状況 オニグルミの出土状況
オニグルミの出土状況 石皿と磨石の組合せ
石皿と磨石の組合せ
|
ドングリ・クルミ・クリなどの木の実は、アク抜きをしてから粉にしクッキー状にして焼くか、或いは動物の肉・鳥卵などと混ぜてハンパーグ状にして焼いて食べたと想像されている。
今日では90%以上の日本国民が虫歯と戦っていると云われているが、そのルーツは遠く縄文時代に遡る。 虫歯が食生活文化度を表す尺度とすると、縄文人の食生活文化水準が既に高かったことを物語っている。 |
 鳥浜貝塚のクジラの骨
鳥浜貝塚のクジラの骨 鳥浜貝塚のフグの骨
鳥浜貝塚のフグの骨
|
鯨やイルカの遺骸が特に北陸地方で数多く見つかっているが、湾内への追い込み漁法が既に相当発達していたと考えられる。
一方フグの骨も時折見かけるが、当時からフグの美味に見せられ命懸けで食していたと見られる。 美味・珍味を追い求めた縄文人の飽くなき食文化の伝統が今日迄受け継がれてきたと云える。 |
 木製スプーンとフォーク
木製スプーンとフォーク
|
縄文当時の鳥獣類の調理法は、主つとして木の実の粉に混ぜて加工して食べていたと考えられる。 丸のまま・或いはステーキ状にして焼き立てを箸のようなモノに挟んで、又は刺して食べていたとも考えられるが、ステーキとして食卓に載るのは木製フォークが作り出されてからではないかと考えられる。 食肉調理法の補助用具として木製フォークが発明されたと見られる。 一方木製スプーンはシジミ・アサリ・ハマグリなどの貝類のベストな調理法として、貝のダシ・塩分をそのままスープに取り込んだ縄文人の知恵を連想させる。 食生活用具は、縄文人の知恵を雄弁に物語っている! |