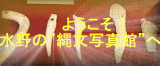
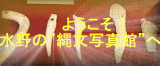
|
分銅形土製品は江戸時代に使われた秤の分銅の形に似ていることから“分銅形”と俗称されているが、弥生中期から後期にかけて住居跡に埋められた土中から見つかっている。 この土製品は岡山県南部を中心に、東は兵庫県から西は山口県、北は鳥取県から南は愛媛・徳島・高知各県など中国四国地方を主として、限定された地域から発見されている。
特に岡山県山陽町や鳥取県伯耆地方で各々50個以上の分銅形土製品が出土している。 これまでに見つかった全国約300点以上のほとんどが中ほどで故意に割られた状態で出土すること、眉・目鼻・口など顔を表現していること、縁の形が円形である点、中にはノコギリ状の歯・刺突や渦巻・線条・櫛目のような文様を施したモノや赤く塗られたモノもあるなどが共通している。 これからリアルな人物・顔を表現した分銅形土製品やデフォルメされたモノなど、典型的・特徴的なサンプルを紹介する。
 以下文字列にポインタをおくと、前半の4点はリアルな人物・顔を表現したモノ、後半の3点はデフォルメされた抽象的な人物・顔を表現した分銅形土製品に出会えますよ! 以下文字列にポインタをおくと、前半の4点はリアルな人物・顔を表現したモノ、後半の3点はデフォルメされた抽象的な人物・顔を表現した分銅形土製品に出会えますよ!  |
 特定家族の人物を表現したと見られ、割られた状態で住居跡に埋められていることから、特定家族の先祖の霊を祭り・鎮める祭祀用具として作られ・使われ、そしてこの祭祀風習が一部地域に伝播されたところで、時代の終焉を迎えたと考えられる。
特定家族の人物を表現したと見られ、割られた状態で住居跡に埋められていることから、特定家族の先祖の霊を祭り・鎮める祭祀用具として作られ・使われ、そしてこの祭祀風習が一部地域に伝播されたところで、時代の終焉を迎えたと考えられる。様々な災いから逃れるために、その原因と考えられた先祖の悪霊を鎮め・追い払う目的で一部の家族で使われた習慣が、同じような必要性を持った家族間に広められて行ったと推定される。 |