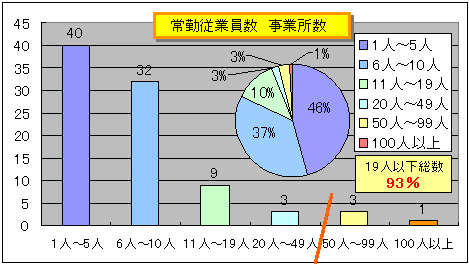
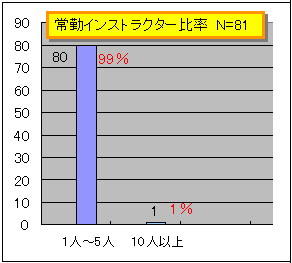
平成9年度のダイビング業界の傾向
資料提供・掲載許可:(社)レジャー・スポーツダイビング産業協会
「平成9年度ダイビング産業の実態に関する動向調査報告書」
(社)レジャー・スポーツダイビング産業協会が調査した業界の規模と産業としての傾向を見てみたいと思います。データの加工はホームページの管理者である私によります。
なお、ここでは日本のダイビング業界の全数を調査したものではありませんが、その調査数が多いこともあり、産業の現在の傾向を見るのに最適だと思います。
●ダイビングショップの常勤従業員数と事業所規模について
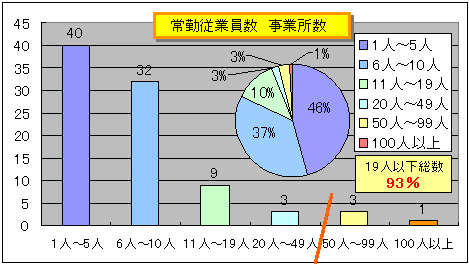 |
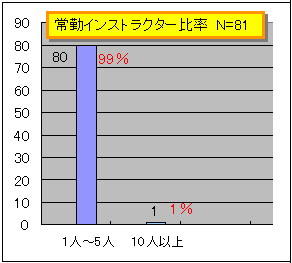 |
ここからは一事業所あたりの従業員数が10人以下が圧倒的であり、ここではダイビングショップの質は、会社としての組織としてよりもそのオーナーと従業員個人の資質が決め手になることが推定できます。
●一事業所の保有するダイビングサービスの店舗数(調査総数77件)と事業所当たりの年間売上高
|
このデータからも、オーナー=ショップそのものという業界の特徴がわかります。 | ||||||||||||||||
| 次にこれらダイビングショップの形態別に見た比率です。都市型とは一般に都市の中でダイビングの講習とツアーを中心とした事業を行っている店舗であり、リゾート型とはリゾート地で講習およびファンダイブ(ガイドツアー)などを事業としている店舗です。 | |||||||||||||||||
|
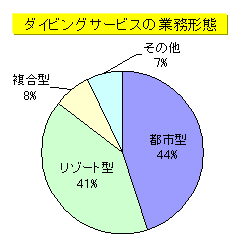 |
||||||||||||||||
ではその売上は規模はというと以下のようになっています。
H8(1996) |
H9(1997) |
|||
売上高 |
度数 |
% |
度数 |
% |
1〜1000万円 |
19 |
23.2% |
18 |
22.2% |
1000〜3000万円 |
27 |
32.9% |
27 |
33.3% |
3000〜5000万 |
13 |
15.9% |
13 |
16.0% |
5000万〜1億円 |
13 |
15.9% |
17 |
21.0% |
1億円以上 |
10 |
12.2% |
6 |
7.4% |
●講習生やダイバー達と直接触れ合うインストラクターの経験年数の構成について
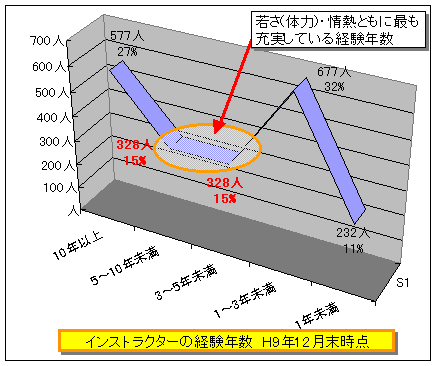 |
この事実から重要なことは、若さ(体力)・情熱ともに最も充実していると思われるインストラクターが減ってきていることであり、インストラクターという職業に従事することが魅力の薄いものになってきているのか、あるいは「生活」を支えることが難しいゆえにか、今後のダイビング業界の発展を占う上で研究の余地があると思われる。 |
●優良ダイブショップの連携の必要性
このように小規模事業所が圧倒的に多い業界の特性から、大手認定証販売会社(彼らは「指導団体」と自称している)の支配が避け得ないものとなっています。優良ダイビングショップは日本国内でも、主として日本人をマーケットとしている外国でも、私の知る限りまじめで優良ダイビングショップほど冷遇されていると思われます。そのためにはそれらダイビングショップ間の連携と、情報の事故情報のスムーズな流通が必要と言えます。