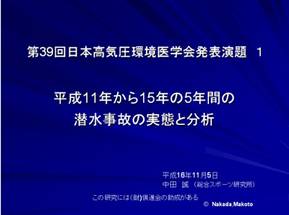 これまでダイビング事故を語る際には、どの学会でも、事故数を、事実上その一部の統計発表のみを取り上げて全体かのように扱っていたことから、それを是正し、また事故の原因について語る際にも、これまでは業界の意向を全面的に「配慮」した上で加工された後のデータを生データとして無批判で使用するという、科学的では分析根拠を使う例が著しく見られたことから、私が平成11年から15年の5年間に渡る直接の調査・分析、及びその生データの研究に基づいて、事故の実態の報告と、その防止及び救助対策の考察について発表を行った。
これまでダイビング事故を語る際には、どの学会でも、事故数を、事実上その一部の統計発表のみを取り上げて全体かのように扱っていたことから、それを是正し、また事故の原因について語る際にも、これまでは業界の意向を全面的に「配慮」した上で加工された後のデータを生データとして無批判で使用するという、科学的では分析根拠を使う例が著しく見られたことから、私が平成11年から15年の5年間に渡る直接の調査・分析、及びその生データの研究に基づいて、事故の実態の報告と、その防止及び救助対策の考察について発表を行った。平成16年の学会活動報告
平成16年11月、12月の学会活動について報告します。
私が事故問題や事故被害者の事故後の苦難、またそれについて伴う法的問題について研究することには、業界では一部の良心的事業者を除いて、積極的な無関心が業界標準となっているように感じます。そのため昨年も、事業と生活を支えてくれている消費者の生命・身体の安全を確保することで、ひいては自らのビジネスリスクを減らそうという考えに賛同を表明し、その研究の支援や、その成果に、「業界」として興味を示されることはありませんでした。
したがって、脆弱な個人の研究活動としては、以下でお知らせする程度の活動がせいいっぱいでした。
力不足はお許しください。
1.
日本高気圧環境医学会助成研究発表(2題)
(平成16年11月5日 海運クラブ)
1題目 「平成11年から15年の5年間の潜水事故の実態と分析」
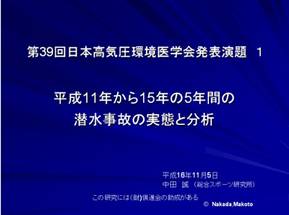 これまでダイビング事故を語る際には、どの学会でも、事故数を、事実上その一部の統計発表のみを取り上げて全体かのように扱っていたことから、それを是正し、また事故の原因について語る際にも、これまでは業界の意向を全面的に「配慮」した上で加工された後のデータを生データとして無批判で使用するという、科学的では分析根拠を使う例が著しく見られたことから、私が平成11年から15年の5年間に渡る直接の調査・分析、及びその生データの研究に基づいて、事故の実態の報告と、その防止及び救助対策の考察について発表を行った。
これまでダイビング事故を語る際には、どの学会でも、事故数を、事実上その一部の統計発表のみを取り上げて全体かのように扱っていたことから、それを是正し、また事故の原因について語る際にも、これまでは業界の意向を全面的に「配慮」した上で加工された後のデータを生データとして無批判で使用するという、科学的では分析根拠を使う例が著しく見られたことから、私が平成11年から15年の5年間に渡る直接の調査・分析、及びその生データの研究に基づいて、事故の実態の報告と、その防止及び救助対策の考察について発表を行った。
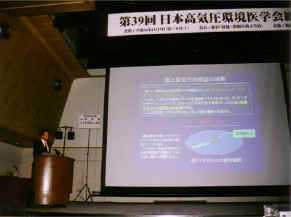 左は発表している様子。
左は発表している様子。
2題目 「スクーバ・ダイビング実行段階別の脈拍及び血圧変化の傾向調査の試み」
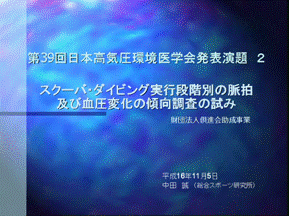 この調査・研究は、多数のボランティアダイバーの協力と、財団法人倶進会の助成があって初めて実現したものである。
この調査・研究は、多数のボランティアダイバーの協力と、財団法人倶進会の助成があって初めて実現したものである。
この調査の結果、ダイバーの安全にかかわる多くの示唆が見られた。
 1次調査会で協力してくれたボランティアダイバーとベテランのプロ及び立会いの医師の方々。(2次でも何人ものボランティアダイバーの協力があった。大感謝です。)
1次調査会で協力してくれたボランティアダイバーとベテランのプロ及び立会いの医師の方々。(2次でも何人ものボランティアダイバーの協力があった。大感謝です。) 左はそれを発表している様子。
左はそれを発表している様子。
なおこの総会では海外からの報告者やシンポジウム参加者もあり、11月5日、6日と、2日間に渡って行われた。
2.日本旅行医学会講演
(平成16年11月18日 東京体育館)
「スクーバダイビングの事故及びリスクマネジメント」
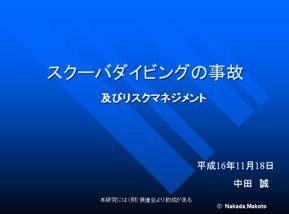 左記の題で講演を行う。
左記の題で講演を行う。
講演が50分程度、そして20分程度の質疑応答があった。

なお当日は、スポーツ事故問題に関心を寄せている著名な法学者や、最愛の家族をダイビング事故で亡くされた方、また植物状態となったお子さんを何年にも渡って毎日介護しながら苦労なさっている親御さんなども聞きに来られていました。
3.日本スポーツ法学会研究発表
(平成16年12月19日 早稲田大学)
『「商品スポーツ」の法的責任』
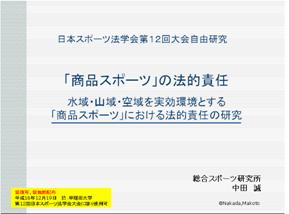
この発表では、数多くのダイビング事故裁判(判例集未掲載、また最高裁の判例データベースにも乗せられていない最新の判例や、一般に注目されにくい海事審判採決も紹介し、ダイビング事故を中心として、その展開として、ラフティング、カヌー、(以上水域)、ガイド付き有料ツアーである散策登山(以上山域)、パラグライダー、ハングライダー、タンデムジャンプ(以上空域)についても言及して発表した。
この発表には、ダイビング事故でご遺族となったり被害者となった方の家族の方々や、空域事故裁判支援弁護士なども聞きに来られており、この研究に対して少なからず関心が寄せられた。
 左は他の発表者と共に、発表後の質問を受けている様子。
左は他の発表者と共に、発表後の質問を受けている様子。
このページへの直接のリンクはご遠慮ください。
平成17年1月27日