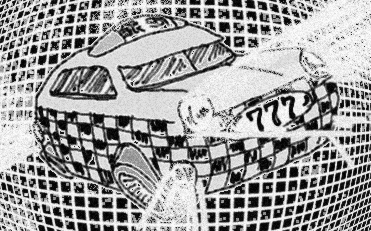
私は今日の仕事を終え帰路に就いた。 私は家族と離れて一人住まいの状況にある。月に一度、第三金曜の夜は我が家まで帰ることに決めていた。 今日はその第三金曜なので帰宅の準備をして出社してきた。しかし顧客のクレーム対応で仕事が遅くなり、もう最終バスも2時間前となる時間になってしまっていた。 「お客さん、どちらまでですか?」 運良く近くにはタクシー乗り場があった。金曜の真夜中なので酔っぱらいの帰宅を待ち受けていたのだろうか客待ちの車が何台か止まっていた。私はその先頭の1台に乗り込んだ。 「火星のグリーンピース地区までお願いできるかな」 私が行き先を告げるとドアが閉まった。 「火星...火星ですか?」 「だめかい?」 「いえとんでもない、その逆で大喜びですよ、いやあ粘った甲斐があった。もう帰ろうかと思ってたんですがね...」 火星が地球の衛星都市として開発されてからもう80年になるそうだ。人類の惑星の開拓はその英知の進歩と共に留まるところを知らず、今では土星にまで及んでいる。私の稼ぎでは地球上に家を持つことは難しく、新しく建てた家は家族と共に遠い火星にある。 「やっぱり長距離は嬉しいものなのかい?」 「そりゃあもう、なんてったって1回で1日のノルマがクリアですからね。地球の中を一日中行ったり来たりの小銭集めを考えれば...おっといけない、決して近距離のお客さんが迷惑だと言ってる訳じゃあないんですよ、四国でも九州でも、いえ埼玉でも静岡でも大事なお客様に違いはないですからねえ、そういうお客さんに役に立ってこそ、この仕事が社会に貢献できるというもんでしょう」 「ははは、運転手さん無理しなくていいよ、素直にいこうよ」 「はいすいません、失礼しました...でも駅前タクシー乗り場のあの『お近くでもご利用下さい』って看板、あれは良くないですね、あれじゃあ『ホントは近距離はイヤなんだよ』って言ってるようなものじゃあないですか、どうせ書くなら『近距離お断り』とすればいいのに、それが素直だというもんでしょうね」 「はははは」 その運転手は料金メーターを倒し、その手でギヤをローに入れ車を発進させた。私の乗ったそのタクシーはオフィスビル群の窓にその姿を映しながら滑るようにスピードを上げていった。屋根の上に「銀河」と書かれたマークを灯したそのタクシーはビルの谷間を抜け地球を飛び立った。 「お客さん、こんな遅くまで仕事ですか」 そう言ってタクシーの運転手はこちら側へ振り返り、初めてその顔を私に見せた。 見るとその運転手は白髪が大部分を占める初老といった感じで、人なつっこいおどけたまなざしを見せていた。 「ああ、お客は定時で帰してくれないね、せっかくの週末だというのに」 「世間の皆様は今頃飲んだくれているか歌い明かしているか寝ているかというのに大変なことですね」 「でも運転手さんだってまだ営業中なんだろう」 「まあそうですが...お客さん、電離層を出ますんでシャッター上げさしてもらいますよ」 運転手はそう言って宇宙線防護シールドで車の窓を遮蔽した。外の景色は(景色といっても真っ暗な空だけなのだが)少しの間見えなくなったが、すぐに室内のガラス窓に内蔵されたプラズマ映像が同じ風景を蘇らせた。 「ところでお客さん、私も上客に恵まれてラッキーですが、お客さんも運がいいですねえ、この車のナンバー見ました?」 「ナンバー?」 タクシーに乗る毎にナンバーを確認する者などいないだろう、この運転手は何を言いたかったのか分からずに困った顔をしてやるとそのうち運転手がルームミラーにニヤニヤした顔を映してこう答えを言ってきた。 「この車の星間営業ライセンスナンバーですよ...つまりナンバープレート、この営業車のはね、777なんですよ」 「ほほう、確かにそりゃラッキーナンバーだ」 「そうでしょ、でもただのラッキーじゃあないんですよ、私はこのナンバーを手に入れるために抽選会へ30回も通ったんですよ。ちゃんと元手がかかった、自力で勝ち取った幸運なんですよ」 「30回も、そりゃあすごい」 「それだけじゃないんですよ。このタクシーはね他の営業車にないような装備が満載されているんですよ、例えばほらお客さん、そこのグリーンのスイッチ押してみて下さいな」 「グリーン?」 私は運転手に言われるままセンターコンソールにあったグリーンのスイッチを押してみた。すると今まで天井だと思っていた一部分がせり出しながらスライドし、目前に3Dスクリーンが現れた。 「若い人向けに3Dテレビゲームとユニバーサルネット、ご老人向けにヘビメタとヒップホップのカラオケセット、女性には恋愛ムービー、子供にはアニメ、ペット用に環境ビデオ...」 「これは何と...」 「ドリンクサービスもございます、ブルーのボタンでどうぞ、料金は頂きませんのでご自由にどうぞ」 「これはいい、ビールもあるぞ」 「あと軽いスナックとおつまみ、それから自動マッサージ機、自動散髪機、簡易トイレ、小型洗濯機に乾燥機と」 「こりゃあ驚いた、うちの社長専用車にもここまでの装備はないよ」 「へへへーっ、それが私の自慢なんですよ。お客さん嬉しいこと言ってくれますねえ」 「こんなにサービスしちゃっていいの? 維持費だって大変でしょ?」 「そりゃあもう自腹ですよ、こういうサービスは私みたいな個人タクシーには許されてるんですけどね、それを別料金にするのは営業法に引っかかるのでお金は頂きません」 「というとこれは、やっぱり営業努力っていうヤツ?」 「いえねお客さん、それがタクシーってのは因果な商売で、こうやっていくらサービスに心がけてもそれが直接収益にはつながらないんですよ。だってそうでしょ、お客さんだってこの777号に乗りたくて乗った訳じゃない、また777号に乗りたいと言っても乗れる訳じゃない、たまたまいた場所にたまたまのお客様がたまたまの順番で乗ってこられる...いわば巡り合わせというヤツですかね。それでも2度目のお客さんなんかもたまにいらっしゃって『また乗れて良かったよ』なんて言ってくれるんですよ、そのおかげでお客さんと話題もできるし私も気分良く運転が出来る、言ってみりゃこのサービスは私自身のためにやっている様なもんですかね」 「運転手さん、謙遜しちゃっていい人なんだね」 「ありがとうございます、でもね、元はと言えば、私はただこうやってお客さんとお話しをするのが好きなだけなんですよ。やっぱり何かの縁で巡り会った以上はお互いの身の上話とか話相手になって欲しいじゃないですか、私は見ての通り星空に一人で願い事を語るようなロマンチストじゃないですからね、だけどお客さんの中にはおしゃべりが嫌いな方もいらっしゃる、そういった方には私も黙ってるようにはするのですがこの車の中でたった二人がずーっと黙り込んでるところを想像してみて下さいな、気まずいもんですよ、それを考えればこのサービスでお客さんが楽しんでてくれれば私も気楽になれると言うもんです」 「うん、これだけ揃っていれば火星までの間の暇つぶしには事欠かないよ」 「そうそう、実は新しいゲームを取り入れたんで、お客さん一つ試してみませんか」 「ゲーム?」 運転手がそう言ったのは『タクシーでGO』というシュミレーションゲームで、仮想の町でタクシーを流しながらいくつかの障害をクリアしていくゲームだった。 このゲームが傑作だった。この777号にはゲームと連動するシステムが備わっており、私がゲームの中で操作する通りに777号も向きを変えたりスピードを変えたりした。窓ガラスのプラズマ映像にゲーム画面が映し出されるためその臨場感たるや現実の運転と錯覚するほどであった。このゲームは運転手もお気に入りらしく、私の運転に『そこ右、加速、上昇上昇!』といっしょにゲームに興じていた。 お手本を見せてもらおうと運転手にもやってもらったがゲームの操作にまだ慣れていないらしく戦績は私とさほど変わらなかった。 このゲームのおかげで私は時の経つのを忘れるほどだった。子供の時分に帰ったように遊び、運転手と二人で大笑いしながら楽しく時を過ごした。たまたま拾ったタクシーのおかげでこんなすばらしい体験が出来るとは夢にも思わなかった。 いい加減笑い疲れて、私はドリンクのサービスを貰い一息入れることにした。乗車してからかれこれ2時間近くが経っただろうか。 「はははは、とても気に入ったよこのタクシー」 「ありがとうございます、それが何よりです。町で見かけたらこのスリーセブン号に声でもかけて下さいな」 「うん、是非に! おかげで時間も忘れて楽しかったよ」 「そう言って下さると私も甲斐があるというもんです、本当に時の経つのは...」 そう言葉を途中で切って、運転手は急にそわそわし始めた。ゲーム画面を消すと前方には丸い天体が白く輝いていて、その直径をどんどん大きくさせて近づいてきた。どうやら到着が近づいたらしい。運転手のそわそわはその到着に構えたためだろうと思った。 しかしあれだけおしゃべりな運転手がさっきから黙ったまま一言も話しかけてこなくなった。 何かトラブルでもあったのかと思い、私は運転手に問いかけた。 「運転手さん、どうかしたの? 急に黙り込んじゃって具合でも悪くなった?」 「...いえ、そうじゃあないんですが...」 そう言いながらその運転手はルームミラーでこちらの表情を伺う様にちらちらと何回か目配せを送ってきた。そしてそのうち何か考えがまとまったのか、また私へ話しかけてきた。 「...お客さん、もう2、3分で到着です。それでついでと言っちゃあなんですが、あと二つほどサービスさせて下さいませんか」 「そりゃあ豪華だな、まだこれ以上サービスがあるんだ、それも二つも...二つって、一つ目は何だい?」 「ええ、よろしければ料金を半額に致しましょう」 「本当かい? そりゃあ今日一番のサービスだ、何てったって安いに越したことはないからな。でも半額とは随分安いじゃないか、運転手さん大丈夫? 足が出るんじゃないの? 無理しなくていいんだよ」 「いえ、これはお客様がとてもいい人だということを見込んでなんですよ。お客さんがこんなにいい人じゃなかったらとても言い出せなかったと思うんですけど、お客さんホントにいい人だから...」 妙に「いい人」にこだわる言い方が気になったがそんなうまい話を断る理由もなく私はその好意を素直に受け入れることにした。 「それで二つ目は何?」 私をどこまでも喜ばせようとしてくれるこの運転手、こんな人情的な体験は久しぶりだった。私は自宅へ帰ったらこの心温まる話を家族にもしてやろうと思った。 「...それで二つ目なんですけどね」 「うん、一体何だい?」 「驚かないで下さいよ」 「そうもったいぶられると少し後ろめたい気が起こるじゃないか。これ以上どんなサービスで僕を喜ばせようと言うんだい?」 見ると鮮やかな彩りの光を放つタクシー発着場が目前にまで迫っていた。遠くからでもその位置が分かるようにライトアップされ、そこはまるで宇宙の灯台といった風だった。そこには観光客用の大きな看板があり、イルミネーションの光に照らし出されていた。 「実はお客さん、時の経つのは早いもんで...オマケして木星までにしときました、エヘヘヘヘ...」 上空からでもよく見えるその看板には「ようこそ木星へ」と大きな文字が書かれていた。 |