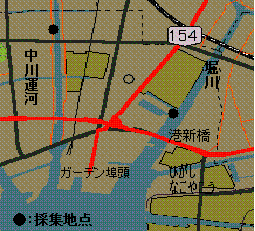�`�`���E�J�C�~�h���K�j(Carcinus mediterraneus)�͒n���C�ɕ��z���郏�^���K�j�Ȃ̃J�j�Łi�r�c, 1989�j�A1958�NHolthuis��Gottlieb�ɂ��ʎ�Ƃ����܂ŋ߉���̃~�h���K�j(Carcinus maenas)�ƍ�������Ă����i�瓇, 1997�j�B�b�k�̌`�߉���̃~�h���K�j��C�V�K�j�ɔ�b�k����⋷���A5�p�`�ɋ߂���ۂ��A���҈�̗��N���������߁A�O������5���͔���o����ۂ���ق��A�Y�̌����̌`�~�h���K�j�̌����قǘp�Ȃ����A���E�̌����̊����1/3����悪�قڂ܂��������s�i����, 1986�j�Ɉʒu����B���É��`�ō̏W���ꂽ�̂����̓����ƈ�v���Ă���B
�܂��A���^���K�j�Ȃɑ����Ă��邪�A�K�U�~��C�V�K�j�̂悤�ɑ�4���r���I�[����̗V�j�r�ɂȂ��Ă��炸�A���̕��r�Ƃقړ��^��ł��邱�Ƃ�A�b�k�ɂ����������Ȃ��A���r����r�͗Ί��F�ō������_���_�݂��邱�ƁA�b�k�̌㉏�͒����I�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��������̓������݂���B
����܂ł̋L�^
�@�`�`���E�J�C�~�h���K�j�iCarcinus mediterraneus�j�̍ŏ��̕�1984�N3���ɒr�c�ɂ��i�r�c, 1989�j�̏W���ꂽ��Ɏ���ɂ���č��肳��i����, 1986�j�A�ŏ��ɕ��ꂽ�B���̌�A�r�c��1985�N7���ɁA���c�E�x�z��1985�N12���ɑ�����͌��ł̍̏W�i���c, 1993�j����Ă���B
�@�@�@�@�@ �} �P . �� �� ��
�@�@�@Fig..2.. (Carcinus mediterraneus),copulatory orban.
�@
�@����ɁA1995�N�ɓn粂������s�`�擌�����Y��w�W�D��t�߂œ��킪�唭���������Ƃ�i�n�,1995�j���Ă���ق��A1996�`1997�N�ɂ����āA�瓇�炪���p���k�`�������s�o�����`��9�̂��A1996�N10���ɗ���͌����Ukm�㗬�ŒE��k���̏W����A�����1997�N5���ɋ��Ǝ҂����k�`�ɓ��ꂽ�h���Ԃɋ��l���ꂽ�������Ă���i�瓇,
1997�j�B
���É��`�ł̏o��
���É��`���Ń`�`���E�J�C�~�h���K�j���������ꂽ�͖̂��É��`���ɗ�������x��ƒ���^�́i�}�P�j�ŁA1997�N7�����1998�N5���܂Ŏl�G�ɕt�������������s�����ہA1998�N5��18���ɒ���^�́u���C���v�E�݁A�x��u�����Q�R�����`�V���v�t�߉E�݂Ő��̂��̏W�����B����^�͂ō̏W���ꂽ�͍̂b��18.0�`21.0mm�Y�Q�́A�x��ō̏W���ꂽ�̂�24.0�`28.0mm�Y�Q�̂ł������B����^�͂ł̍̏W�n�_�͐��[��1.8m�ł���A�͌������}�傪�݂����Ă��邽�ߊ����ɂ�鐅�ʂ̕ϓ��͏��Ȃ��B�ꎿ�͊݊�肪���D�̏�ɕ��D���͐ς��ė��S���ɋ߂Â��ɂ�ăw�h����̕��D���͐ς��A�l�G��ʂ��ė������f�L�������B
�@�@�@�@
�@ �}�@�P �`�`���E�J�C�~�h���K�j�̏W�ꏊ�@�x��ł̍̏W�n�_�̐��[�ɂ��ẮA��ݒ����t�߂ɂ����č�]���ϊ����Ő��[0.5�`3.0m�ł��藬�S���t����6.8���Ɛ[���Ȃ�B��݂���3�`4m���ꂽ�ꕔ�ő�ʂ��`�`���E�J�C�~�h���K�j��喏W���݂��A0.25�u�ɂP�O�̒��x���݂�ꂽ�B���̒����n�_�ł͐��|�D��R���^���D���o���������邽�߁A�X�N�����[�̝��a���ɂ���ĕ��D�̑͐ς���r�I���Ȃ��D�����荻��ł��邪�A���S���ɋ߂Â��ƃw�h�����D���͐ς��Ă���A���n�_�Ƃ��ċG�ɂ͕n�_�f���������ɒ[�Ɋ��͈�������Ǝv��A�����p�ł̑唭���̕ꏊ�i�n�,1995 ;���c,1993�j�Ƃ悭�������ɂ�����̂Ǝv����B
Fig.2. Map showing the locality of collection
�@�x��ł̓C�\�M���`���N�ڂȂǂ̉Ԓ��ށA�P�t�T�C�\�K�j�A�e�i�K�G�r�ȓ��̍b�k�ށA�n�[�ȓ��̋��ނ��݂�ꂽ�B���ɂT�n�_�̕t�������������s�������A�C�b�J�N�N���K�j�A�P�t�T�C�\�K�j�A�C�V�K�j�A�C���K�j���̃J�j�ނ͖ڎ��ώ@����邪�A�`�`���E�J�C�~�h���K�j�͊ώ@����Ȃ������B
�@�@
���ԓI����
�@�X�L���[�o��p���������ώ@�ł̃`�`���E�J�C�~�h���K�j�̐��ԓI�����́A���^���K�j�Ȃɂ݂���V�j�r��p����������������тɓ�������悤�ȍs���݂͂��Ȃ����A�O������̐i���ɔ��ɕq���ȓ����s�����������B�܂��A�ǂ��߂Ď���߂Â��Ă��C�V�K�j��K�U�~�̂悤�ɍU���I�����s����Њd�p�����Ƃ炸�A������邾���̔�r�I���a�ȍs�����Ƃ�����A����������Ƌ[���s�����Ƃ�̂��݂�ꂽ�B�����ł̊ώ@�ł͗Y�����|�I�ɑ����݂��A�Y�����ЂƂ܂�菬�^�̎�������������Ĉړ�����Y�̂��݂�ꂽ�B
�@�܂Ƃ�
�@�`�`���E�J�C�~�h���K�j�̐��m�ȕ��z��͕s���ł��邪�A�~�h���K�j���܂߂����z��́A���Y�n�̒n���C���͂��߁A�A�t���J���k���A�i�o�X�R�V�A�`�o�[�W�j�A�E�p�i�}�p�Ȃǂ̑吼�m�����A�g�C�A�}�_�K�X�J���A�X�������J�A�I�[�X�g�����A�Ƃ���Ă���B
����܂œ��{�Ɉړ����Ă����O����Ƃ��ẮA�����T�L�C�K�C�A�~�h���C�K�C�A���[���b�p�t�W�c�{�A�A�����J�t�W�c�{�A�C�b�J�N�N���K�j�i���C�c, 1988�j�ȂǓ��p�ɐ�������킪�����݂���B��������D���̃o���X�g���Ȃǂɗc�����܂���A����ɕ��z���g�債�Ă��������̂Ǝv����B
�@�`�`���E�J�C�~�h���K�j�ɂ����Ă��p���̉͌��t�߂�^�͂̌�݂Ȃǂɐ������Ă��邱�Ƃ���A���ɑ��鋖�e�͈͂����ɍL���Ǝv���A�{��̓����p����p�̕��z�g��X���Ȃǂ��l���ɂ����ƁA���É��`�ɂ����Ă��p�����𒆐S�Ƃ��āA���z���g�傳��Ă������̂Ɨ\�������B���̍`�p�Ȃǂƍ��킹���É��`�ł̍���̓����ɒ��ڂ������B�@
�@�Ӂ@��
�@�Ō�ɁA�{��쐬�ɂ����蕶���̎��W��L�v�ȏ������������������{�����Y�������C�������瓇���M���Ȃ�тɌ��e�̍Z�{���������������s�����R�j�����َ�C�w�|���R���Ǖ����ɐS���犴�ӂ��܂��B
�@���p����
�r�c�@���D1989�F�����p�̃`�`���E�J�C�~�h���K�j
�_�ސ쌧�������فA�_�ސ쎩�R������(10), 83-85�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
����@�P�D1986�F����Ȃ���{�Y�I�ނ̑��Ǝ�ɂ����@
Researches on
Crustacea 15, 1-10.
��������D1969�F�`�`���E�J�C�~�h���K�j�������p�Ŕ������ꂽ�̂͂���
CANCER 5 29-30.
���c���ρD1993�F�����p�ɒ蒅�����`�`���E�J�C�~�h���K�j
�C�m�Ɛ���15(2),121-124
�n粐���D1995�F�O����̃`�`���E�J�C�~�h���K�j�������p�ɑ唭��
CANCER 4 9-10.
�������i�D1991�F���l�s�쓇���ӂœ���ꂽ�I��2�H���̋L�^
�_�ސ쌧�������فA�_�ސ쎩�R������
�@�@(12),45-47
���o�[���D1995.11.27�F�O���Y�~�h���K�j�ƃC�K�C�����p�ɑ�ʔɐB
��t����D1995.11.29�F�����p�̐��Ԍn�ɈٕρH�`�`���E�J�C�~�h���K�j�ȂNJO���Y�J�j�ƃJ�C����ʔ��B
���C�c���v�D1988�F�ړ���C�b�J�N�N���K�j�̐��ԁi�\��j
���{�x���g�X������A33�D34,79-89
���C�c���v�E�Ð��_�u�D1988�F�ړ���C�b�J�N�N���K�j�̓��{���݂ɂ����镪�z
���{�x���g�X������A
�@�@33�D34,75-78
�瓇���M�E�������h�V�E��������E�R�����i�D1997�F����p�Ō��������`�`���E�J�C�~�h���K�j
Nature
Study 43 (7),75-78