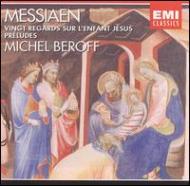メシアン(1908〜1992)は、ブーレーズの師匠でもあり、とっつきにくい作曲家と思っていました。それは今でもそう大きく変わってはいませんが、生誕100周年ということもあり、このところ何曲かまとめて聴いてみました。すると、なかなか良い曲である、と感じるようになってきました。
とっつきにくいということで、メシアンの音楽を知らずにいるということはもったいないと思い、私と同様なメシアン初心者向けに入門編ということで紹介してみることにします。
0.メシアンの一般的な知識
まず、メシアンの生涯、作曲家としての概要はこちら(Wikipediaです)。
ポイントは、熱心なカトリック教徒であること、鳥の声に詳しく音楽に取り入れたこと、そして和声に色彩を感じる能力を持っていたこと、というあたりでしょうか。ちょっと、神がかり的な音楽家だったわけです。
メシアン音楽語法については、とても詳しい方が、分かりやすく解説されていますので、参考にしてください。
「移調の限られた旋法」とか「逆行不可能なリズム」とか、知らないと煙に巻かれてしまいますが、これを読んで「まあ、そんなものか」という程度に理解すれば、何とかなりそうです。学者やメシアン一派の作曲家になろうとするのでなければ、基本的なことだけ分かっていれば大丈夫そうです。
また、今年2008年が生誕100周年であることで、メシアン生誕100周年公式サイトも設けられています。参考にしてください。
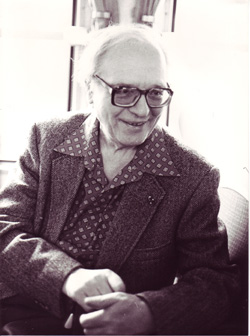 オリヴィエ・メシアン (1908-1992)
オリヴィエ・メシアン (1908-1992)
では、代表曲に体当たりしてみましょう。音楽としては、とても美しく、奥深いものが多いのです。
1.おすすめ・その1 「時の終わりのための四重奏曲」
まずのお勧めは、代表曲でもある「時の終わりのための四重奏曲」(あるいは「世の終わりのための四重奏曲」)。ピアノ、ヴァイオリン、チェロ、クラリネットという変則的な編成ですが、それはこの曲が第2次大戦中のドイツ軍の捕虜収容所(ポーランドのゲルリッツ収容所)で、たまたま捕虜として居合わせた演奏家に合わせて作曲・初演されたという事情によります。メシアン自身がピアノを弾いた1941年1月の初演は、5000人の捕虜たちを前に、零下30度の極寒の中、3本しか弦のないチェロや、鍵盤を押さえると元に戻らない調律の狂ったピアノなどによって行われたといいます。
曲は、聖書のヨハネ黙示録に基づくそうです(聖書の知識がないので、それぞれが何を象徴するのか分かりません)。8つの楽章からなり、8は、神による天地創造の6日と7日目の安息日の後、不変の平穏な8日目が訪れることに由来するとか。徹底して聖書の世界です。
時の終わりのための四重奏曲(1940) Quatuor pour la fin du temps
第1楽章:「水晶の典礼」
四重奏による夜明けの情景。メシアンの特徴である鳥が歌い始めます。
第2楽章:「時の終わりを告げる天使のためのヴォカリーズ」
ピアノによる和声の強打の上でのグリッサンドやトリルの後、中間部のヴォカリーズではヴァイオリンとチェロのハーモニクスのユニゾンに、メシアン自身が「ブルー=オレンジ」と表現したピアノの和音が彩ります。なんとも不思議な世界・・・。
第3楽章:「鳥たちの深淵」
クラリネット独奏による、鳥の歌を交えた息の長い音と、深さに満ちた静寂。
第4楽章:「間奏曲」
ヴァイオリン、クラリネット、チェロの三重奏。ユニゾンとアンサンブルが交互に出てくる印象的な旋律。ここにも鳥の歌が・・・。
第5楽章:「イエスの永遠性への賛美」
チェロとピアノの二重奏。チェロの息の長い旋律に、無限のときの流れを感じさせるピアノの和音。
第6楽章:「七つのトランペットのための狂乱の踊り」
四重奏による徹頭徹尾ユニゾン。メシアン独特の「付加リズム」による変拍子が特徴。
第7楽章:「時の終わりを告げる天使のための虹の混乱」
四重奏による、静と動の変化に富んだ曲。雰囲気としては、まるで「フィナーレ」。
第8楽章:「イエスの不滅性への賛美」
ヴァイオリンとピアノの二重奏。静かに、深く、永遠を歌い、瞑想的に幕を閉じます。
この曲のCDとしては、結構数多く出ています。ピーター・ゼルキン率いる「タッシ」のように、この曲を演奏するために結成された団体もあるほどです。
他の代表作である「トゥランガリラ交響曲」とカップリングされたものが2種類ありますので、このあたりから。一方はメシアンを得意とするミシェル・ベロフがピアノを弾いたもの、他方はメシアンの奥さんであるイヴォンヌ・ロリオがピアノを弾いたもの。
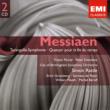 ミシェル・ベロフ(ピアノ)他 (サイモン・ラトル指揮のトゥランガリラ交響曲とのカップリング)
ミシェル・ベロフ(ピアノ)他 (サイモン・ラトル指揮のトゥランガリラ交響曲とのカップリング)
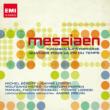 イヴォンヌ・ロリオ(ピアノ)他 (プレヴィン指揮のトゥランガリラ交響曲とのカップリング)
イヴォンヌ・ロリオ(ピアノ)他 (プレヴィン指揮のトゥランガリラ交響曲とのカップリング)
 タッシ(ピアノはピーター・ゼルキン)
タッシ(ピアノはピーター・ゼルキン)
また、今年(2008年)のメシアン生誕100周年の特別企画として、ピアニストの児玉桃さんが「メシアン・プロジェクト2008」として、日本各地でこの曲を演奏しています。日本だけでなく、ドイツのハンブルクでも演奏しているようで、ハンブルクでホルン修行中の方のブログ(この夏までウィーンにいらっしゃった方)にも載っていました。
児玉桃さんは、メシアン生誕100周年公式サイトでインタビューに答えてメシアンについて語っている動画が見られます。また、下の「まなざし」のCDも出しています。
さらに、2008年11月7日には、NHK教育テレビの「芸術劇場」で、8月に軽井沢で行われたこの曲の演奏会の模様が放映されていました。第3楽章「鳥たちの深淵」で、クラリネットのナイディックさんが循環呼吸を効果的に使っているのが印象的でした。
出演:堀米ゆず子(ヴァイオリン)、野平一郎(ピアノ)、チャールズ・ナイディック(クラリネット)、工藤すみれ(チェロ)
2.おすすめ・その2 「幼児イエスに注ぐ20のまなざし」
次のお勧めは、オーケストラ愛好家にはどうかな、とは思いますが、ピアノ曲の「幼児イエスに注ぐ20のまなざし」。題名のとおり20曲からなる組曲で、全体で100分を超える大曲ですが、これがなかなか良い曲です。ピアノ曲で、これだけの「色彩」を感じられる曲が作れるのだ、と感動します。ピアノ曲の好きな方、特にドビュッシーのピアノ曲の好きな方は絶対にはまります。
この曲も、第2次大戦のさなか、ノルマンディー上陸作戦を機に反攻に転じた連合軍によるパリ解放(1944年8月25日)前後に作曲が進められ、翌年1945年3月26日に初演されています。
「神の主題」「神秘の愛の主題」「星と十字架の主題」「和音の主題」という共通に使われている4つの循環主題があり、各々はメシアンの総合サイトに楽譜例も載っていますので参考にしてください。
幼児イエスに注ぐ20のまなざし(1944) Vingt regards sur l'Enfant-Jesus
第1曲 父のまなざし
第2曲 星のまなざし
第3曲 交換
ここで描かれる「交換」とは、神性と人間性の交流のことだそうです。
第4曲 聖母のまなざし
第5曲 御子を見つめる御子の眼差し
この曲で扱われるテーマは「子=イエス」を見つめる「子=御言葉」。
第6曲 御言葉によってすべては成されたり
第7曲 十字架のまなざし
第8曲 高き御空のまなざし
第9曲 時のまなざし
第11曲 喜びの聖霊のまなざし
第11曲 聖母の最初の聖体拝領
第12曲 全能の御言葉
第13曲 ノエル(降誕祭)
第14曲 天使たちのまなざし
第15曲 幼児イエスの口づけ
第16曲 預言者、羊飼いと東方の三博士のまなざし
第17曲 沈黙のまなざし
第18曲 恐るべき塗油のまなざし
このタイトルの意味するところは、非キリスト教徒にはよく分かりませんが、「キリスト」とはギリシャ語で「油を注がれた者」の意味、ヘブライ語の「メシア」も「油を注がれた者」の意味であることが関係しているようです。
第19曲 我は眠る、されど我が心は目覚め
このタイトルは、旧約聖書からの引用で、その意味するところは最愛の人を待ち望む魂だそうです。
第20曲 愛の教会のまなざし
お勧めCDは、ミシェル・ベロフが弱冠19歳で録音したデビュー盤が良いようです。他に、ピーター・ゼルキン、イヴォンヌ・ロリオ、児玉桃さんなど。
3.おすすめ・その3 「トゥランガリラ交響曲」
ピアノだけで色彩にあふれた曲を作る作曲家なので、オーケストラ曲はあまりにどぎつくなり過ぎるきらいがあります。オーケストラ愛好家には、「トゥランガリラ交響曲」を第一に勧めるのが筋なのでしょうが、この曲はあまりに極彩色過ぎて、個人的にはちょっと引いてしまいます。ということで、この曲は代表作とされていますが、上記の四重奏曲、ピアノ曲を聴いた後に聴くことをお勧めします。そうでないと、メシアンという作曲家を誤解する恐れがあります・・・(私もそうで、この曲から入ったためにメシアンが好きになれませんでした)。
メシアンの弟子であるブーレーズも、この曲を「淫売宿の音楽」といって嫌っているようで、メシアンを積極的に演奏・録音しているにも拘らず、この曲は録音していません。なお、この曲の初演はレナード・バーンスタイン指揮ボストン交響楽団だそうです。
ちなみに、「トゥランガリラ」とは、サンスクリット語に基づくメシアンの造語で、「愛の歌」「喜び、時、運動、リズム、そして生と死の讃歌」というような意味合いだそうです。また、オンド・マルトノという電子楽器が用いられており、独特のグリッサンドがなんともたまりません(快感だが気持ち悪い・・・)。
トゥランガリラ交響曲(1946〜48) Turangalila-Symphonie pour piano principal et grand orchestre
第1楽章 導入部
第2楽章 愛の歌・1
第3楽章 トゥランガリラ・1
第4楽章 愛の歌・2
第5楽章 星たちの喜び
第6楽章 愛の眠りの園
第7楽章 トゥランガリラ・2
第8楽章 愛の展開
第9楽章 トゥランガリラ・3
第10楽章 終曲
CDは、たくさん出ています。前出のラトル/バーミンガム市響、プレヴィン/ロンドン響に加え、チョン・ミュンフン/パリ・オペラ座バスティーユ管、若き日の小澤/トロント響、ケント・ナガノ/ベルリン・フィルなど。
4.おまけ 「峡谷から星たちへ」
もう一つ、ホルン吹きとして落とせないのは、1971〜1974年にかけてアメリカ建国200周年のために委嘱されて作曲した「峡谷から星たちへ」(独奏ピアノ、ホルン、シロリンバ、グロッケンシュピールと管弦楽のための)。
この曲を作曲するため、メシアンはアメリカのユタ州にあるブレイス峡谷とザイオン国立公園を訪れ、その雄大な自然にインスピレーションを得たそうです。
全体にわたり、砂漠と峡谷、メシアン特有の多彩な「鳥の歌」、ホルンによる「星の呼び声」、そして星のきらめき、宇宙の静けさに満ちています。
タイトルに鳥の名前がたくさん出てきますが、よく分かりません・・・。
峡谷から星たちへ(1971〜1974) Des Canyons aux etoiles... pour piano solo, cor, xylorimba, glockenspiel et orchestre
第1部
第1曲 砂漠
独奏ホルン、ウィンドマシンも登場します。
第2曲 ムクドリモドキたち
第3曲 星たちの上に書かれているもの・・・
第4曲 マミジロオニヒタキ
第5曲 シーダー・ブレイクスと畏怖の贈り物
(注)シーダー・ブレイクス:国立公園の名前。
ホルンのマウスピースによる「狼」の遠吠えも。
第2部
第6曲 恒星の呼び声
ホルン独奏による。
第7曲 ブライス峡谷と赤橙色の岩
第3部
第8曲 甦りしものとアルデバランの星の歌
第9曲 マネシツグミ
第10曲 モリツグミ
第11曲 ハワイツグミ、ソウシチョウ、ハワイヒタキ、アカハラシキチョウ
第12曲 ザイオン公園と天上の都
CDは、チョン・ミュン・フン/フランス国立放送フィル(ホルンはジャン=ジャック・ジュスタフレ)、サロネン/ロンドン・シンフォニエッタ(ホルンはマイケル・トンプソン)、コンスタント/フランス国立放送管(ホルンはジョルジュ・バルボトゥ)など。
以上、簡単なメシアン入門でした。気に入るかどうか、まずは聴いて、ご自分の耳で心で味わってみて下さい。
追伸:さすが生誕100周年ですね。メシアン・コンプリート・エディションという32枚組(それでも \11,176 )が発売されています。お買い得ですが、全部聴くかどうか・・・。
管弦楽作品集という8枚組( \8,892 )もあります。